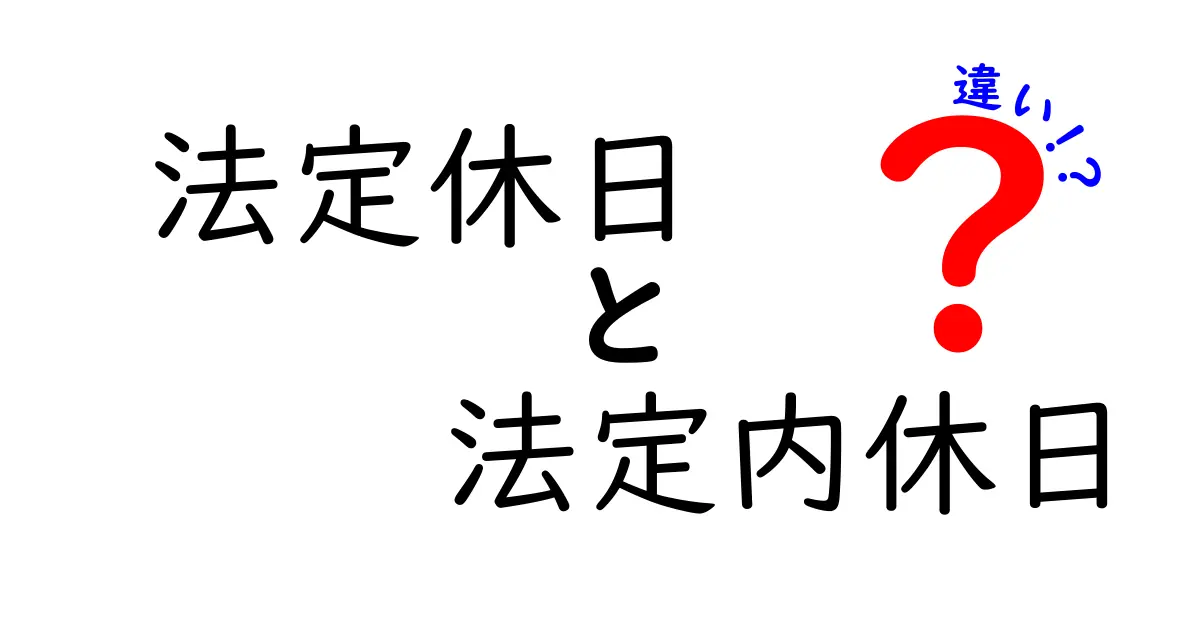

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
法定休日と法定内休日の違いを徹底解説
法定休日と法定内休日の違いを正しく理解することは、働く人だけでなく事業を運営する側にも大切です。法定休日とは、法律で決められている休み日で、原則として従業員に与えるべき休息日です。日本の労働基準法では、法定休日を必ず休ませる義務があり、企業はその日を労働時間の計算から除外することが求められます。これにより、働く人は心身の回復の時間を確保でき、過度な連勤を避けやすくなります。
一方、法定内休日とは、労働基準法で直接“休日”として定められているわけではなく、就業規則や企業の賃金規程で追加的に設定される休みのことを指します。法定内休日は、務め先の業種や繁忙度合い、月次の稼働状況によって設けられ、必ずしも全員に適用されるものではありません。法定内休日に関しては、代休の取り扱い・賃金の割増の適用・時間管理の方法が就業規則に依存します。
この二つを正しく使い分けるには、就業規則・労働契約書の条項を確認することが基本です。法定休日は「法で守られた休み」としての国家的役割を担い、従業員の健康と生活の安定を支える重要な役割を果たします。一方、法定内休日は「企業の裁量で設定される追加の休み」であり、同じ“休み”という語でも取り扱い方が大きく異なることがあります。
要点を整理すると、法定休日は労働時間計算から除外される日、法定内休日は就業規則に基づく扱いになることが多い、代休・賃金の割増は個別の規程に左右される、という3点が基本です。現場では、シフト作成時に法定休日を必ず反映させ、法定内休日の定義と扱いを就業規則で再確認することが重要です。
法定休日とは何か
法定休日とは、日本の労働基準法で定められている休みのことを指します。具体的には、週に少なくとも1回の休日を確保する義務があり、企業はこの条件を満たすための制度設計を行います。法定休日があるとき、出勤日であっても賃金計算の対象が変わることがあり、通常の出勤日と同じ扱いにはなりません。法定休日に働いた場合には、通常の賃金に加えて割増賃金を支払う義務が生じるケースが多いですが、契約や規程で別の取り決めがある場合にはその限りではありません。つまり、法定休日の適用範囲は、雇用形態や就業規則の内容によって異なることがあります。正社員だけでなく、アルバイト・パートにも適用されることがある一方で、短時間勤務者には適用範囲が限定されることもあります。管理者や人事部門は、出勤表・賃金台帳にこの取り扱いを正確に反映させる責任があります。法定休日は“国家が定めた休み”として、従業員の健康と生活の安定を支える重要な役割を果たします。
法定内休日とは何か
法定内休日は、法定休日に対する対になる概念で、企業が就業規則や社内規程で独自に追加して設定する休みを指します。法定内休日は必ずしも全員に適用されるわけではなく、雇用形態・職種・繁忙期などによって扱いが異なることがあります。就業規則で「法定内休日を休日日として扱う」「法定内休日を特定の条件で代休とする」などの規定がある場合、これに従って賃金計算や時間外労働の扱いを決めます。法定内休日に勤務した場合にも、代休を付与するかどうか、割増賃金の適用がどうなるかは企業のルール次第です。実務では、法定内休日を休みとして扱うか、出勤扱いとするかで、月の総労働時間や賃金が大きく変わることがあるため、現場の担当者は就業規則に書かれた条項を細かくチェックする必要があります。従業員にとっては、法定内休日の定義とその使い方を理解しておくことで、トラブルを避け、適正な休暇取得ができるようになります。
違いを分かりやすく整理するコツ
ここでは、法定休日と法定内休日の違いを見分けやすくするためのポイントを整理します。まず第一に、法定休日は法律で決まった休みであり、原則として賃金計算から休み日として扱われ、時間外手当の対応が発生する場合が多い点を押さえておきましょう。第二に、法定内休日は就業規則の中で定義される追加の休みで、代休や賃金の割増などの扱いは企業規程に依存します。第三に、両者の適用範囲は雇用形態や契約の内容によって異なるため、個別の就業規則を必ず確認することが重要です。最後に、現場では「休みの日付と賃金の計算がどうなるか」を事前にシフト表と給与計算ソフトで検算する癖をつけると、後からのトラブルが減ります。もし不明点があれば、労働基準監督署や人事部門に相談するのが安全です。
今日は友人と昼休みにこの話題を深掘りします。法定休日と法定内休日、どちらも“休み”の話ですが、意味や扱いが違います。法定休日は法律で決まった休みで、出勤扱いにならない日が基本です。一方、法定内休日は企業の規程で追加される休みで、代休の有無や賃金の取り扱いが就業規則に左右されます。つまり、同じ“休み”という言葉でも、現場のルールが違うのです。僕らがアルバイトをする時には、シフト表や賃金計算が複雑になりやすいので、事前に就業規則を読んでおくと安心です。話をするときには、友達にも「法定休日と法定内休日は別物だ」と伝え、具体例を挙げて理解を深めるとよいでしょう。これを知っていれば、学校の課題や部活の計画を立てるときにも役立ちます。さらに、日付が重なるときの賃金の扱いがどうなるかを想像してみると、生活設計にも役立ちます。





















