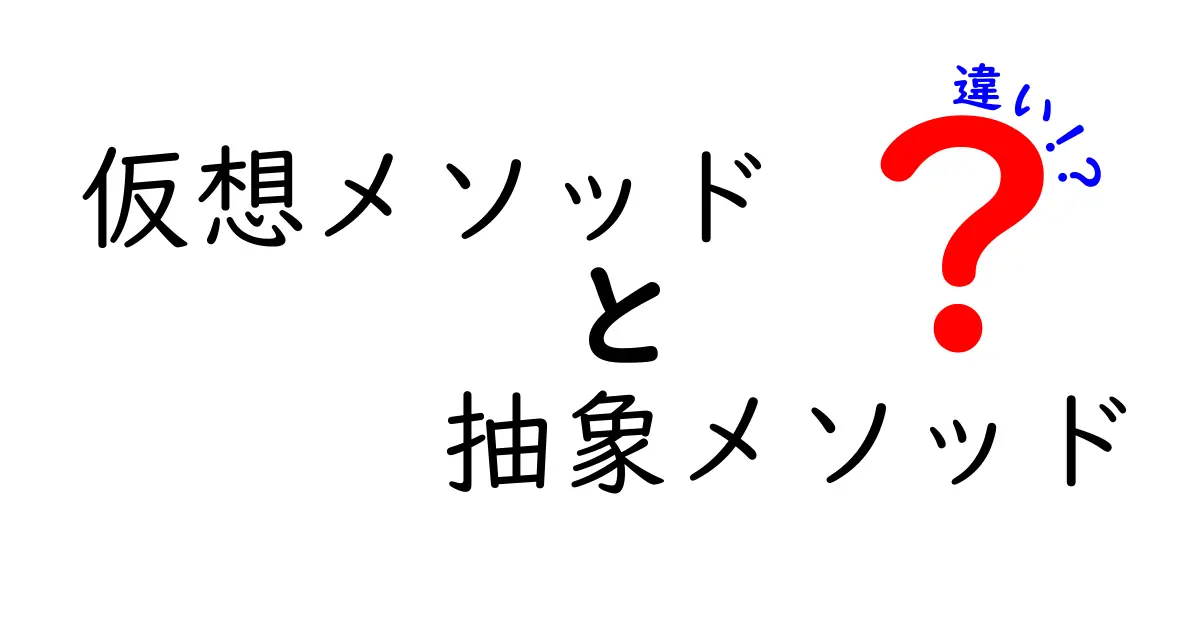

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
仮想メソッドと抽象メソッドの基本を押さえよう
ここでは 仮想メソッドと 抽象メソッド の基本を丁寧に説明します。仮想メソッドは親クラスで実装が用意されており、必要に応じて子クラスで上書きできる性質を持っています。これにより、同じ型のオブジェクトが異なる振る舞いをするように拡張できます。
抽象メソッドは親クラス自体に実装を置かず、派生クラスに具体的な動作を必ず実装させる契約のような役割を果たします。
この2つの仕組みはプログラムの拡張性と安全性を大きく左右します。特に大きなソフトウェアを作るときは、どちらを使うべきかの判断が設計の側で重要になります。ここからはポイントを順番に見ていきます。
なお 仮想メソッドと 抽象メソッド は言語によって呼び方が違うことがありますが、基本的な考え方は同じです。例えば C Sharp や C++ や Java の一部の機能と対応します。
違いのポイントを実用的に比較してみよう
このセクションでは実際のプログラミングでどう使い分けるのかを、具体的な観点で詳しく比較します。
まず 実装の義務の違いを理解すると、設計の方向性が見えやすくなります。仮想メソッドは親クラスの実装を基点として用意し、子クラスは任意でそれを上書きします。抽象メソッドは親クラスが実装を持たず、派生クラスが必ず新しい実装を提供しなければなりません。
次に デフォルト実装 の有無についてです。仮想メソッドには基本的な機能の実装があることが多いのに対し、抽象メソッドにはデフォルトの機能が存在せず、派生クラスでの実装が全てです。これが設計上の大きな分かれ道になります。
最後に 設計上の狙い について考えましょう。仮想メソッドを活用すれば共通処理を多くの派生クラスで共有でき、柔軟性が増します。一方で抽象メソッドを使えば派生クラスの動作を厳密に約束させ、後から新しい派生クラスを追加しても予期せぬ動作の崩れを防ぐ設計が可能です。
このように使い分けることでコードの再利用性と安全性を両立しやすくなります。実際の開発では言語の仕様とプロジェクトの方針に合わせて適切な選択をすることが大切です。
たとえばフレームワークの拡張ポイントを作る場合は抽象メソッドを使い、基底クラスで基本動作を提供しつつ拡張点だけを子クラスに任せるのが典型的です。
一方で複数の派生クラスで共通の実装を共有したいときは仮想メソッドを活用して、基本は親クラスの実装を利用しつつ必要な部分だけ派生クラスで変える、という設計が自然です。
今日は友達とプログラミングの話をしていて、仮想メソッドと抽象メソッドの違いについてこんな結論に落ち着きました。彼は最初、仮想は自由に変えられると思っていたけど、実はそれは選択肢の多さで、抽象は強制力の強い契約だと説明してくれました。僕らは例として学校の部活動の指示を思い浮かべました。指揮系統の中で部長が方針を出しており、部員はその範囲で動くという感じ、部長が具体的な手順をすでに用意していて、それを部員が自分のやり方で応用するのが仮想メソッド。対して抽象メソッドは部長が“これを作れ”と明確な設計を示し、部員が自分の解釈を加えず必ず実装する、という約束のようなものだと話しました。





















