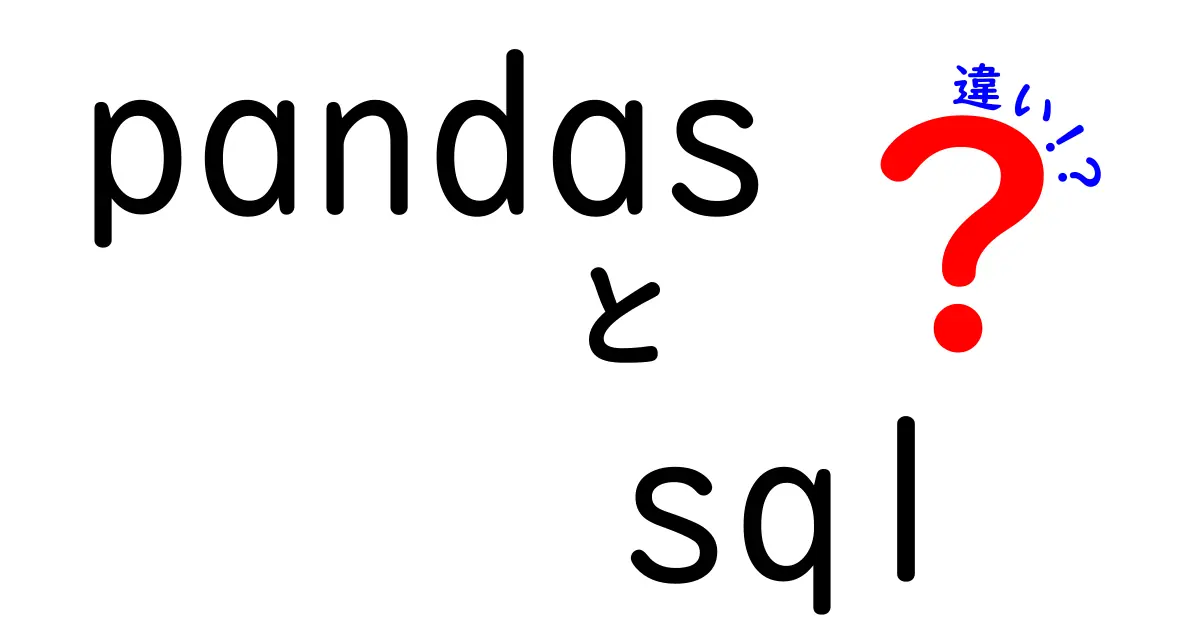

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:pandasとSQLは別物?同じところもある?
データを扱う道具にはいろいろありますが、代表的な二つが pandas と SQL です。
pandas はPythonの中で動くデータ分析用ライブラリで、表形式のデータを読み込み加工し、集計や可視化まで一連の作業を行えます。
SQL はデータベースと呼ばれる場所に対して命令を出し、テーブルの中身を取り出したり結合したりする言語です。
この二つは同じ「データを扱う」点は共通しますが、動く場所や得意分野が大きく異なります。
現場では、SQL でデータを絞り出し、それを pandas に渡して細かな加工をする、というハイブリッドな使い方が多く見られます。
つまり「どこで何をするか」を決める設計力がとても大事です。
この解説では、両者の特徴と使い分けの基本を中学生にも分かる言葉で丁寧に説明します。
最後まで読めば、データの世界がぐっと身近に感じられるでしょう。
pandasとは何か:データ分析のための道具
pandas は Python のデータ分析を支える強力な道具です。
主役となる DataFrame は行と列でデータを表す「表の箱」みたいなもの。ここに CSV や Excel などのデータを読み込み、欠損値の補完、列の追加、データの型の変換、集計、結合、フィルタリングなどを連続して行えます。
pandas の魅力は「コード一行でデータ処理を表現できる」点と、「柔軟性が高い」点です。
たとえば大量のデータをあらかじめ整形してから機械学習モデルに渡す際、pandas は前処理の要として活躍します。
ただしデータをメモリ上に置いて操作するため、データ量が大きいとメモリ不足になるリスクがあります。
その場合はデータベースに移すか、分割して処理することを検討します。
学ぶコツは、まず DataFrame の基本操作を覚え、次に欠損値処理や結合の高度な手法を段階的に身につけることです。
またデータ型を正しく選ぶこと、列単位の計算を心がけること、そしてパフォーマンスの観点を忘れないことが重要です。
これらを押さえると、データの洗練された処理がスムーズに進み、分析作業が楽しくなります。
SQLとは何か:データベースを操る言語
SQL はデータベースの中身を直接操作するための言語です。
代表的な命令は SELECT でデータを取り出すこと、FROM で対象のテーブルを指定すること、WHERE で条件を絞ること、JOIN で複数のテーブルを結びつけること、そして GROUP BY や HAVING、ORDER BY で集計と並べ替えを行います。
SQL の強みは「データをデータベースの中で処理する」点にあり、データ量が多くてもデータベースのインデックスや実行計画を活かして高速に動くことです。
一方で、SQL は分析や可視化、機械学習の前処理を直接完結させるものではありません。後続の処理は pandas や他のツールに任せるのが一般的です。
現場では、データの初期絞り込みを SQL で行い、必要なデータだけを取り出してから pandas に渡して追加の加工を進める、という流れがよく使われます。
この考え方を身につけると、データの流れが見えやすくなり、学習の効率も高まります。
両者の違いと使い分け:現場の実践ガイド
実務での使い分けの基本的な考え方をいくつか紹介します。
データ量の規模:大規模なデータはまずデータベース側で絞り込み、最小限のデータを pandas に渡すのが基本です。
処理の性質:データのクレンジングや結合などの「整形」は SQL と pandas のどちらで行うかを状況に応じて決めます。
遅延評価とパフォーマンス:SQL はデータベースの最適化機能を活用でき、pandas は Python の柔軟性を活かせます。
学習コスト:pandas は Python の基礎があると習得が早い一方、SQL は論理の組み立て方を覚えやすい場合が多いです。
以下の実践的なポイントも覚えておくと役立ちます。
・データの「取り出すベストな量」を常に意識する
・計算は列単位で行い、行ごとに繰り返さない
・可視化やモデリングを別のツールに任せるタイミングを見極める
この判断ができると、作業の無駄が減り、品質の高いデータ処理が実現します。
SQLの深い考え方は日常の整理術にも似ています。データの棚を整理するように、どの列を使い、どのテーブルを結合して、何を結果として出すのかを設計します。初めは簡単なSELECTから始め、慣れると複数のテーブルをつなぎ合わせるJOINや集計の考え方へとステップアップします。こうした設計力がつくと、データの断片が雑然と積み上がるのではなく、意味のある形で並ぶようになり、データサイエンスの現場で役立つ“思考の筋肉”が育ちます。





















