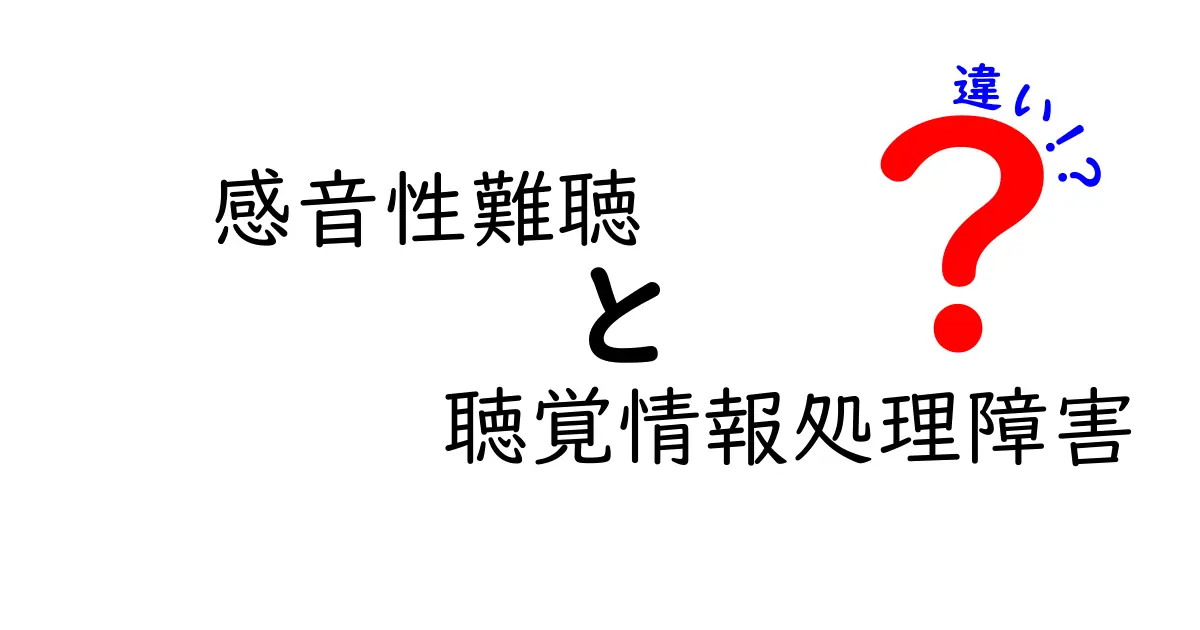

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
感音性難聴と聴覚情報処理障害の基本的な違い
この二つはともに“難聴”の言葉を使いますが、根本的な原因と日常の感じ方は大きく異なります。まず感音性難聴は耳の内部、特に内耳の蝸牛や聴神経といった音の受け取り口の機能障害が原因で、音の閾値が上がり音が小さくても聞こえにくくなる状態です。これにより、音が出ているのに気づかない、または言葉を聞き取るのが難しいと感じることが多く、検査では純音聴力などの閾値が高く出ることが多いです。
対して聴覚情報処理障害は脳の中で音の情報を整理・解釈する処理の流れに問題がある状態です。耳自体は音を受け取れていることも多いのですが、聴こえた音を意味のある情報に変換する段階でつまずくため、特に雑音の中で言葉を聞き分けるのが難しく、指示を理解するのに時間がかかることがあります。
この違いは治療法の選び方にも大きく影響します。耳の機能を補う補聴器や医療的な介入が有効な感音性難聴に対し、聴覚情報処理障害には音声訓練や環境調整、学習支援など脳の処理能力を高める取り組みが中心になります。以上の点を知っておくと、困っている場面を具体的な対策に結びつけやすくなります。
また両者が同時に起きているケースもあり、その場合は“聴こえ方”と“情報処理の仕方”を別々に評価して組み合わせる支援が重要です。
実際の生活では、家族や先生が話す時の背景音、教室の雑音、スマホの通知音など、さまざまな音が絡み合います。こうした環境の中で、耳の機能の有無だけでなく、情報をどう処理するかという視点を持つことが重要です。
総じて言えるのは、感音性難聴は音を受け取る能力の不足、聴覚情報処理障害は音を理解・整理する力の不足という“違う種類の難しさ”を指すという点です。正確な理解と適切な支援を受けるためには、医療機関や学校と連携して適切な検査を受けることが大切です。
ここまでのポイントを整理すると、まずは自分の聴こえ方の特徴を観察し、音が聞こえづらい場所や話の理解に時間がかかる場面をメモしておくと診断の際に役立ちます。次に、音声訓練や学習支援、環境改善といった具体的な対策を組み合わせることで、日常生活のストレスを減らすことができます。大切なのは“自分の強みを活かす方法を探すこと”と、専門家と家族の協力体制を作ることです。
本記事の結論としては、聞こえ方と処理の仕方は別の課題であり、それぞれに合った対策を組み合わせることで、学ぶ・遊ぶ・話すといった日常活動をより楽にしていけるという点です。
よく混同されがちなサインと検査の違い
次のポイントを知ると、どの状態か判断する手がかりになります。まず、感音性難聴が疑われる場面は、音の大きさを上げても言葉がかすかにしか聞こえない、家族が小さな音を拾いづらいと感じるといった現れ方が多いです。聴力検査では閾値の上昇、つまり音を聞くために必要な最小の音量が高くなる結果が出ます。これに対して聴覚情報処理障害は、耳は正常な音を聞けても、言葉の意味理解、特に雑音の中での聞き分けが難しい、話の順序を追うのに時間がかかるといったサインが現れます。検査としては、聴力検査とともに聴覚処理能力を測る検査(例えばディコティック聴取テスト、聴覚処理検査など)を組み合わせて評価します。
表を見てもらうと、それぞれの特徴がより分かりやすくなります。
この二つは混同されやすいですが、原因の場所と日常の感じ方が違うため、治療・支援の方向性も異なります。
学校現場では、音がうるいと感じる教室での課題中の聴き取り、授業中の指示の理解、友人との会話の取りこぼしなどが、聴覚情報処理障害の特徴として現れやすいです。反対に、家族との会話で小さな音しか聞こえない、電話での言葉が聞き取りづらいといった状況が多い場合は感音性難聴の可能性を考えます。
正確な診断の鍵は、聴覚機能と処理機能の両方を評価する専門家の総合的な判断です。
| 観点 | 感音性難聴 | 聴覚情報処理障害 |
|---|---|---|
| 原因 | 内耳や聴神経の障害 | 脳の処理機能の問題 |
| 聴こえ方の特徴 | 音が小さくても難聴が出ることが多い | 音は聞こえるが理解が難しい場面が多い |
| 検査のポイント | 純音聴力など聴力閾値の上昇 | 聴覚処理検査の結果が重要 |
| 日常生活の影響 | 音の質が低下する感覚 | 会話理解、指示理解の困難 |
| 対応・治療 | 補聴器、医療的介入が中心 | 音声訓練、環境調整、学習支援が中心 |
診断と治療のポイント
診断は複数の専門家が協力して行います。まず耳鼻咽喉科で感音性難聴の可能性を評価し、必要に応じて聴覚処理の検査を依頼します。治療・支援の基本は早期発見と適切な環境づくりです。
家庭では家庭内聴覚環境の改善、例えばテレビの音量を適切に保つ、話すときは相手の目を見て話す、静かな場所で話しかける、などが効果的です。学校では教室の音環境改善、座席の配置、指示の簡略化、ノートの読み上げ支援、必要に応じた追加の説明時間などを取り入れます。
最後に、家族や教師・医療者が連携して支援計画を作ることが最も大切です。正しい情報と適切な支援があれば、難しさを大きく減らし、学びや日常生活をより楽にしていくことができます。
この記事で紹介したポイントを実践して、焦らず一歩ずつ取り組んでください。
koneta: "友だちAと僕の会話" A: 最近、音が小さくても話が聞き取りづらい場面が増えたんだ。 B: それって聴覚情報処理障害の可能性かも。耳は音を拾えてても、耳から入った情報を頭で整理する力がうまく働かないことがあるんだよ。 A: へえ、耳の問題だけじゃなく、脳の処理の仕方にも原因があるんだね。 B: そう。だから対策は二つで、耳の音の聞こえを改善する治療と、話の意味を正しく捉える訓練を両方組み合わせるのが大事。 A: 教室の騒音が多いと聞き分けが難しくなるのも、このせいか。 B: うん。だから座席の工夫や、指示を短く分けて伝えると効果が出やすいんだ。 A: 家族も学校も協力してくれると、僕の listening skill はぐんと伸びるはずだね。"





















