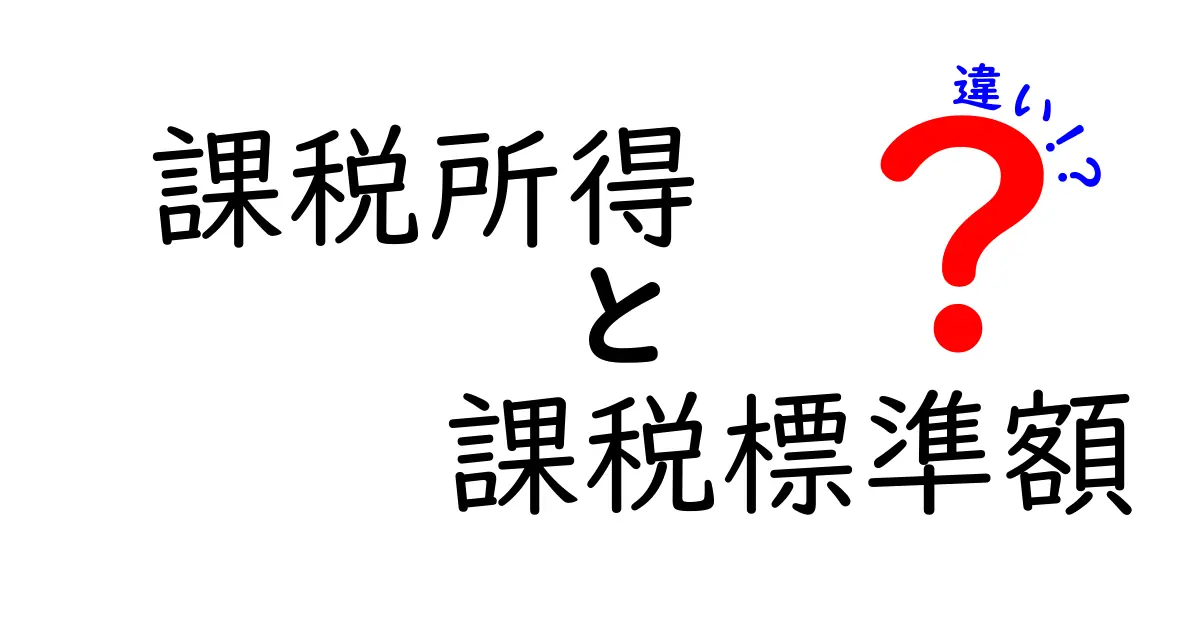

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
課税所得と課税標準額の違いとは?
税金の話をするとよく聞く「課税所得」と「課税標準額」という言葉ですが、実はこの2つは似ているようで意味が違います。
課税所得とは、所得から必要な控除を差し引いた後の金額のことを言います。つまり、税金を計算するためにまず所得からいろいろな控除をして残った本当の課税対象となる所得です。
一方で課税標準額は、課税の対象となる基準となる金額のことを指します。住宅税や固定資産税などでは課税標準額という言葉が使われることが多いのですが、所得税の場合は課税所得とほぼ同じ意味として使われることが多いです。
このように「課税所得」は特に所得税などの計算で使い、「課税標準額」は税金の基準となる金額全般を指す場合が多い、と覚えるとわかりやすいです。
課税所得ができるまでの流れ
まず、収入があってそこから色々な費用や控除を引いていきます。
例えば給与所得の場合、年間の給与から社会保険料控除や基礎控除などを引きます。
計算は大まかに以下のようになります。
- 総収入(給料など)
- - 必要経費や所得控除(社会保険料控除、配偶者控除など)
- = 課税所得
この課税所得が決定すると、この金額を基に税率をかけて所得税額が決まります。
課税標準額の使われ方とその特徴
課税標準額は所得税以外の税金にもよく使われる言葉です。
例えば固定資産税では「課税標準額」が「課税対象となる不動産の価値」を示します。その課税標準額を基に税率を掛けて税額が決まります。
表にまとめると以下のようになります。
| 税の種類 | 課税所得 | 課税標準額 |
|---|---|---|
| 所得税 | 所得から控除を引いた金額 | ほぼ同義(文脈による) |
| 固定資産税 | 使われない | 不動産評価額からの課税対象額 |
| 事業税など | 事業所得などから計算した所得 | 課税の基準額として使用 |
つまり課税標準額は「税金計算のもとになる基準金額」と考えると理解しやすいです。
まとめ:それぞれの言葉のポイント
ここまで説明した大切なポイントは下記です。
- 課税所得は特に所得税の計算で使い、所得から控除を差し引いた後の額を指す。
- 課税標準額はより広い意味で使われ、様々な税目の課税の基準となる金額を指す。
- 所得税の場合は課税所得と課税標準額がほぼ同じ意味で使われることもある。
- 固定資産税などでは課税標準額が不動産の評価額から決まる。
- 税金計算で重要なのはこれらの「課税」のもとになる基準額をきちんと理解すること。
税金は難しく感じますが、「課税所得は所得から控除を引いた後の金額」「課税標準額は税金の計算基準となる金額」と覚えるだけでずいぶん理解しやすくなります。
ぜひ覚えて役立ててください!
「課税標準額」という言葉は、実は固定資産税などの不動産税でよく耳にします。ここでは、不動産の評価額を元に課税されるのですが、評価額には市場価格とはちょっと違うルールがあって面白いんですよ。たとえば、周囲の土地や建物の状況から評価額が決まるので、必ずしも売値と一致しないことがあるんです。だから、「課税標準額」を知ることは、税金だけでなく不動産の価値の考え方の勉強にもつながります。意外と身近な話題ですね!
次の記事: 申告納税と確定申告の違いとは?初心者でもわかる税金の基本解説 »





















