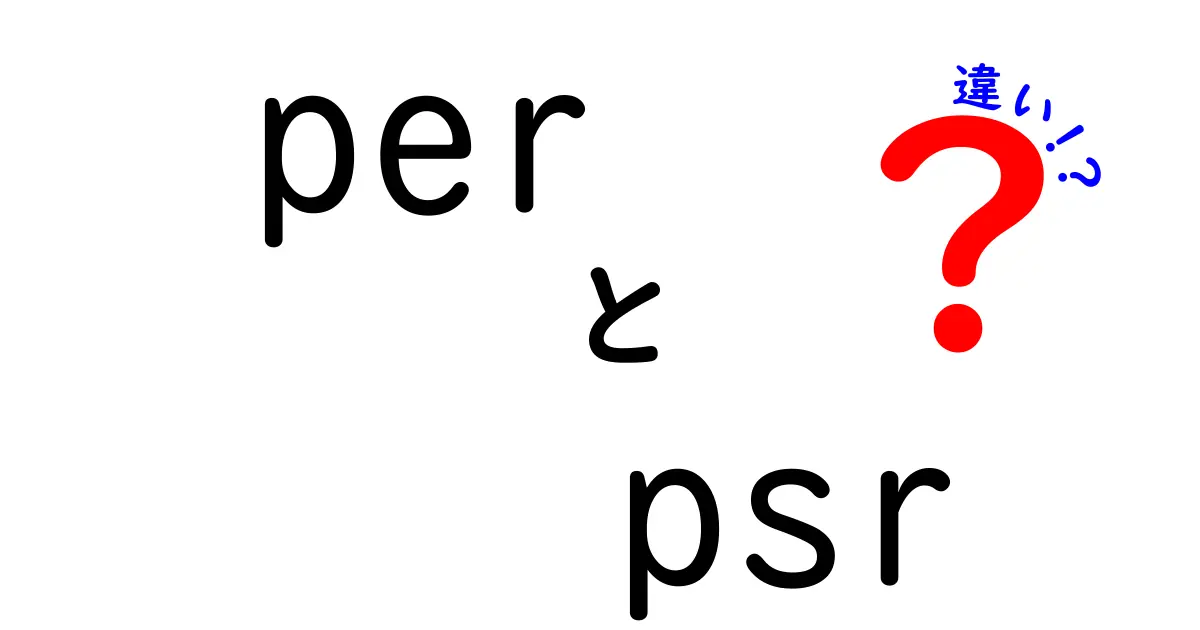

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
PERとPSRの違いを徹底解説
株式投資の世界では、企業の値動きを判断するための指標がいくつも存在します。その中でも「PER(株価収益率)」と「PSR(株価売上高倍率)」は、初心者にもよく使われる基本指標です。この2つは目的が異なり、計算方法も違います。PERは企業の稼ぐ力に対して株価がどう評価されているかを示すのに対し、PSRは売上高に対して株価がどれくらい高いかを示します。つまり、同じ株価の水準でも、利益が大きい会社と小さい会社では示す意味合いが変わるのです。
以下では、 PERとPSRの基本、それぞれの計算式、解釈のしかた、実務での使い分け、そして注意点を順番に解説します。まずは両指標の根本的な違いを整理しましょう。PERとPSRはどちらも株価の「水準」を見ている指標ですが、背景にあるデータの性質が異なります。その点を理解するだけで、銘柄選びの際の目線が大きく変わります。
また、実務では企業の財務体質や業界特性を踏まえて複数の指標を組み合わせて判断することが重要です。単一の数字だけで売買を決めてはいけないという原則を忘れずに活用してください。
PERとは何か?計算式と解釈
PER(Price Earnings Ratio)は「株価 ÷ 1株当たりの利益(EPS)」で計算されます。日本語では「株価収益率」と呼ばれ、株価が企業の利益を何倍で評価しているかを示します。数字が大きいほど「株価が利益に対して割高だ」と考えられやすく、反対に小さいと「割安」と見なされがちですが、業種や成長性、利益の安定性によって適正水準は異なります。
例えば、安定した高配当企業はPERが低く見える場合もありますが、成長企業は一時的にPERが高いことも珍しくありません。
計算上のポイントとして、EPSの変動がPERに大きな影響を与えます。EPSが伸びるとPERは低下し、株価が同じでも投資家の評価が変わることがあります。
また、PERは業界間の比較に使いやすい一方で、利益が一時的な要因で大きく上下する場合には誤解を生む可能性がある点にも注意が必要です。例えば、新規事業の赤字が一時的に発生している企業はPERが低く見え、株価が割安と判断されがちですが、長期的な視点では改善が難しいケースもあり得ます。
このような背景を踏まえると、PERだけでなくEPSの安定性、利益の質、キャッシュフロー、財務健全性など他の要因と一緒に見ることが重要です。
PSRとは何か?計算式と解釈
PSR(Price to Sales Ratio)は「株価 ÷ 1株当たりの売上高」を用いて計算されます。日本語では「株価売上倍率」と呼ばれ、企業が売上に対して市場からどのくらいの評価を受けているかを示します。PSRは利益が赤字である新興企業でも使える指標であり、利益の有無に左右されにくいという利点があります。
特に急成長中の企業や、利益が一時的にマイナスの段階にある企業を評価する際には、PSRがPERよりも現実的な手がかりを提供することがあります。
PSRの低さは必ずしも「割安」を意味するわけではなく、売上高の質やマージンの推移、将来の収益性の見通しといった要因も考慮する必要があります。
PSRを実務で使う時は、売上の成長性と粗利率の動向、そして業界平均との比較を重視します。例えば、同じPSRでも売上が急伸している企業は株価が高く評価されやすい一方、利益率が低かったりキャッシュフローが悪化していれば注意が必要です。
PSRの活用には注意点もあり、PSRは売上の水準に依存するため、売上が小さな企業では数値が過大評価されがちです。したがって、PSRだけで投資判断を下すのは避け、他指標と合わせて総合的に判断することが重要です。
実務での使い分けと注意点
実務でPERとPSRを使い分ける際には、まず投資対象の「成長段階」と「収益性の安定性」を考慮します。成長企業にはPSRが適している場合が多く、成熟企業にはPERが重要な指標となることが多いです。このため、業種別の適正水準や市場環境を踏まえた比較が必要です。
また、両指標は単独で判断するべきではなく、キャッシュフロー、ROE、財務健全性、負債比率、そして市場環境や金利動向などと組み合わせて検討します。具体的には、PERが高くてもEPSが安定して伸びていれば株価は正当に評価されている可能性がありますし、PSRが低くても売上成長が鈍化していれば割安とは限りません。
以下のコツも覚えておくと良いでしょう。
- PERの強み: 収益力と利益率の関係を理解するのに適しており、成熟企業の比較に向く。
- PSRの強み: 利益が安定していない成長企業の評価に強く、赤字企業でも比較が可能。
- 両指標の組み合わせ: キャッシュフロー、ROE、財務健全性 等をセットで見ると、誤解が減る。
最後に、投資判断は複数の指標を横断的に見ることが基本であると理解してください。PERとPSRは補助的な道具であり、適切に使うほど銘柄選びの成功率が高まります。日々のニュースや決算発表、ガイダンスの更新にも敏感に反応するので、継続的な情報収集が不可欠です。
今日はPSRについての雑談をちょっとします。PERとPSR、どちらが大事かは銘柄の成長段階で変わるよね。新興ベンチャーは利益が出ないことが多いからPERは低く出やすい。でもPSRは売上が増えるほど株価の未来像が反映されやすい。だから成長期にはPSRの方が現実的な評価につながる場面が多い。日常の会話のように、例え話で整理してみると、PSRは“売上の地図”のように感じられる。株価がこの地図のどの場所に位置しているかで、投資家がどんな将来を期待しているのかが見えやすい。つまり、売上が大きく伸びるとPSRは意味を持ち、利益の大きさだけでは測りきれない世界になる。こんな感じで、PERとPSRの違いを会話形式で考えると、学習が楽になります。





















