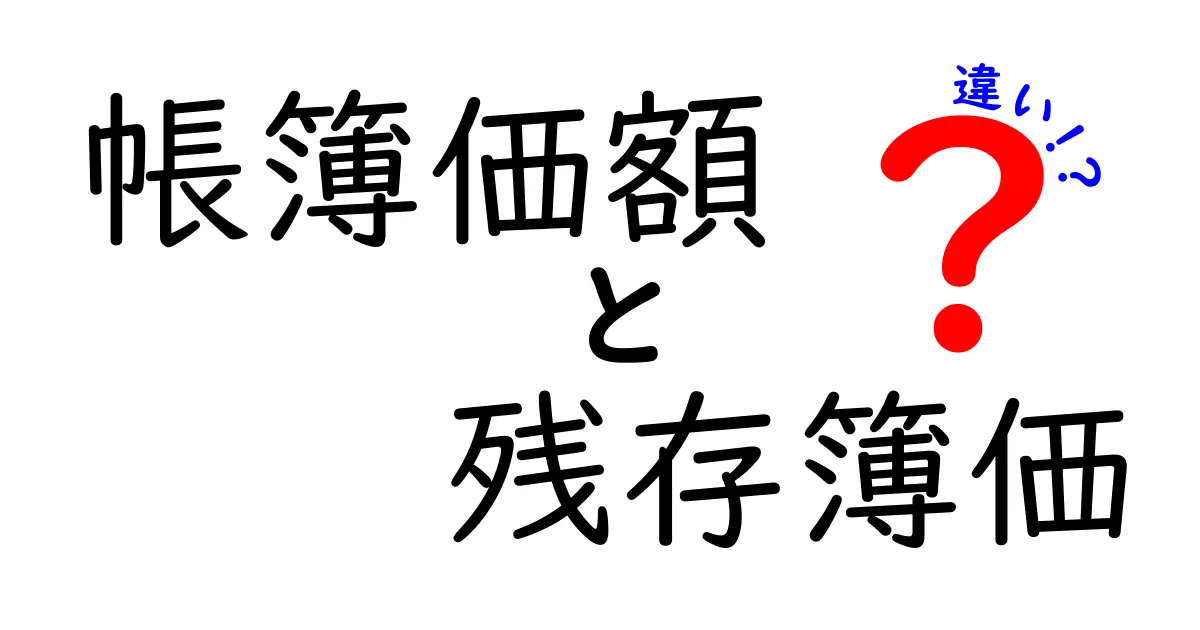

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
帳簿価額とは何か?基本を押さえよう
<帳簿価額(ちょうぼかがく)とは、企業が資産を購入した際の取得原価から、減価償却などの調整を行った後の価値のことを指します。簡単に言えば、会計帳簿に記録されている物の値段のことです。
例えば会社が機械を100万円で買ったとします。その機械が使われるうちに価値は徐々に減っていきますが、その減った分を差し引いた残りの金額が帳簿価額となります。この帳簿価額は毎年の決算時に見直され、減価償却を計算して更新されます。
つまり帳簿価額は、資産の取得価格に減価償却を加味した現在の価値を表しているのです。日々の経理作業や決算報告でよく登場する重要な概念ですね。
残存簿価とは?帳簿価額との違いを比較
<残存簿価(ざんぞんぼか)も帳簿価額と似た言葉ですが、厳密には少し違います。残存簿価とは資産の使用可能期間が終了した時点での帳簿価額のことを指します。つまり減価償却を終えた後の最終的な価値、または廃棄や売却時の見積もられた価値のことです。
例えば先ほどの機械が使い切られ寿命が来たとしましょう。残存簿価はその時点で残っている価値、あるいはスクラップとしての価値などになるわけです。
よく似ていますが、帳簿価額は「現在の価値」のこと、残存簿価は「使い終わった時の最終的な価値」という違いがポイントです。
表で理解!帳簿価額と残存簿価の特徴比較
<| 項目 | <帳簿価額 | <残存簿価 | <
|---|---|---|
| 意味 | <取得原価から減価償却を差し引いた現在の資産価値 | <使用期間終了時点で残っている資産の価値(最終価値) | <
| 使うタイミング | <毎年の決算や資産管理の際 | <資産の耐用年数終了時や売却・廃棄時 | <
| 計算対象 | <資産の簿価=取得原価−累計減価償却額 | <資産の残余価値・スクラップ価値 | <
| 会計上の役割 | <資産の現在の価値を示す | <資産の最終的な価値判断に使う | <





















