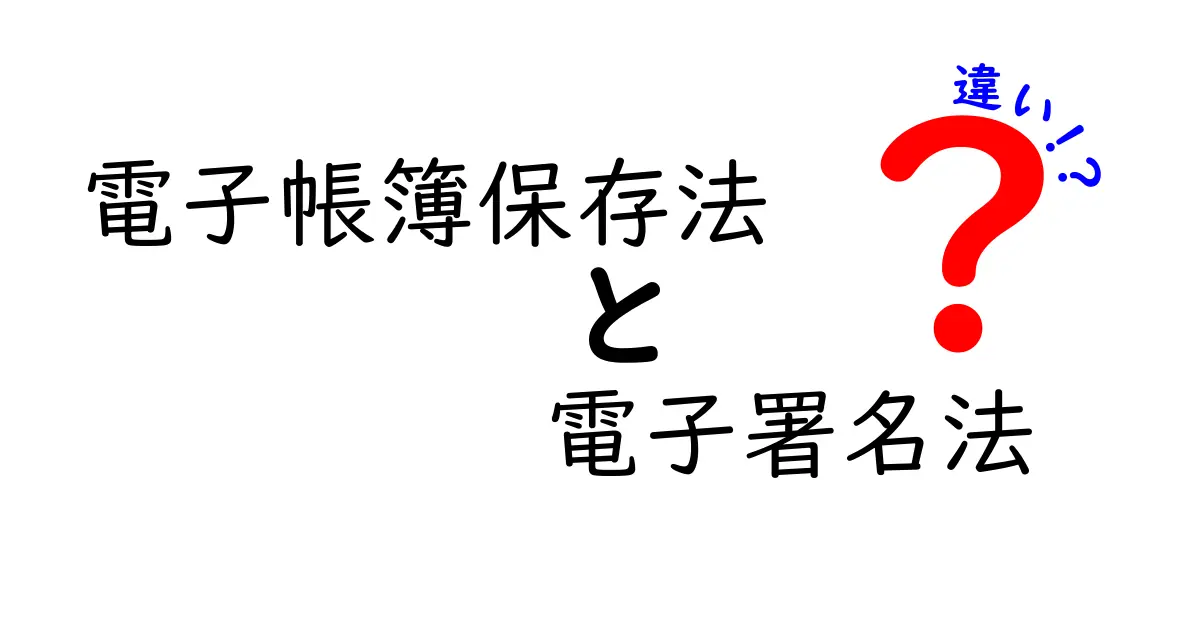

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
電子帳簿保存法と電子署名法って何?まずは基本を押さえよう
日本のビジネスや行政で使われる法律の中には、デジタルに関する規則がたくさんあります。その中でも特によく名前を聞くのが、電子帳簿保存法と電子署名法です。どちらも「電子」という言葉が入っているので似ているように感じますが、実は全く違う法律です。
電子帳簿保存法は、会社が作る帳簿や書類を電子データとして保存してもよいというルールを定めています。目的は紙の書類を減らして、効率よくデータを保管しやすくすることです。
一方、電子署名法は電子データが本物かどうかを証明する仕組みについて決めています。つまり、書面に押印する印鑑の電子版のようなもので、電子データの安全性や信頼性を守る法律です。
このように、電子帳簿保存法は「どのように電子書類を保存するか」がテーマで、電子署名法は「その電子書類に信頼できる証明をつけるか」がテーマになります。
電子帳簿保存法と電子署名法の違いを表にまとめてみよう
両方の法律の違いをもっとはっきりさせるため、下の表で比較をしてみます。
| ポイント | 電子帳簿保存法 | 電子署名法 |
|---|---|---|
| 目的 | 帳簿や書類の電子保存を認めるルール | 電子文書の本人確認や改ざん防止の仕組み |
| 対象 | 法人や個人事業者が作成する帳簿、書類 | 電子署名を使って証明するすべての電子文書 |
| 重要ポイント | 電子データを国税庁が認める基準で保存すること | 電子署名の技術や基準を定め、法的な証明力をもつ |
| 運用例 | 受領した請求書や領収書を電子で保存可能 | 電子契約書に署名をつける場面など |
このように、保存のルールを定めるのが電子帳簿保存法、署名のルールを定めるのが電子署名法と理解するとポイントがつかみやすいですね。
どんな場面でそれぞれの法律は使われるの?実例で見てみよう
会社の経理担当者の場合、電子帳簿保存法のおかげで紙の請求書をスキャナーで読み取り、デジタルデータとして一定のルールで保存すれば国税調査でも問題ありません。これにより書類の保管スペースが減り、検索も簡単になります。
一方で、電子署名法は、インターネット上での契約書のやり取りを行う際に使われます。たとえば、二つの会社間で「電子契約」をするときに、署名を電子的に付与し、その契約が本当に相手からのものであり、あとから変更されていないことを証明するのです。
電子署名がなければ、誰でも契約書を勝手に書き換えられてしまいます。そのため、企業間の信頼を守る重要な仕組みとして役立っています。
電子署名法で使われる「電子署名」は、単なるパスワードやスタンプのようなものではありません。実は暗号化技術を使っていて、世界中の銀行や政府でも利用されています。例えば、誰かがメールの内容を書き換えると電子署名の検証が失敗し、データの改ざんがすぐにわかる仕組みがあるんです。だから電子署名は、ネット上の安全を守るためのスゴイ技術なんですよ。中学生でもイメージしやすいのは、「秘密のカギを使った合い言葉」のようなものと考えるとわかりやすいでしょう。
次の記事: 会計年度と決算期の違いとは?初心者にもわかりやすく解説! »





















