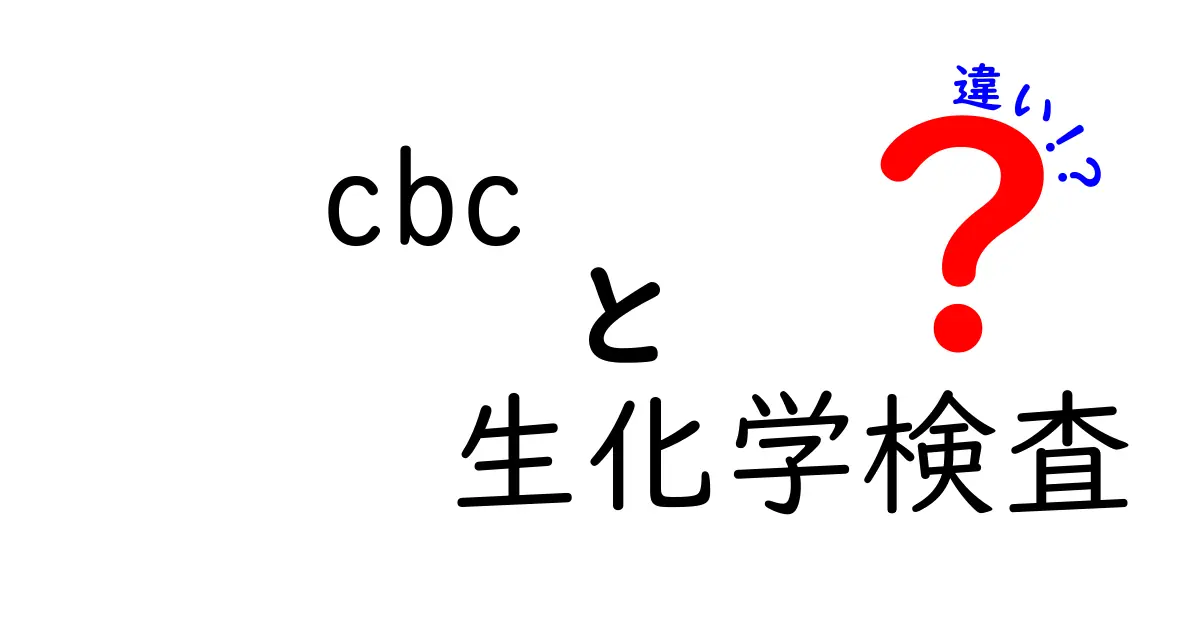

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
CBCと生化学検査の基本的な違いについて
医療現場でよく行われる検査の中に、CBC(Complete Blood Count)と生化学検査があります。この二つはどちらも血液を使った検査ですが、その目的や測る項目が大きく異なります。
CBCは主に血液中の血球成分、つまり赤血球・白血球・血小板の数や形を調べる検査です。一方、生化学検査は血液に含まれる様々な化学物質や酵素の量を測ることで、体の臓器の働きや栄養状態、代謝の状態を確認します。
このように、CBCは血液の細胞レベルの状態を、生化学検査は血液中の化学物質・酵素の状態を調べる検査である点が大きな違いです。
CBCの特徴と具体的にわかること
CBCは血液中の成分を詳しく調べることで、様々な病気の早期発見や経過観察に役立ちます。
具体的に測定する項目には、赤血球数、白血球数、血色素量(ヘモグロビン)、ヘマトクリット値(血液の中に占める赤血球の割合)、血小板数などがあります。
これにより、貧血や感染症、炎症、血液の病気などを見つけたり、状態をチェックしたりすることができるため、身体の基本的な状態を知る検査として広く使われています。
また、血液中の白血球の種類ごとの割合(白血球分画)を調べることで、免疫の状態や特定の感染症の種類も推測できます。
生化学検査の特徴とわかること
生化学検査は、血液の液体成分である血漿や血清を使い、体内の各種臓器の働きを調べるための検査です。
血液中の酵素の量や電解質、脂質、糖質、タンパク質など多くの成分を測ることで、肝臓や腎臓、心臓、膵臓の状態や代謝の異常を調べることができます。
例えば、肝機能を見るためにはASTやALT、アルカリフォスファターゼの数値を測り、腎機能はクレアチニンや尿酸でチェックします。
生化学検査は、多くの疾患や健康状態の指標となる数値を包括的に調べられるため、健康診断や病気の診断・治療方針の決定に非常に重要です。
CBCと生化学検査の違いのまとめ表
| 検査名 | 検査対象 | 主な測定項目 | わかること・用途 |
|---|---|---|---|
| CBC | 血液中の血球成分 | 赤血球数、白血球数、血小板数など | 貧血、感染症、炎症、血液の異常の確認 |
| 生化学検査 | 血液中の化学物質・酵素 | AST、ALT、クレアチニン、コレステロールなど | 肝臓、腎臓、心臓の機能や代謝の異常の検出 |
どんな時にどちらの検査が行われるか?
CBCは、風邪や感染症の疑いがある時、だるさや貧血の症状がある時など体の基本的な状態を調べたい時によく行われます。病院の初診時や健康診断の一部として実施される場合も多いです。
生化学検査は、健康診断で内臓の状態を詳しく調べるときや、肝臓や腎臓に関する症状が疑われるとき、慢性疾患の経過観察として行われます。複数の数値から総合的に身体の状態を評価できるため、病気が疑われた際にCTやMRIなどの画像検査と組み合わせて使われることもあります。
まとめ
CBCは血液中の細胞成分を調べる検査で、身体の基本的な状態や血液の病気をチェックするのに適しています。
生化学検査は血液中の化学物質や酵素を測定し、臓器の機能や代謝状態を知るための検査です。
どちらの検査も血液検査として大切ですが、それぞれ得られる情報が異なるため、症状や検査の目的に応じて適切に使い分けられています。
CBC(Complete Blood Count)は血液中の細胞を調べる検査ですが、実はこの中の白血球には多くの種類があります。例えば、好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球などがあり、それぞれ役割が違います。白血球の種類ごとの割合や数が変わることで、感染症の種類や体の炎症の状態を細かく判断できるのです。医師はこの情報をもとに、より的確な診断や治療方針を決めるので、CBCの中の白血球分画はとても重要な指標の一つなんですよ。





















