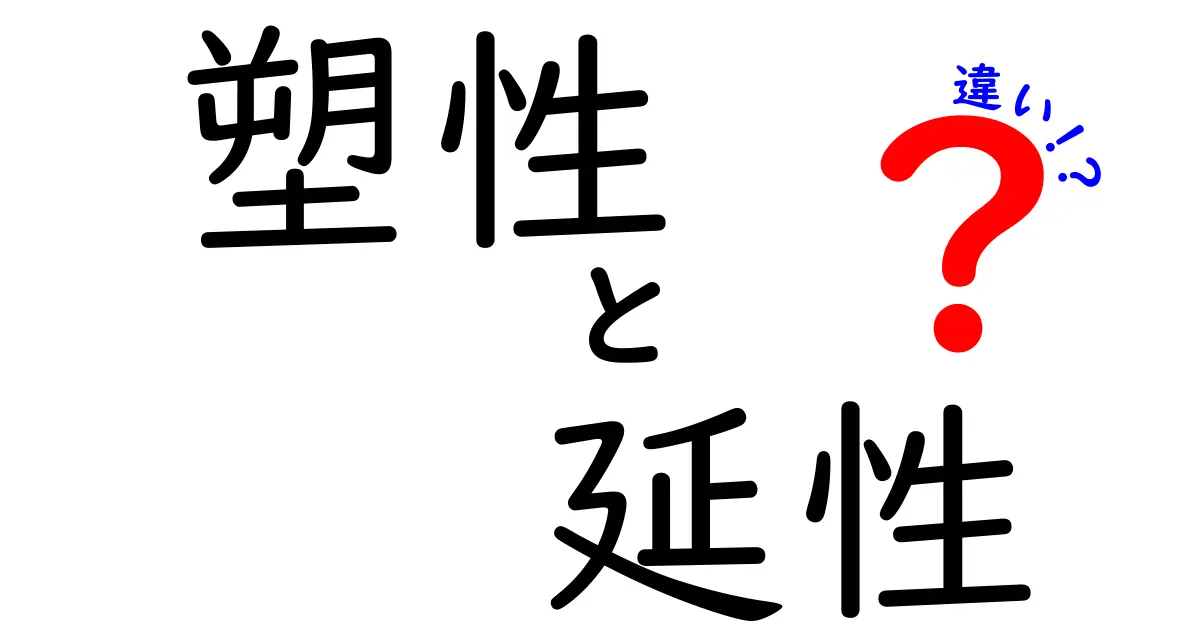

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
塑性とは何か?材料の変形性質を理解しよう
まず、塑性(そせい)とは、材料が力を受けたときに元の形に戻らず、新しい形に変わる性質のことを指します。例えば、粘土や金属を曲げたり伸ばしたりしたときに、その形が変わって元に戻らないことをイメージしてください。これは材料が永久変形したということです。
塑性は材料がどれだけ変形できるかだけでなく、その変形が一旦起こると戻らなくなることを意味します。つまり、力によって材料の内部構造が変化して、形が変わったまま固定されやすくなるのです。
この性質は、材料の加工や成形にとても重要で、金属加工(鍛造や圧延)、プラスチック成形などで活用されます。もし塑性がなければ、材料は力を加えられた瞬間に割れたり壊れたりしてしまいます。
延性とは?材料の引っ張りに強い性質を知ろう
一方、延性(えんせい)は、材料が引っ張られたときに細く伸びる性質のことを指します。簡単に言うと、材料がぐにゃぐにゃ伸びる能力とも言えます。
例えば、金の指輪をイメージしてください。金は非常に延性が高く、細く長く伸ばしても割れにくいのが特徴です。これに対して、ガラスは延性が低く、少し伸ばすだけで簡単に割れてしまいます。
延性が高い材料は、力を加えられてもバリバリと割れることなく、変形しながら力を吸収できるのが強みです。よく「粘り強い」という表現もここからきています。
塑性と延性の違いとは?分かりやすい比較表で理解しよう
ここまで説明したように、塑性も延性も材料の変形に関する性質ですが、少し違います。
両者の違いを以下の表にまとめてみました。
| 項目 | 塑性 | 延性 |
|---|---|---|
| 意味 | 永久変形しやすい性質 | 引っ張られて細く伸びる性質 |
| 特徴 | 力を加えると形が変わり、元に戻らない | 割れずに引き伸ばせる能力 |
| 例 | 粘土や柔らかい金属の変形 | 金・銀などの伸びやすい金属 |
| 重要ポイント | 形を変えられるかどうか | どれだけ細く伸びられるか |
材料の性質を正しく理解するには、どちらも大切な指標となります。
まとめ:生活や工業で役立つ塑性と延性の知識
塑性と延性は、一見似ているようで少し違う材料の性質です。塑性は変形しても戻らない性質、延性は引っ張って細く伸びる性質を意味します。
この違いを知ることで、日常生活での材料選びや、工業や建設の仕事の場面で材料の扱い方や安全性を正しく考えることができます。
例えば、橋や建物に使う鉄骨は高延性でないと、急な力でバキッと折れてしまう危険があります。一方、塑性が高い材料ならば加工がしやすく、様々な形に変えられるため便利です。
ぜひ、これらの性質を意識しながら、周りの材料や製品を観察してみてください。そうすると科学の面白さや工業技術の奥深さがより身近に感じられるはずです。
延性っていう言葉、実は金属をただ伸ばす能力だけじゃないんだよね。例えば、金はとっても延性が高いけど、それがあるから簡単に細く伸ばせてアクセサリーになる。だけど、延性が高くても別の力で曲げすぎると折れちゃうこともあるんだ。だから実は、延性と塑性は協力して材料の『粘り強さ』を作り出しているんだよ。材料の性質を理解すると、『なぜこの金具は折れにくいの?』っていう疑問も解決できるかもね。延性って意外と奥が深い!
前の記事: « ヤング率と引張強さの違いとは?中学生にもわかるやさしい解説





















