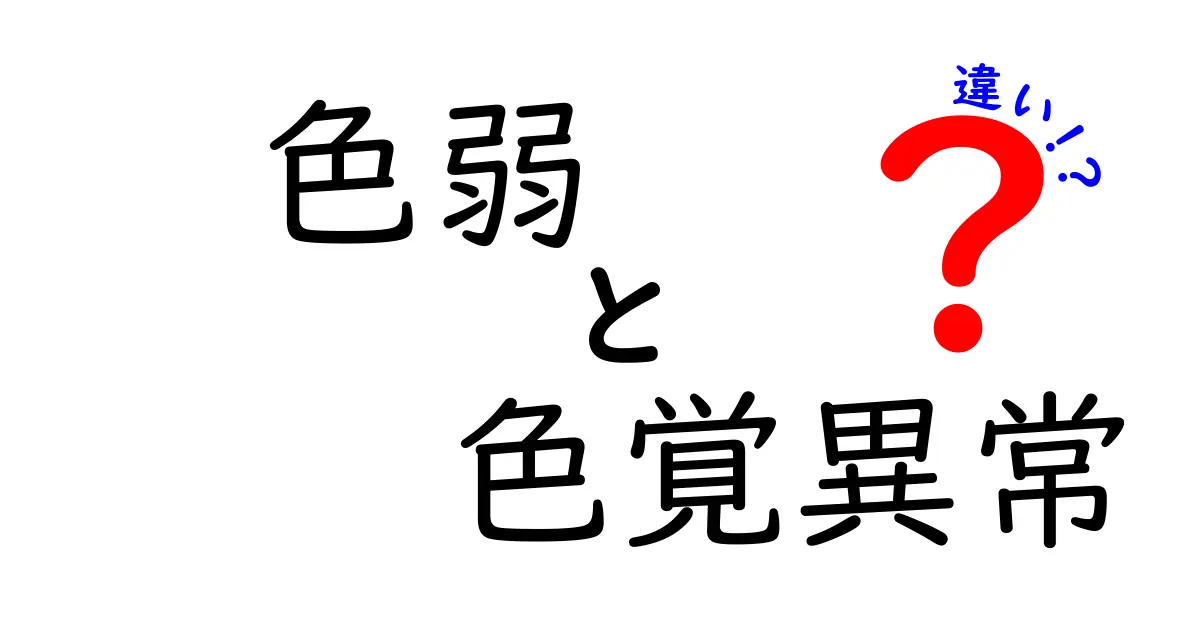

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
色弱と色覚異常の基本的な違い
色に関する問題を感じたとき、よく「色弱」と「色覚異常」という言葉が使われますが、実際にはどのような違いがあるのでしょうか?
色弱とは、色の識別が正常の人に比べて弱い状態を指し、日常生活に大きな支障がない場合も多いです。一方で色覚異常は、色の感じ方自体に異常がある広い概念で、色弱もその中に含まれます。つまり、色弱は色覚異常の一種なのです。
この違いを理解することは、正しい知識を持つうえでとても大切です。次の見出しでさらに詳しく解説します。
色弱と色覚異常の種類と特徴
色覚異常にはさまざまな種類がありますが、大きく分けると先天性(生まれつきの)色覚異常と後天性(病気やケガで起こる)色覚異常の2つです。
色弱は先天性の色覚異常の代表であり、多くは赤と緑の識別が困難になるタイプです。具体的には赤が弱い「プロタノープ」、緑が弱い「デュタノープ」などがあります。
また、青に関する問題は「トリタノープ」と呼ばれますが、非常に稀です。
後天性の色覚異常は、眼病や薬の副作用で色が見づらくなるケースが多く、視力低下や視野欠損と合わせて症状が出ることもあります。
色弱と色覚異常の見分け方と検査方法
色弱か色覚異常かを判断するためには、専門の検査を受ける必要があります。
代表的な検査法として「石原式色覚検査表(イシハラテスト)」や「パネルD-15検査」があります。
石原式では、点で描かれた数字や模様を見て識別できるかを確認します。パネルD-15は色を類似色から順に並べる検査で、どの色の区別が苦手かより具体的に判断できます。
これらの検査をクリアできない場合が「色覚異常」に該当しますが、軽度の識別困難なら「色弱」と診断されます。
色弱や色覚異常がある人の日常生活への影響
色弱や色覚異常は、日常生活での色の判別に影響を及ぼしますが、多くの場合、工夫や補助具で対処可能です。
例えば、信号機の色がわかりづらい人は位置や形で判断したり、専用のメガネやアプリも利用されています。
教育や職業選択の際にも配慮が必要なことがあります。特に交通や医療、デザインの分野など、色の区別が重要な仕事では理解を深めることが大切です。
最近では社会の認知度も上がり、さまざまな支援ツールが開発されています。
色弱と色覚異常の違いのまとめ表
色弱という言葉はよく聞きますが、実は「色弱」は色覚異常の中の一つのタイプであることをご存じですか?たとえば赤と緑の区別が苦手な人が多いですが、中には青が弱いタイプもあり、とても珍しいんです。身近な色の見え方の多様さを考えると、色の世界は案外奥深いですよね。色に関する悩みや工夫は、日常生活の中で気づかぬうちに支え合っています。
前の記事: « 色と視認性の違いとは?見やすさを左右するポイントを徹底解説!
次の記事: 近似色と類似色の違いをわかりやすく解説!見分けるポイントとは? »





















