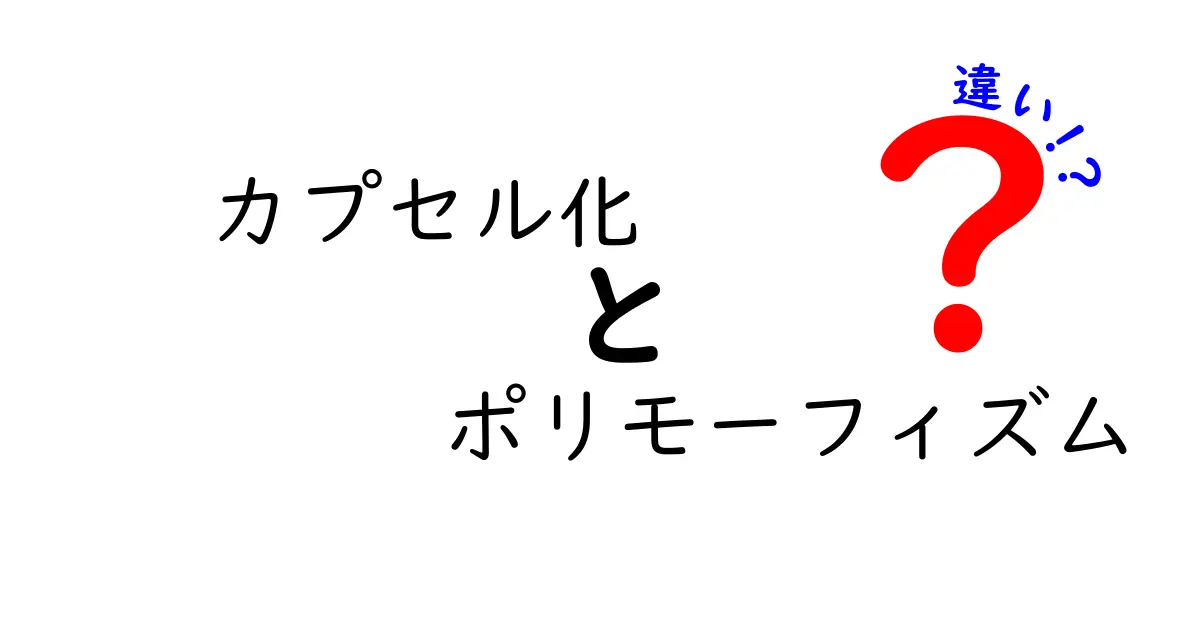

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
カプセル化とは何か?
オブジェクト指向プログラミングでよく耳にするカプセル化は、簡単に言うと「データを守る仕組み」です。
例えば、スマートフォンには画面の明るさや音量といった情報がありますが、簡単に勝手に変えられたら困りますよね。
カプセル化はそんな情報を外から直接触れられないように隠して、決められた方法でだけ操作できるようにする技術なんです。
具体的には、データ(変数)をクラスの中で非公開(private)にし、外部からは公開されたメソッド(関数)を通じてのみ操作できるようにします。こうすることで、データの安全性が守られ、不正な使い方を防げます。
この仕組みは例えば銀行の口座情報やゲームのキャラクターの能力値など、勝手に変更されてはいけない情報を守るためにとても重要な考え方です。
つまり、カプセル化はデータを隠し、管理することでプログラムの安全性と安定性を高める手法なんですね。
ポリモーフィズムとは何か?
一方、ポリモーフィズムは少し難しく聞こえますが、中身は「同じ名前でいろんな形で動くこと」という意味です。
例えば、動物というクラスがいて、「鳴く」という動作を指示したとします。
犬なら「ワンワン」、猫なら「ニャー」とそれぞれ違う鳴き方をしますよね。
これがポリモーフィズムのイメージです。同じ命令でも、その動物に合わせて違う動きをする、つまり同じ名前のメソッドが状況に応じて異なる動作をすることを意味します。
プログラムの中で、同じ操作なのに違った処理が行えるので、プログラムを書くときに便利で柔軟な設計ができるのが利点です。
これにより複雑な処理を簡単にしたり、新しい動物が増えてもプログラムを修正しやすくなります。
まとめると、ポリモーフィズムは同じメソッドで異なる振る舞いを実現する技術です。
カプセル化とポリモーフィズムの違いを表にして比較
カプセル化とポリモーフィズムはどちらもオブジェクト指向の重要な概念ですが、役割や目的が全く違います。
カプセル化は「守ること」、ポリモーフィズムは「変化させること」と覚えると理解しやすいでしょう。
これらをうまく使うことで、より安全で柔軟なプログラムを書くことができ、初心者でもわかりやすい設計が可能になります。
オブジェクト指向を学び始めた人はまずカプセル化で「データを守ること」の大切さを理解し、次にポリモーフィズムで「同じ操作で異なる動作をさせる楽しさ」を体験してみてくださいね。
どちらもプログラミングをより楽しく、強力にする武器になります!
ポリモーフィズムについて話すと、同じ『鳴く』という命令でも、犬がワンワン鳴き、猫がニャーと鳴くのは面白いですよね。
これはプログラムでも同じ名前の関数やメソッドが状況に合わせて違う動きをする仕組みなんです。
こうすることでプログラムを書く人は、色んな動物に合わせた処理を一つの命令で済ませられるんですよ。
だから、新しい動物が増えても柔軟に対応できるんですね。
まさに『多態性』の面白さがここに詰まっています!
前の記事: « 参照型と基本データ型の違いを中学生でもわかるように徹底解説!





















