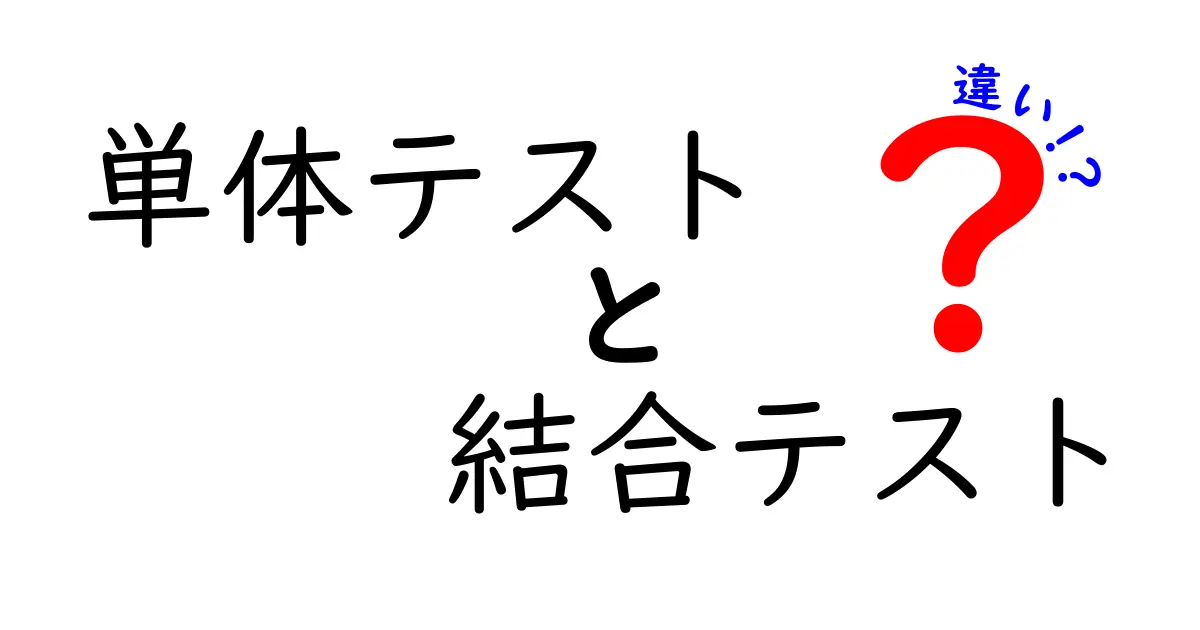

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
単体テストとは何か?
プログラムを書くときには、たくさんの部品やパーツを作ります。
その一つ一つのパーツが正しく動くかどうかを確かめるために行うのが単体テストです。
例えば、電卓アプリを作るときに「足し算をする部分だけ」を取り出して、ちゃんと1+2=3になるかを確かめるイメージです。
単体テストは
・プログラムの小さい部分をチェックする
・バグを早く見つけやすい
・問題が起きても原因がはっきりしやすい
という特徴があります。
ですから、単体テストはプログラムの品質を上げる最初のステップとしてとても大切です。
しっかり単体テストができていると、その後の作業がずっと楽になります。
結合テストとは何か?
単体テストでそれぞれのパーツがちゃんと動くことを確かめたあと、次はそのパーツ同士をつなげて動かします。
このときに動き方をチェックするのが結合テストです。
つまり、単体テストは「一つ一つのパーツのチェック」、結合テストは「パーツを組み合わせたときの動作チェック」と言えます。
例えば、先ほどの電卓アプリだと「足し算」と「引き算」のパーツは単体テストでチェックしますが、ユーザーが「足し算の後に引き算をする」という手順を行った時に正しく計算できるかを確かめるイメージです。
結合テストは、
・パーツ同士のやりとりがうまくいっているか確認する
・全体の動作をスムーズにする
・単体テストでは見つかりにくい問題を見つける
という役割があります。
単体テストと結合テストの違いを一覧表でチェック!
原因が特定しやすい
全体のスムーズな動作保障
なぜ両方のテストが必要なの?
単体テストだけでは、部品単体の問題は見つかっても、組み合わせたときに起きる問題には気づきにくいです。
結合テストだけにすると、問題がどの部品から来ているか原因を見つけるのが難しくなります。
だから、単体テストと結合テストの両方を行うことで、効率よくバグを見つけて修正できます。
ソフトウェアの品質を高めて、使いやすいプログラムを作るためには、この2つのテストが欠かせません。
「単体テスト」という言葉はプログラミング初心者には少し難しく感じられるかもしれません。でも面白いのは、単体テストはまるで“部品の健康診断”のようなものだということです。一つ一つのパーツがちゃんと動くかを調べて、問題があればすぐに直す。この細かいチェックが、後の大きなトラブルを防ぐヒントになるので、ソフトを安全に、そしてスムーズに動かす大事な工程なんですよ。
前の記事: « リファクタとリファクタリングの違いとは?初心者にも分かる解説!
次の記事: シーケンス図とラダー図の違いとは?初心者でもわかる基礎解説 »





















