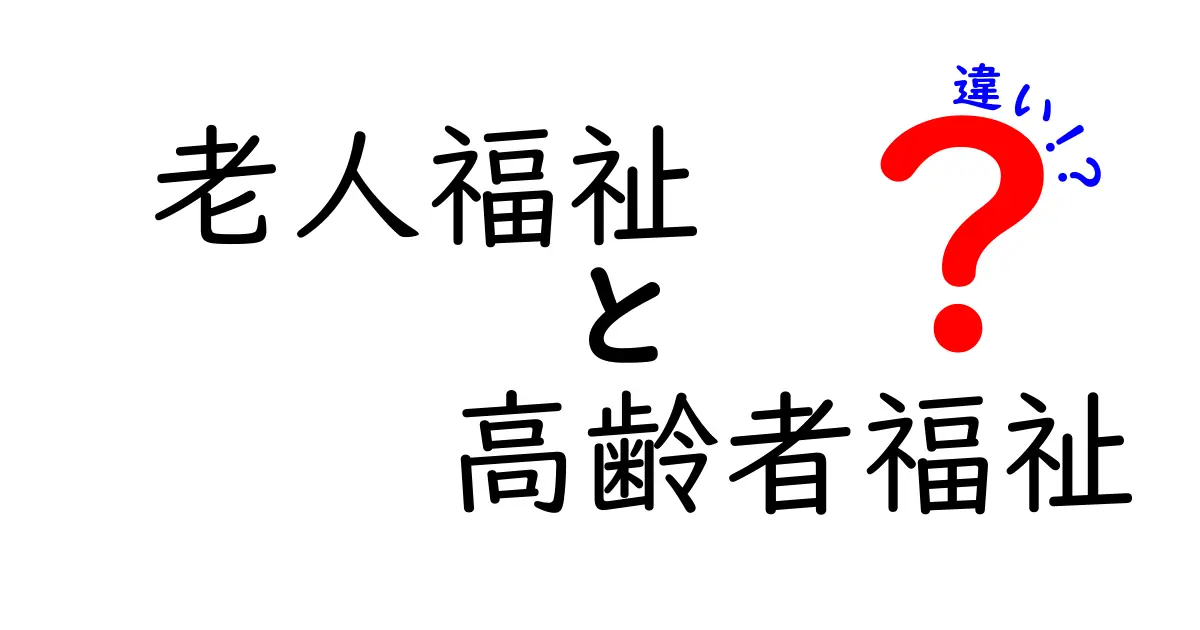

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
老人福祉と高齢者福祉は何が違うの?
日本では年をとった人たちを支える仕組みがたくさんありますが、その中でもよく聞くのが「老人福祉」と「高齢者福祉」という言葉です。
この二つの言葉は似ているようですが、実は少し違った意味や使われ方をしています。
まず「老人福祉」は、主に社会福祉の分野で使われ、60歳以上の人を対象にさまざまな支援やサービスを提供することを指します。一般的には戦後の社会福祉制度の中で使われ始めた言葉で、古くから高齢者を意味する「老人」という言葉とともに使われてきました。
一方で「高齢者福祉」は、より広い意味で使われることが多く、65歳以上の人を指すことが一般的になっています。社会の高齢化にともない、単に「老人」という言葉よりも「高齢者」という言葉のほうがやわらかく、偏見を避けるために使われることが多くなりました。
老人福祉と高齢者福祉の特徴とサポート内容
老人福祉:
・対象年齢:60歳以上(歴史的にそうされてきた)
・主な内容:生活支援、介護サービス、健康管理
・制度例:老人ホームや介護保険の前身となる福祉事業
高齢者福祉:
・対象年齢:65歳以上が中心
・主な内容:医療・介護・就労支援・地域活動の促進
・特徴:より包括的で現代的な高齢者支援の考え方
これらの違いをわかりやすく表にまとめると次のようになります。項目 老人福祉 高齢者福祉 対象年齢 60歳以上 65歳以上(一般的) 用語の時代背景 戦後の福祉制度で使われることが多い 高齢化社会に合わせて登場したやわらかい表現 支援内容 生活支援や介護が中心 医療・介護・就労など幅広い支援 言葉の印象 やや古いイメージ 現代的・偏見を避ける表現
なぜ言葉の違いに注目するの?
日本では高齢者の数がどんどん増えています。
そのため、福祉の仕組みや支援方法も変わってきました。
昔は「老人」という言葉が当たり前でしたが、最近は「高齢者」という言葉が好まれています。
これは、年をとった人を尊重し、偏見や差別を避けるためです。
また高齢者福祉は、単に生活の助けだけでなく、健康的に長く暮らせるように、働く場所を作ったり、社会参加を促したりすることにも力を入れています。
つまり、言葉の違いは、その背景にある考え方の違いも表しているのです。
これからも高齢者の暮らしをより良くするために、言葉の意味を知り、理解を深めることが大切です。
「高齢者福祉」という言葉は、単なる介護や生活支援だけでなく、実は『社会参加の促進』という大切な意味も含んでいるんです。例えば、高齢者が地域の活動に参加できるようにサポートしたり、お仕事を続けられる環境づくりをしたりしています。
昔は「老人は家で休むもの」というイメージが強かったけど、今は「自分らしく元気に社会で活躍したい」と考える高齢者が増えているんですね。
こうした時代の変化を反映して、「高齢者福祉」の考え方も広がっています。だから単なる支援だけじゃなく、楽しみや生きがいをつくる取り組みが大事になるんですよ。
前の記事: « ショートステイと老健の違いとは?わかりやすく解説!





















