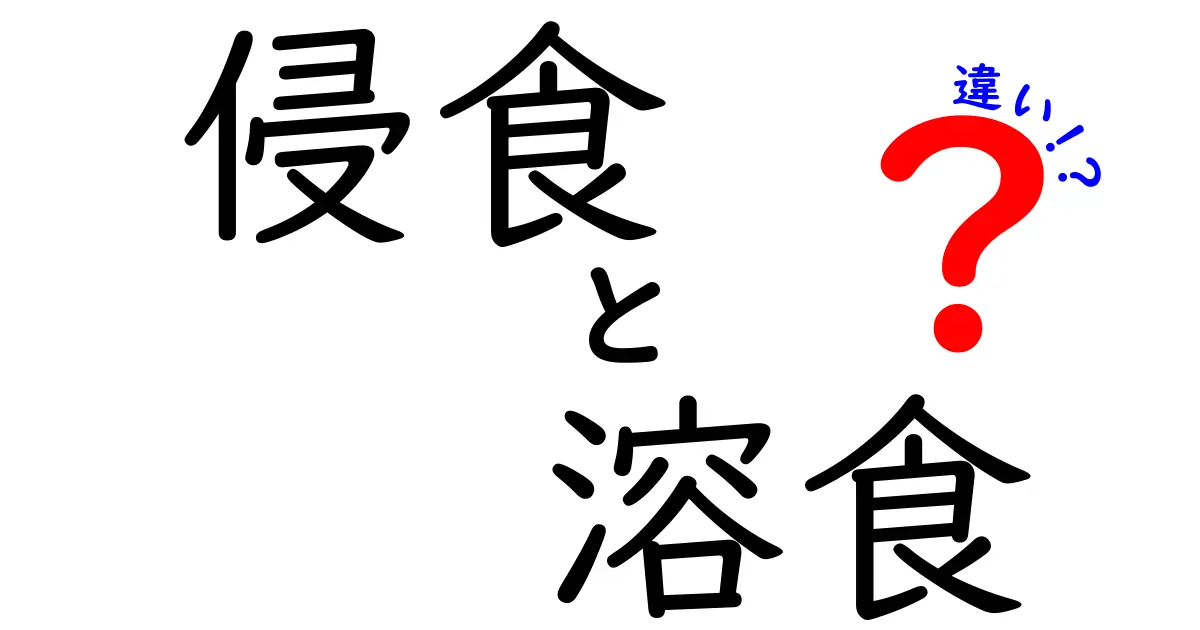

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
侵食と溶食の基本を理解しよう
自然の力で岩や土が削られていく現象に侵食と溶食があります。どちらも地形を変える重要な働きですが、実は違いがあるのです。
まず侵食とは、風や水、氷などが土や岩を物理的に削ったり運んだりする現象です。たとえば、川の流れが岩を削ったり、強い風が砂を運んで丘を削ったりします。
一方、溶食は化学的な反応で岩石が溶けて削られる現象です。特に炭酸カルシウムを含む石灰岩が酸性の水に溶けていくことが代表的です。洞穴や鍾乳洞ができるのはこの溶食の働きによるものです。
侵食と溶食の違いを詳しく比較!
侵食と溶食は似ていますが、ポイントは削られる仕組みです。
侵食は主に物理的な力によって岩や土がこすられたり砕かれたりします。水の流れや風、氷の動きが代表的な要因です。
溶食は化学的な溶解作用で、岩の成分が水に溶け出してしまうプロセスです。特に酸性の水が石灰岩に作用すると溶解が進みます。
下の表でそれぞれの特徴を見てみましょう。
自然の中での侵食と溶食の役割と意義
侵食と溶食は長い時間をかけて地球の景色を作り変えています。
侵食によって川が渓谷を刻み、強い風が砂漠の形をつくります。氷河による侵食では巨大なU字谷が形成されます。これらは自然の力で形作られる美しい景観の元となります。
また溶食は石灰岩の洞窟を作り、中は独特の鍾乳石や石筍が成長します。カルスト地形は水が岩を溶かすことでできた穴や裂け目が多く、水の通り道が複雑に張り巡らされています。
両者は違うしくみですが、地形を特色づけたり地下水の流れをつくったりする自然の大切な働きなのです。
溶食は石灰岩が酸に溶ける現象ですが、実は口の中の歯も酸に溶けることで虫歯になりますよね。石灰岩と歯はカルシウムを多く含んでいるため、科学的には似た溶解の仕組みが存在するといえます。自然の溶食と身近な虫歯。理科の授業で自然現象と体の仕組みを結びつける面白い話題になりますよね。酸によってものが溶けるという点で、溶食の理解も深まります。
次の記事: 流紋岩と花崗岩の違いとは?見た目・成分・でき方を徹底解説! »





















