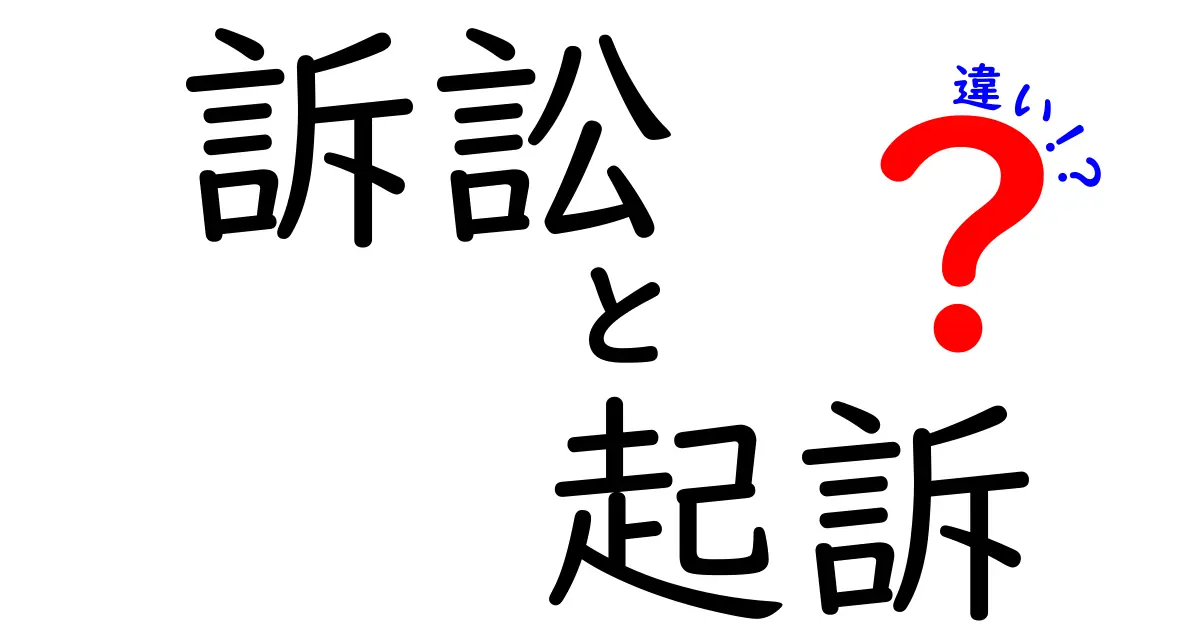

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
訴訟と起訴、まずはそれぞれの意味から理解しよう
法律の話でよく出てくる「訴訟」と「起訴」は、似ているようで違うものです。
訴訟とは、一般の人や会社が誰かを相手にして裁判を起こし、争いを解決することを言います。例えば、お金の貸し借りで問題が起きた時に裁判で解決したいときに使います。
一方、起訴は警察や検察が刑事事件の犯人を裁判にかけるために裁判所に訴えを起こすことを意味します。つまり、犯罪があった場合の手続きです。
それでは、それぞれの特徴や違いを詳しく見ていきましょう。
訴訟の仕組みと特徴について
訴訟は主に民事訴訟と呼ばれ、個人や会社などが相手に損害賠償や契約の履行を求めたりする時に起こします。
具体例としては、借金の返済がされない、土地の境界線で揉めている、商品に欠陥があったなどがあります。
この場合、訴訟を起こす人は原告、訴えられた側は被告と呼ばれます。
裁判所(民事裁判所)が両者の話を聞いて、法律に基づき判断を下します。
また、訴訟では争いの原因を証明するために証拠を示したり、証人の意見を聞くなど複雑な手続きが必要です。
起訴の意味と流れ
起訴は刑事事件の手続きで、警察が調べた結果、犯罪をした疑いのある人について起こされます。
起訴をするのは検察官で、被疑者(犯罪の疑いがある人)を裁判にかけることを裁判所に伝えます。
起訴されると、その人は裁判所で裁判を受けることになります。
起訴の決定は「起訴する」「不起訴(起訴しない)」の二択で、不起訴の場合は裁判に進みません。
起訴は犯罪を裁くための重要なステップで、裁判の始まりと言えます。
訴訟と起訴の違いを表で比較!
まとめ:法律を理解する第一歩として大切なこと
今回の解説でわかったように、訴訟は個人間や企業間の問題を解決する裁判で、起訴は検察官が犯罪を裁判にかけるための手続きです。
日常生活ではあまり聞きなれない言葉かもしれませんが、知っておくことでニュースや事件の話も理解しやすくなります。
これらの違いをしっかり覚えておくと、法律の話題に弱くなくなり将来役立つ知識になりますよ。
ぜひ、これをきっかけに法律に興味を持ってみてくださいね。
起訴という言葉は、ニュースでよく「起訴されました」と聞きますが、実はこれは検察官がその人を裁判にかけることを決めた証拠なんです。
意外と知られていませんが、起訴されなければ裁判は始まりません。
検察官はじっくりと調べてから起訴するかどうか決めるので、これは『罪を確実に証明できるか』を意味すると考えるとわかりやすいですよ。
つまり、起訴は法律の世界でいうスタートの合図のようなものなんです。
次の記事: 懲役と禁固の違いをわかりやすく解説!刑罰の基本を学ぼう »





















