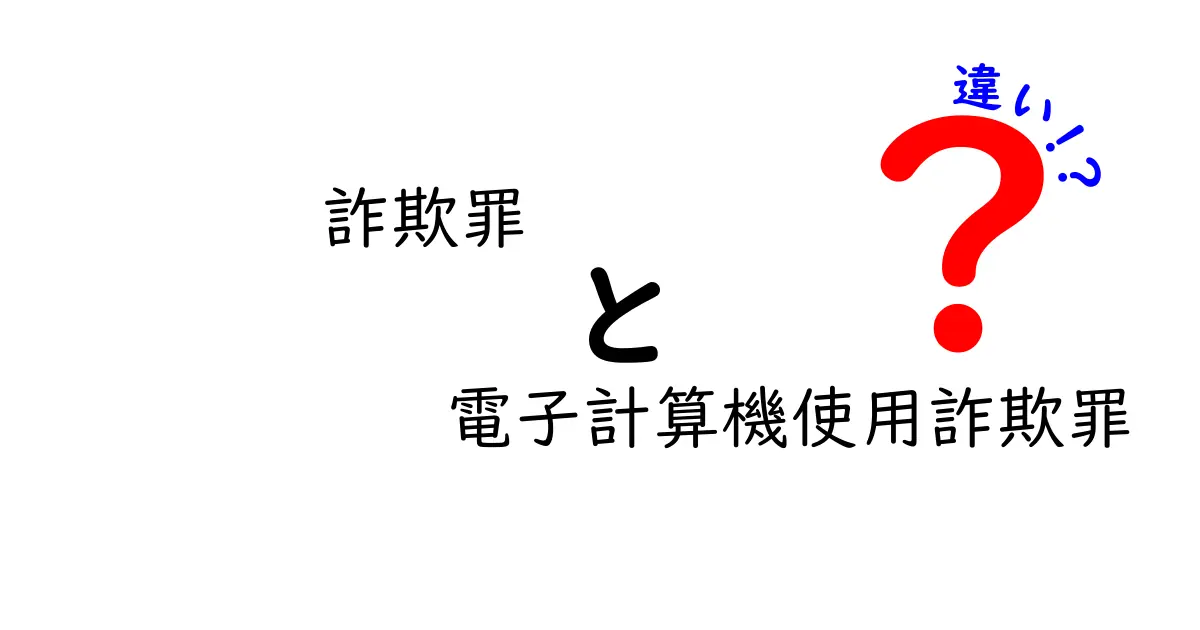

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪って何?
まず、詐欺罪とはどんな犯罪か簡単に説明します。詐欺罪は、人をだましてお金やものをだまし取る犯罪のことです。たとえば、嘘の話をして誰かからお金を騙し取ることがこれに当たります。詐欺罪は刑法で規定されていて、法律上厳しく罰せられます。
一方、電子計算機使用詐欺罪というのは、詐欺罪の中でも特にコンピューターやインターネットを使って行われる詐欺のことを指します。パソコンやスマートフォンを使って偽のウェブサイトを作ったり、電子メールで嘘を流すなどの行為がこれに含まれます。
このように、詐欺罪は広い意味で人をだます犯罪全般を指し、電子計算機使用詐欺罪はその中でも特にコンピューターを使った詐欺のことをいいます。
詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪の法律上の違いとは?
では、法律上はどのような違いがあるのでしょうか?
詐欺罪は、刑法246条に書かれていて、人を騙して財産を取ることを処罰します。たとえば、偽の情報を使って現金を奪うことなどです。
一方で、電子計算機使用詐欺罪は刑法248条の2に規定されています。こちらは、電子計算機やネットワークを使って詐欺を行う場合に特別に適用される条文です。この法律の特徴は、嘘のプログラムやデータを使って他人の財産をだます行為を罰することにあります。
つまり、普通の詐欺に加えて、コンピューターの仕組みを悪用した詐欺行為が明確に法律で区別されているのです。
具体的な違いをわかりやすく表で比較!
| ポイント | 詐欺罪 | 電子計算機使用詐欺罪 |
|---|---|---|
| 対象行為 | 人を騙して金品を奪う一般的な詐欺 | コンピュータ・ネットを使いプログラムやデータを偽装する詐欺 |
| 法律の条文 | 刑法 第246条 | 刑法 第248条の2 |
| 使われる道具 | 口頭、文書、その他 | 電子計算機、ネットワーク |
| 特徴 | 直接的なだまし取り | プログラムやデータの偽装が中心 |
| 例 | 嘘の話をしてお金を取る | 偽のネットバンキング画面でログイン情報を盗む |
まとめ:どう使い分けられるの?
詐欺罪は昔からある一般的な騙しの犯罪です。
それに対して電子計算機使用詐欺罪は、ITが発達した今の時代に対応して作られた特別な法律です。
だから、普通の騙しとネットを使った騙しは法律上もしっかり区別されており、違う罪として扱われています。
これからの時代もますますコンピューター技術が進むので、こういった法律の理解はとても大切です。
みなさんもインターネットやスマホを使うときは詐欺に遭わないよう気をつけましょう!
「電子計算機使用詐欺罪」という言葉、ちょっとむずかしそうですよね。でも、要はコンピューターを使った詐欺のことなんです。例えば、ネットバンキングの偽物サイトに騙されてしまうこともこれにあたります。最近の詐欺はネットを使うことが多いので、法律でも特別にカバーしているんですね。ところで、こんなに法律が細かいのに、詐欺を見破るのはなかなか難しくて、警察も日々勉強しているんですよ。だから、怪しいメールやサイトは触らないのが一番安全です!
前の記事: « なりすましメールとフィッシングメールの違いとは?簡単に解説!
次の記事: 虚偽表示と詐欺の違いとは?わかりやすく解説! »





















