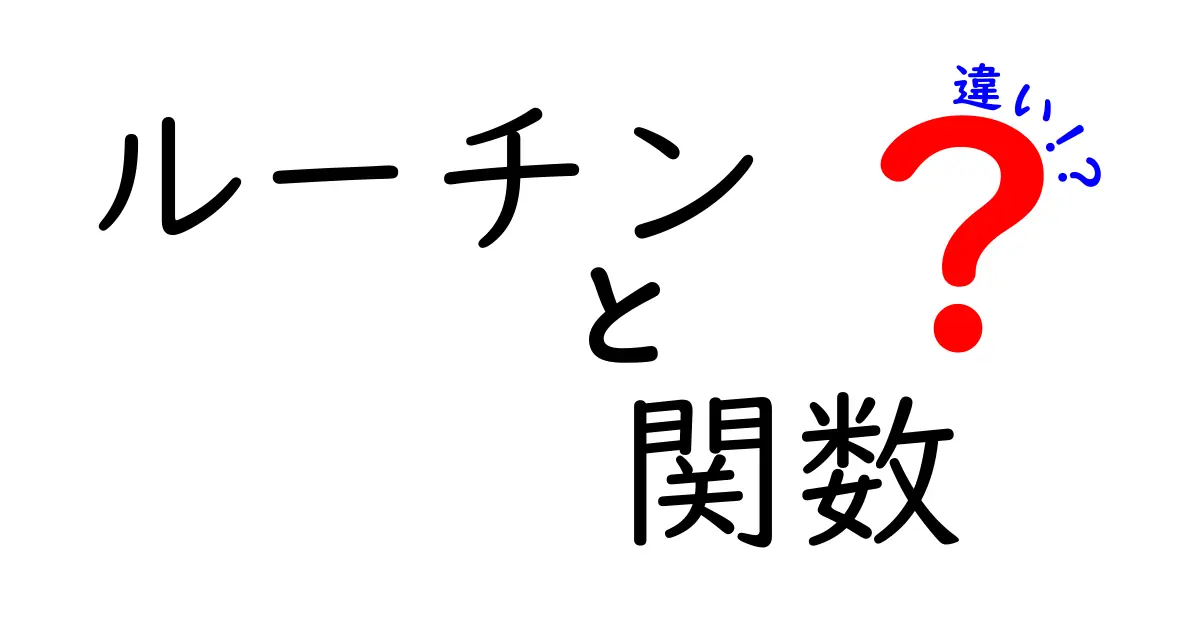

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ルーチンと関数の違いを知ろう
プログラミングを学ぶときに耳にする「ルーチン」と「関数」という言葉は、同じように使われる場面も多いのですが、実は意味や使い方が異なります。初めて触れる人にとっては混乱しやすいポイントです。ここでは中学生にもわかるように、両者の基本を整理し、現場での使い分けのコツを丁寧に解説します。
まず大事なポイントは、「ルーチンは処理のまとまりを指す言葉」、「関数は入力を受け取り出力を返すような計算処理を指す言葉」という点です。言葉の定義が分かると、実際のコード設計でも迷いにくくなります。
加えて、歴史的な背景や言語ごとの使われ方の違いも覚えておくと、より深く理解できます。
この後の章では、もう少し具体的な distinction(差)を掘り下げ、実際の例を交えながら分かりやすく説明します。
最初に知っておきたいのは、「ルーチンと関数は共通点も多いが、目的と戻り値の扱いが異なる」ということです。両者は再利用可能なコードの部品ですが、設計の観点が違うため、どう組み合わせるかでプログラムの読みやすさや保守性が大きく変わります。
この区別がつくと、学習の道筋がはっきりと見えてきます。次の章では、基本の意味をもう少し具体的に整理します。
基本の違いを整理する
ここでは、ルーチンと関数の「基本的な違い」を、日常の例でイメージしやすく整理します。
ルーチンは、作業の手順をひとつのまとまりとして扱う集合です。例えば、部屋を掃除する一連の動作を考えてみましょう。床を掃除する、棚を拭く、ゴミを分別する、といった作業を順番に実行します。これらは「いちおう同じ目的(部屋をきれいにする)」に向かう、複数の手順の集合です。ルーチンはこのまとめ方自体を指すことが多く、必ずしも値を返すとは限りません。
一方、関数は「入力を受け取り、それに基づいて何かの値を返す計算の単位」です。算数の計算のように、同じ入力には同じ出力が返ってくる、という性質を持つことが多いです。プログラムの世界では、引数としてデータを渡し、結果として新しいデータを得る、という形が基本です。
この二つの違いは、設計時の視点を変えます。ルーチンは作業の組み合わせを重視、関数はデータ処理の変換を重視する、というように捉えるのが分かりやすいでしょう。
具体例と現場の使い分け
現場での使い分けは言語の特徴だけでなく、設計の方針にも影響します。代表的な区分を以下に整理します。
例1: ルーチン寄りの設計 処理の順序や副作用を重視する場合、例えば、ゲームの「プレイ中のイベント処理」や、アプリ起動時の初期化手順などが挙げられます。これらは必ずしも値を返さず、実行すること自体が意味を持つケースが多いです。
例2: 関数寄りの設計 入力に対して常に同じ出力を返す、純粋な計算を重視する場合、例えば数値計算や文字列操作、データ変換の処理などが該当します。関数を適切に分割すると、テストがしやすくなり、バグを見つけやすくなります。
実際には、現場の多くのプログラムは「ルーチンと関数の混在」で成り立っています。大事なのは、役割をはっきり分け、適切な場所に適切な単位を配置することです。これにより、コードが読みやすく、再利用もしやすくなります。
まとめ:ルーチンと関数は、プログラムを組み立てる最小単位として互いに補完します。初心者のうちは「関数は値を返すもの」という理解を先に固め、次に「ルーチンは作業の流れ」を意識すると、自然と設計のコツがつかめます。学習を進めるうえで大切なのは、実際のコードを書きながら両者の使い分けを経験することです。練習問題として、日常の家事の手順をルーチン化し、同じ手順を繰り返し使えるように組み替えてみると、理解が深まります。
「ルーチンは、部屋をきれいにする一連の行動そのものを指す。棚を拭く、床を掃除する、窓を開ける――これらは順序が大事な作業の集合だね。対して関数は、何かを入力して、それを元に新しい結果を出す、計算の道具だ。入力と出力の関係がはっきりしていると、同じ入力にはいつでも同じ答えが返るんだ。」
彼は少し納得して、ルーチンを「手順の再利用可能な部品」としてまとめ直しました。私たちは同じ演習問題を解くのに、まずルーチンを作ってから、それを組み合わせて関数的な処理を作る練習をしました。こんなふうに、身近な例から始めると、抽象的な用語もぐんと分かりやすくなるんですよ。





















