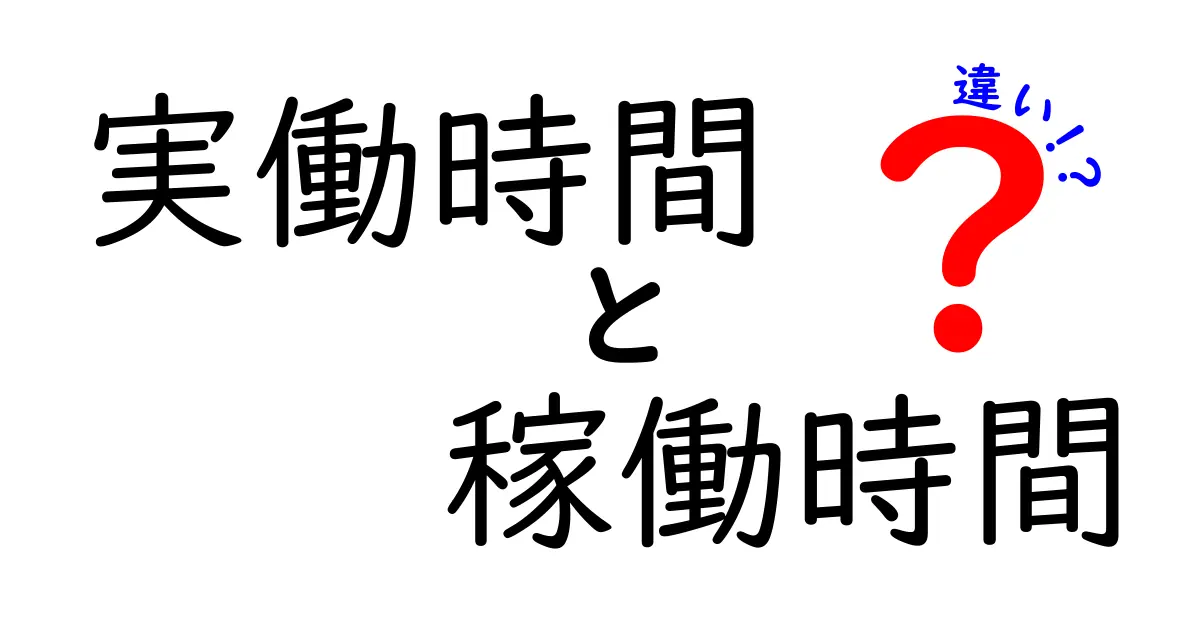

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
実働時間と稼働時間の基本を押さえる
時間の考え方には意味の違いがあり、異なる場面で用いられる。ここでは実働時間と稼働時間の違いを、日常の職場や工場の現場での実例を交えながら、やさしく解説します。まずは実働時間とは何かを整理します。
実働時間は「実際に作業をしている時間」です。ここには休憩や待機、指示待ちの時間など、作業を行っていない時間は基本的に含まれません。学校の授業で言えば、机に座ってノートを開いている時間が実働時間に近いイメージです。ただし現場では、作業の準備や後片付けの時間も含むかどうかで解釈が分かれることがあります。これを正しく把握するには、測定のルールを事前にチームでそろえることが大切です。
一方稼働時間は「機械や設備が実際に動いていた時間」または「ライン全体が作動していた時間」を指すことが多いです。人が操作して直接作業していなくても、機械が回っている時間なら稼働時間にカウントされます。現場の用語としては、稼働時間は設備の状態や点検、切替の時間も含めて測定されることがあり、実際の作業と重なる部分がある一方、ずれてしまうこともあります。つまり、同じ現場でも「誰の時間を測るのか」「何を含め、何を省くのか」という区別を明確にしなければ、数字はぶれてしまいます。
この違いを理解するコツは、測定の目的と対象をはっきりさせることです。例えば、人のパフォーマンスを評価したいときは実働時間を、設備の効率を評価したいときは稼働時間を中心に見ると、混乱を避けやすくなります。以下の表と例を参考にすると、現場の実情が見えやすくなります。
| 指標 | 意味 | 計測対象 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 実働時間 | 実際に作業を行っている時間 | 人が作業している時間 | 休憩や待機時間は場合により除外される |
| 稼働時間 | 機械・設備が動作していた時間 | 機械・ラインの運転時間 | 準備・切替・停止時間を含む/含めないは測定ルール次第 |
| 例 | 例示 | 例示 | 注記 |
| 計測方法 | 測定の方法 | 打刻・センサー・ログ | 目的に応じて選ぶ |
日常の現場で役立つ見分け方と実務上のポイント
現場で実務として使える見分け方のポイントをいくつか列挙します。まず第一に、測定の対象を明確にします。人の時間を測るなら実働時間、機械の時間を測るなら稼働時間と区別します。次に、休憩の扱いを決めておくこと。例えば昼休憩を実働時間に含めるのか、稼働時間に含めるのかは現場の規則で揺れやすいので、事前に書面化しておくと混乱を避けられます。さらに、待機時間の扱いも重要です。作業待ちや指示待ちの時間は実働時間に含めるべきか、稼働時間に含めるべきか、現場のルールに合わせておくと良いでしょう。
具体例として、ある工場のシフト計画を例に挙げます。スタッフが実際に手を動かして作業している時間は8時間、その中で休憩が1時間、準備と片付けが0.5時間、機械の稼働時間が7.5時間と記録されるケースがあります。ここから見えるのは、実働時間と稼働時間が必ずしも同じ長さにはならないという事実です。数字を見ただけでは現場の実態が読みにくい場合があるため、日次・週次で両方の指標を並べて比較すると、ボトムアップの改善案が立てやすくなります。
最後に、表現の統一にも注意します。社内資料や報告書で“実働”と“稼働”を混同してしまうと、後からデータを解釈する人に誤解を生むことがあります。可能なら、まずは“誰が、いつ、どのくらい作業していたのか”を個別に記録し、そこから実働時間と稼働時間を派生させていく方法がおすすめです。これらのポイントを押さえれば、数字の意味を共有でき、現場の改善点を正しく示せます。
友人と雑談していて、実働時間と稼働時間の話題になった。僕はこう答えた。『実働時間は作業に直接使われた時間、休憩や待ち時間は除くことが多い。稼働時間は機械が動いていた時間のことを指すことが多いから、同じ現場でも数字が違って見えるんだ。例えばラインが2時間動いていて、途中で2回停止していたとする。実働時間は1時間半になるかもしれないが、稼働時間は2時間強かもしれない。要するに、何を測るかで数字が変わるということ。'}





















