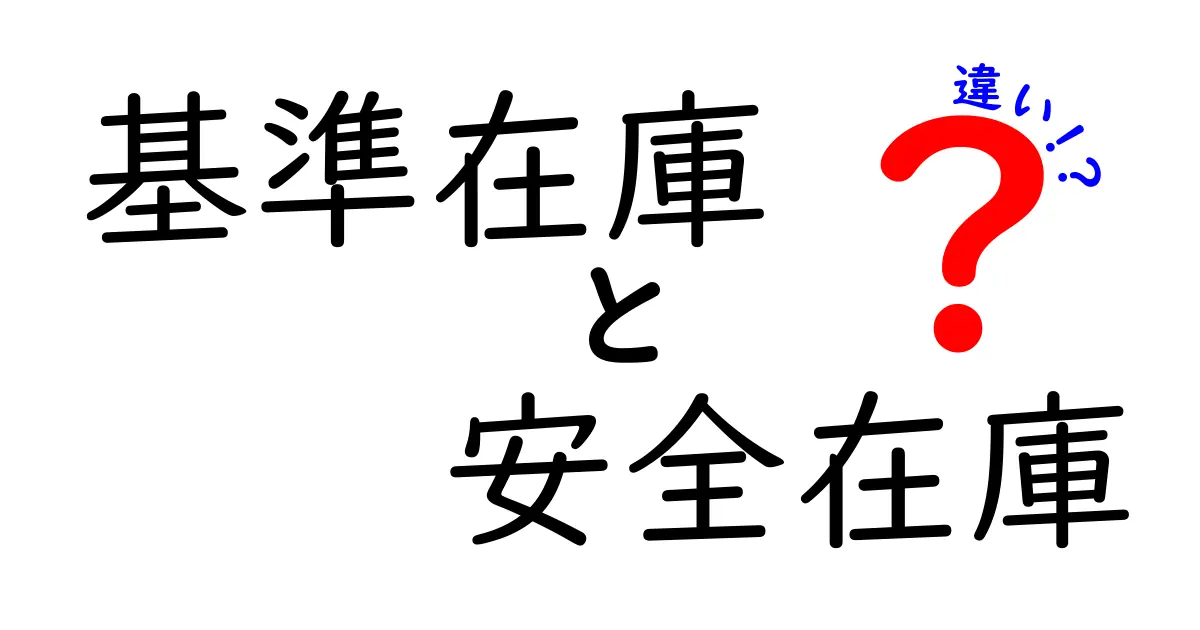

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
基準在庫と安全在庫の違いを完全に理解するためのガイド
在庫を管理する場面でよく耳にする言葉に「基準在庫」と「安全在庫」があります。どちらも在庫量の目安を示す数字ですが、意味や目的が違います。ここでは基準在庫と安全在庫の本質を、中学生にも分かるように、日常の例と数字を交えながら丁寧に解説します。まずは結論から言うと、基準在庫は日常の平均的な需要を想定した“通常運転の在庫”で、安全在庫は不確実性に備える“余裕分の在庫”です。それぞれの役割を正しく理解することが、無駄なコストを減らし、品切れを防ぐコツになります。
基準在庫とは何か
まず基準在庫の基本イメージを掴みましょう。基準在庫は、通常の需要と通常のリードタイムを前提に設定される“最低限の在庫量”のことです。想定される日々の消費量をもとに作られるため、安定した供給が続くときの標準値として機能します。例えば、毎日10個の商品が売れると予想され、発注リードタイムが2日間なら、基準在庫はおおよそ20個前後に設定されることが多いです(実務では配送遅延などを考慮して微調整します)。この量を下回ると補充のサイン、つまり発注の目安になります。つまり基準在庫は、普段の需要を“現状維持”するための最低限のラインです。
基準在庫の設定は、需要予測の精度や棚卸コスト、保管スペースなどの制約とバランスをとります。在庫回転率を考えると、この基準在庫は過剰在庫を減らす一方、欠品リスクを減らす最小限のラインにもなります。現場の実務では、月間の平均販売個数、週ごとのばらつき、季節変動、プロモーション期間などを考慮して、定期的に基準在庫を見直します。
基準在庫は在庫管理の“土台”となる数値です。
なお、別の文献では“基準在庫量”を「発注点の一部」として説明することもあります。いずれにせよ、基準在庫は“通常運用のための最小ライン”と理解しておくと混乱が少なくなります。
安全在庫とは何か
次に安全在庫について説明します。安全在庫は、需要のばらつきや供給の遅延といった不確実性に対応するための“余裕”です。ここが基準在庫と大きく異なる点で、欠品を起こさないための防波堤となります。安全在庫を増やせば欠品リスクは減りますが、同時に在庫コストが増えます。実務ではサービスレベルという目標を設定し、それに合わせて安全在庫を決めます。例えば、月平均の需要が1000単位で、リードタイムが4日、日の需要が平均して33単位、需要の変動が大きい場合は安全在庫を数百単位とするなど、数字は企業ごとに異なります。
安全在庫の設定には、過去のデータ分析が欠かせません。需要が急に増える時期(季節要因、キャンペーン、天候など)には安全在庫を引き上げ、通常時には引き下げてコストを抑えます。さらにサプライヤーの納期遅延リスクを考慮して、複数の納入先を持つ企業は安全在庫を分散させることでリスクを分散します。
基準在庫と安全在庫の違いをわかりやすく比較
この表を見れば、基準在庫は“通常運用のための土台”であり、安全在庫は“想定外の波風を受け止める余裕”だということが分かります。両者の役割を理解して組み合わせると、欠品を減らしつつ在庫コストを抑えることが現実的になります。現場では、データ分析と現場の感覚を両輪にして、サービスレベルに合わせた最適なラインを設定することが大切です。
実務での活用ポイント
- データを集めて需要・リードタイムの傾向を把握する
- 基準在庫と安全在庫のバランスを自社のサービスレベルで設定する
- 在庫可視化ツールでリアルタイムの状況を把握する
- 季節変動や天候リスクを考慮して安全在庫を定期的に見直す
- サプライヤーの信頼性を評価してリスク分散を図る
このように基準在庫と安全在庫を組み合わせると、欠品を減らしつつ在庫コストを抑えることができます。現場では数字と現場感覚を両方使って、サービスを安定させることが大切です。
友達のユウとミナは学校の文化祭の準備で話しています。ユウは「安全在庫って何ですか?」と尋ね、ミナは「売り切れを防ぐための余分な在庫だよ」と答えます。ミナはさらに、天候や配送の遅れ、急な需要増を想定して余裕を持たせることが大事だと説明します。「安心感が違うんだ」とユウは納得します。二人は安全在庫を決める時に、過去の売上データとリードタイムの変動をグラフにしてみることにしました。需要が平均より大きくぶれる季節は、少し多めに設定する。逆に安定している時は最小限に抑える。このようにデータと現場の感覚を両輪にするのが、無駄を抑えつつ欠品を減らすコツだと気づきました。





















