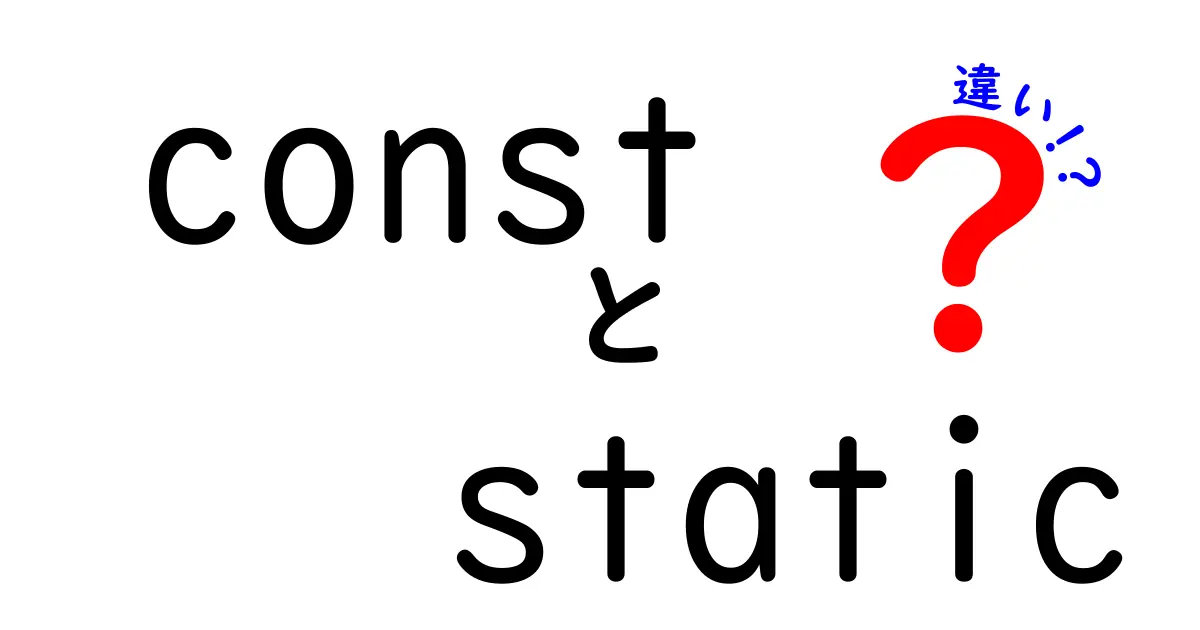

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
constとstaticの基本の理解
プログラミングを学ぶとき、つい混乱するのがconstとstaticの違いです。簡単に言えばどちらも「値の扱い方」に関係しますが、使い方や意味が言語ごとに違います。ここではC/C++風の考え方とJava風の考え方、そしてJavaScriptの現代的な使い方の3つの観点を混ぜずに、基本となる考え方を整理します。まずは共通点と相違点を整理しましょう。共通点としては、どちらも「値や状態をどう扱うか」を決めるための指示であり、コードの読みやすさ・保守性に直接関係することです。
相違点としては、変化の可否、寿命(生存期間)、そしてどこから触れることができるかの範囲が異なります。たとえばconstは一度決めた値を再び書き換えられなくする機能、staticは変数そのものの性質を長く保ち、場所(クラスやファイル)をまたいで共有できる性質を含みます。以下では「長く生きる変数」「変化を許さない定数」という二つのキーワードを中心に見ていきます。
この2つの概念を混同すると、バグの原因になります。例えば「constは絶対に変更されない」と誤解すると、初期化ミスやプログラムの流れの誤解を生み、意図しない挙動を引き起こすことがあります。逆にstaticを過剰に使いすぎると、プログラム全体を通じて状態が共有され、どこで値が変わったのか追跡が難しくなることがあります。したがって、設計段階で「どの変数を誰と共有し、いつ変えられるべきか」を明確に決め、それをコードのルールとして守ることが重要です。こうした基本を押さえると、constとstaticを適切に使い分けることが自然と身についていきます。
constの特性と注意点
ここではconstの性質をもう少し細かく見ていきます。constは「再代入を禁止する」だけではなく言語ごとに意味が少し変わります。C言語系ではconstは読み取り専用の記憶領域を作ることが多く、コンパイル時に定数として扱われる場合もありますが、必ずしも「値が固定」になるとは限りません。実際にはポインタを介して間接的に値を書き換えられる場面もありえます。JSではconstはブロックスコープの定数で、値を書き換えられないという意味ですが、オブジェクトや配列などの内部状態は変更できるという点がやや紛らわしい部分です。
つまり「constは絶対に変えられない」と考えると誤解の原因になります。実務では初期化後の再代入を避けるという意味で使うのが基本で、参照型の値を持つ場合は内部状態の変更が起こり得ることを頭に置くべきです。ここで大切なのは「どのレベルで不変を保証したいか」です。もしクラスの中で定数を宣言して、外部からの変更を一切断ちたいなら、constだけではなくアクセス制御(private, public, getterのみなど)や、オブジェクトのコピーを返す設計を組み合わせるとより安全になります。
また、コンパイル時定数として使う場合もあり、静的初期化の順序やリンク時の影響を考える必要があります。一般論としては、宣言する場所と対象がどの言語仕様に該当するかを意識して使うことが大切です。
staticの性質と使い分けのコツ
staticは語感として「その場にとどまる」という意味を持ち、変数の寿命や共有の範囲に強く影響します。C言語系では関数内にstaticを付けるとその変数は毎回初期化されず前回の値を保持します。つまり関数を呼ぶたびに新しい値が生まれるのではなく、プログラムの実行中ずっと同じ値を覚えておくのです。外部リンクを制御する場合にはstaticをファイル内のスコープに限定することで、他ファイルからは見えなくする内部リンクの役割を果たします。Javaでは同じクラスの中でstaticを使うと、すべてのインスタンスで共有される「クラスレベルの変数・メソッド」になります。ここで静的変数はオブジェクトを作るたびに新しく作られない点と、静的メソッドはオブジェクトを必要としない点を覚えておくと混乱を避けられます。
このようにstaticは「どこから触れられるか」と「誰と共有されるか」を決める機能です。設計上は「複数のインスタンス間で共有して良い情報」や「特定のクラスに紐づく共通の機能」を表現するのに適しています。
使い方としては、設定値を一箇所で管理する、統計情報を集計する、共通のユーティリティを提供する、などが代表的です。ただし、過剰にstaticを乱用するとテストが難しくなったり、プログラムの依存関係が複雑になるので、設計段階でのルールづくりが重要です。
実例で学ぶconstとstaticの組み合わせ
ここでは実用的な雰囲気で「クラス内に静的な定数を持つケース」と「静的変数で長寿命の値を持つケース」を比べて考えます。例えばゲームの設定を例にとると、MAX_LIVESは静的な定数としてクラスに置けば全てのプレイヤーで共通となり、途中で値が変わるべきではありません。一方で、プレイヤーごとに異なるスコアは静的変数にしてしまうと全プレイヤー間で値が共有されてしまい、意図しない挙動になります。
このように「何を共有するべきか」「何を不変にするべきか」を区別して設計することが大切です。表現の仕方としては、こうした特徴を使い分けるだけで、コードの可読性と保守性が大きく向上します。もし混乱したときは、プロジェクト内で「constは不変」「staticは共有」の基本ポリシーを紙に書いて貼っておくと迷わずに済みます。
最後に、現代のプログラミング言語ではconstとstaticの役割が言語ごとに微妙に異なる点を理解することが、正しい使い分けへの近道です。
放課後、友達と const と static の話で盛り上がった。僕は const の“不変”って言葉がカッコいいと思っていたけれど、実はオブジェクトの内部状態は変わり得る点に気づいた。それは「内側は不変でも外側から見える値は変えられる」という意味で、プログラムの挙動を読み解くときの重要なヒントになる。staticはみんなで共有する情報を作るときに便利だと理解した。ゲームの設定値のようなものは静的定数として一箇所に置くと、全員の動作を統一できる。逆にスコアのように個人ごとに違う情報は静的変数には向かない。こうした感覚で使い分けを意識すると、コードの読みやすさがぐんと上がる気がした。





















