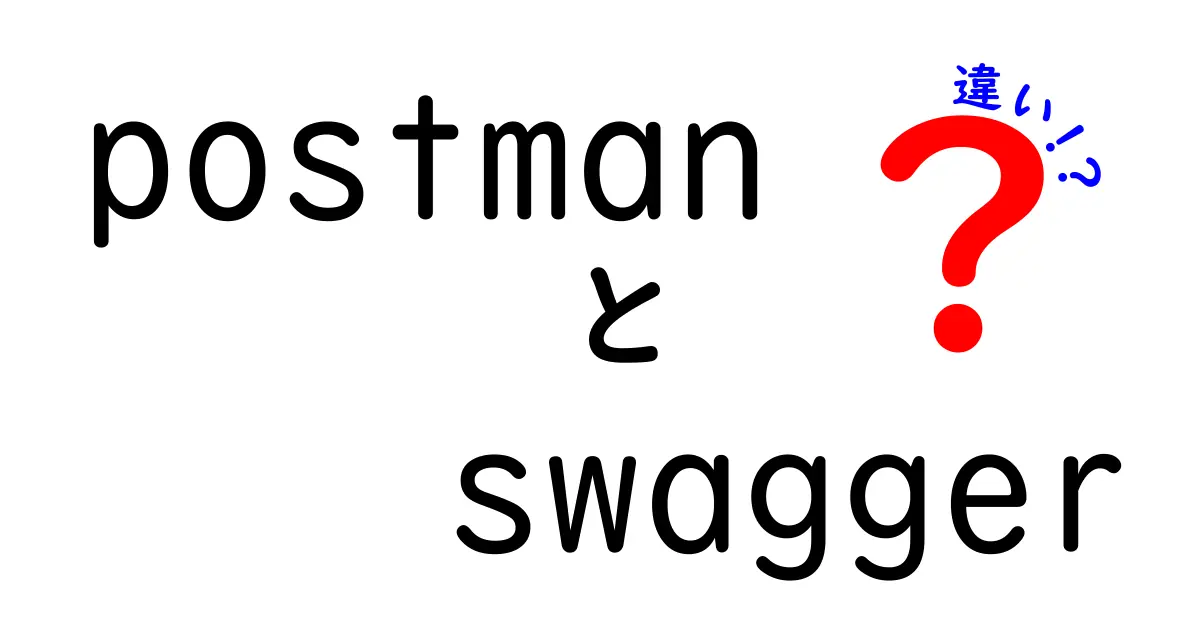

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
PostmanとSwaggerの違いを理解するための最初の一歩
このテーマはAPI開発を学ぶ人にとって避けて通れない話題です。PostmanとSwaggerはそれぞれ別の役割を担うツールであり、名前だけを見ると同じ作業をするように見えますが、現場では“何を作るか”と“どの段階で使うか”という観点が決定的な違いになります。
Postmanは実際のリクエストを走らせてレスポンスを確認するためのツールとして長く使われてきました。コレクションと呼ばれるリクエストの集合を作成し、環境変数を使って本番・開発・テストの切り替えをスムーズにします。テストケースを自動化したり、CI/CDと連携したりする機能も充実しています。
それに対してSwaggerはAPIの設計と仕様を中心に据えたツールです。OpenAPI仕様と呼ばれる形式でエンドポイントごとにリクエストの形、受け取るデータの型、レスポンスの構造、認証情報、エラーレスポンスなどを定義します。仕様書として誰が読んでも同じ理解になることを目指し、ドキュメント生成やモックサーバの提供も行います。ここでのキーワードはOpenAPI、仕様の標準化、設計の透明性です。これらを知っておくと、後の開発プロセスでどのツールをどの段階で使えばよいかが自然に見えてきます。
この2つのツールをどう使い分けるべきかの実務ガイド
実務の現場では設計とテストの段階で上手く分けて使うのが基本です。設計フェーズではOpenAPI仕様を作成し、全エンドポイントのリクエストとレスポンスの形を決めます。ここでSwagger UIを使って関係者に仕様を共有し、レビューを受けやすくします。
実装・テストフェーズではPostmanを使って各エンドポイントを実際に呼び出し、レスポンスを観察します。コレクションを作成し、環境設定を整え、テストケースを自動化して継続的に回せるようにします。モックサーバを立ててバックエンドの完成を待つ時間を短縮することも可能です。これらを結ぶポイントはOpenAPI仕様と実際のリクエストを一貫させることです。
そして連携のコツとして、OpenAPI仕様を更新したらPostmanのコレクションにも自動で反映される仕組みを作ると効率が上がります。以下は現場でよく使われる実践ケースの一部です。
実務ケースのまとめと実践のコツ
現場での運用では、両方のツールを合わせて使うのが最も効率的です。まず OpenAPI で基盤を固め、それをもとに Postman のコレクションを生成して実際の動作を検証します。変更があったら仕様とテストが同時に更新されるワークフローを作るとバグを見逃しにくくなります。短い例として、ある新機能を追加する場合を挙げると、仕様を更新→コレクションを更新→自動テストを実行の順で進められ、結果が可視化されることでチーム全体の理解が深まります。
OpenAPI の話題を深掘りする雑談風の小ネタです。友達とカフェで API の話をしていて、OpenAPI って結局何が良いのかと聞かれたとき、私はこう答えます。OpenAPI はエンドポイントの約束事を決めてチーム全体の理解を揃える“約束の言語”のようなものだと。YAML や JSON の記述で、どの人が何を渡すのか、どんなデータが返ってくるのかをはっきり示してくれる。これがあると、フロントエンドもバックエンドも同じ情報源を見ながら作業を進められます。Swagger UI はその仕様を読んで人が読めるドキュメントを作る道具で、OpenAPI という土台を活かして実装やテストの前に共通認識を作れるのが魅力。





















