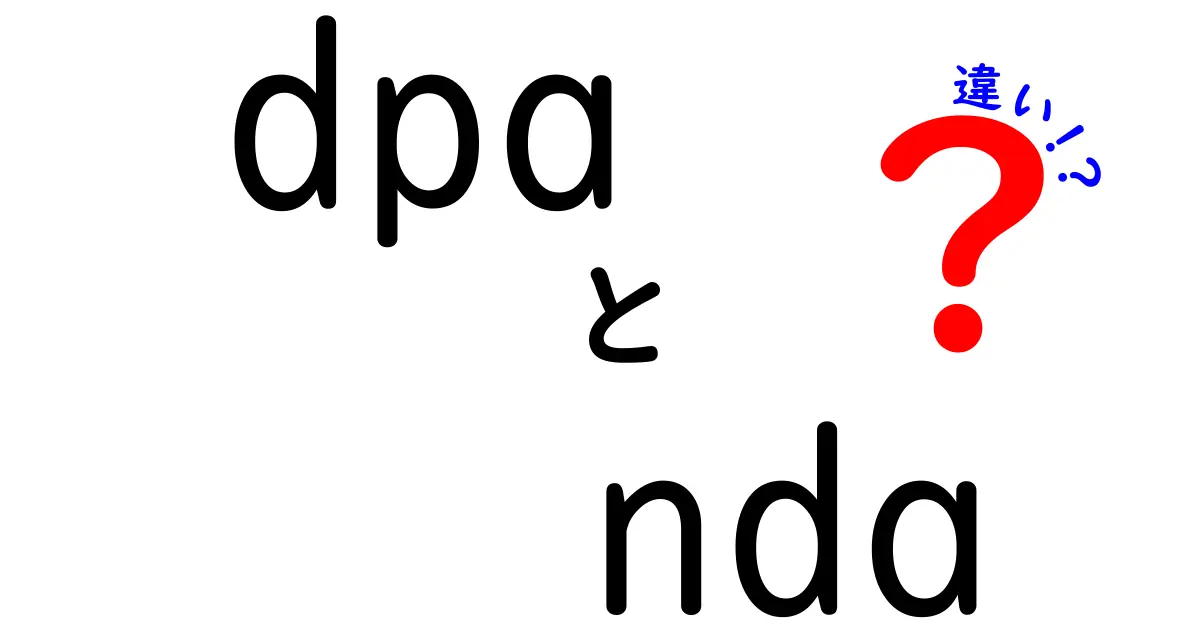

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
dpaとndaの基本的な違いとは
「dpa」と「nda」は日本語でそれぞれ「データ処理契約」と「秘密保持契約」という意味です。 どちらもビジネスの場で重要な契約ですが、目的と対象が大きく異なります。この章ではまずそれぞれの役割と対象を整理します。
NDAは情報の非開示を約束する契約で、情報を開示する側と受領する側の信頼を守る基本ルールです。機密情報の範囲、開示条件、開示後の取り扱い、違反時の救済措置などが主な項目です。
対してDPAは個人データの取り扱いに関する細かいルールを定める契約です。データ処理の目的、データの種類、処理の方法、データの保護水準、第三者への委託・転送の条件、データ主体の権利対応、監査の要件などを規定します。
このようにNDAは情報の「秘密」を守る枠組みであり、DPAはデータを「どう扱うか」を具体的に決める枠組みだと覚えておくと混乱を避けられます。
dpaとndaの使い分けと実務への影響
現場での使い分けは「目的と相手」によって決まります。 データの外部委託がある場合はDPAを必須と考えましょう。例えばクラウド事業者に個人データの処理を任せるケースでは、処理の範囲、期間、データ主体の権利対応、転送の条件、セキュリティ対策の水準などを事前に明記します。
一方、機密情報を広く扱う取引や技術情報の共有がある場合にはNDAが重要です。 開示情報の範囲と秘密保持の期間、情報漏洩時の救済手段などを具体的に規定します。
実務上は両方を組み合わせて契約することも多く、データ処理に関する条項と秘密保持条項を同じ契約の中で整合性を取る作業が求められます。
また、契約当事者は誰か、データの処理場所、データの転送先(国外含む)、従業員の教育・制限、侵害通知の手順、監査の頻度と範囲、違反時の違約金や救済措置など、細かな点まで詰めることが重要です。
もしGDPR等の国際規制が関係する場合は、DPAの条項を現地法の要求に合わせて適切に調整する必要があります。
NDAとDPAを別々に結ぶ場合でも、相手方がデータをどう扱うかに関して齟齬が生じやすいため、両契約の条項の整合性を事前に確認しましょう。
ねえ、NDAとDPAの違いって、難しく感じるよね。実は日常の会議の中でこの二つを混同しがちだけど、実務上は“秘密情報を守るための契約”と“個人データの取り扱いを規定する契約”という大枠の役割分担から考えると、見えてくる点がたくさんあるんだ。あるプロジェクトの話を例に挙げると、初めはNDAだけで済ませようとしたものの、実際には個人データの取り扱いも絡んでくる場面が出てきてDPAが必要になった。二つを別々に用意するより、データの性質と情報の性質を整理して、表のように整理する方がミスが減る。結局、データの種類・扱う人・目的・保存期間を一枚の表に落とす癖をつけると、後々の契約更新や監査にも強くなる。こうした実務の工夫が、難解さを乗り越えるコツだと思う。





















