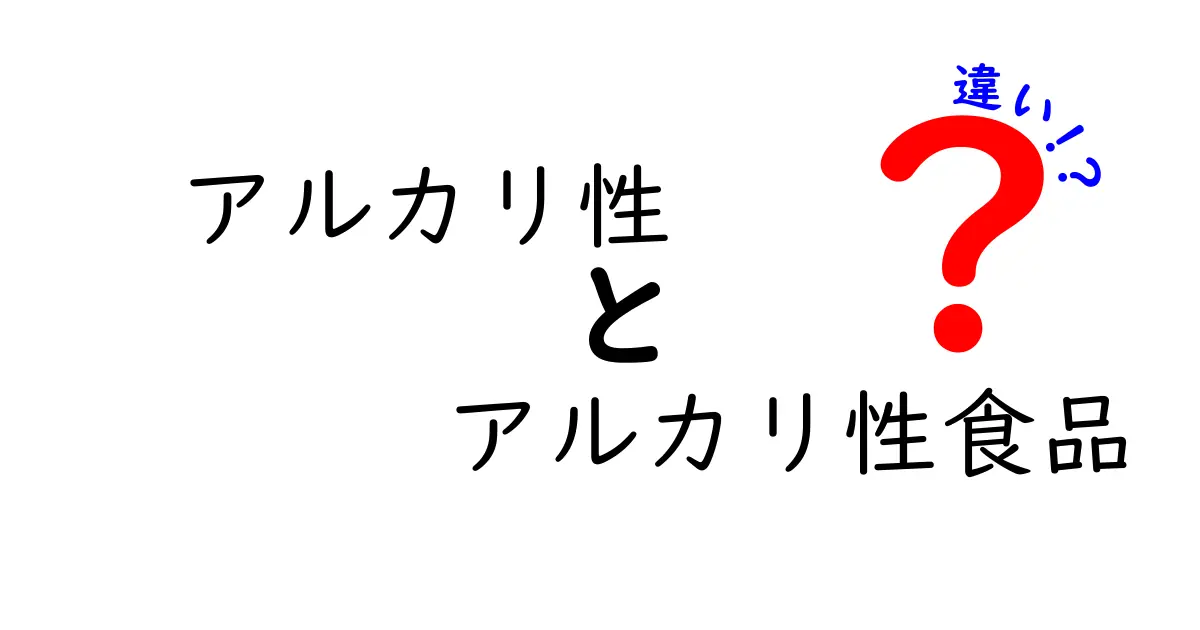

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
アルカリ性とは何か?
私たちが日々の生活でよく聞くアルカリ性とは、一体何を指しているのでしょうか?アルカリ性は、物質の性質や状態を表す言葉で、水溶液のpH値が7より大きい状態を意味します。
pHとは水溶液の酸性・アルカリ性の強さを示す数値のことで、0から14までの値をとります。pH7は中性で、7未満は酸性、7より大きい数値はアルカリ性です。例えば、レモン汁などは酸性でpHが低く、石けん水や重曹水はアルカリ性でpHが高いです。
このアルカリ性という言葉は、化学的な性質を示す用語であり、具体的に体や食べ物にどのように関係しているのかを知ることで、健康や食生活に役立ちます。
では、次にアルカリ性食品とは何か、どのようにアルカリ性と違うのかを見てみましょう。
アルカリ性食品とは何か?
アルカリ性食品とは、体内に取り入れた時、体液をアルカリ性に保つのを助ける食品のことです。つまり、これらの食品を食べると体の中のpHバランスが酸性ではなくアルカリ性寄りになることを目指しています。
一般的には、野菜や果物、海藻などがアルカリ性食品に分類されます。例えば、ほうれん草、かぼちゃ、りんご、バナナなどがその代表です。これに対して、肉類や加工食品、砂糖は酸性食品と言われています。
アルカリ性食品をたくさん摂ると、体の中で酸性物質を中和し、健康的な状態を保つのに役立つと言われています。実際には体内のpHは厳密に調節されていますが、毎日の食事でアルカリ性食品を意識することは健康維持に効果が期待されているのです。
簡単に言えば、アルカリ性はpHの性質そのものであり、アルカリ性食品はその性質を体に取り入れる食品という違いがあります。
アルカリ性とアルカリ性食品の違いまとめ表
| 項目 | アルカリ性 | アルカリ性食品 |
|---|---|---|
| 意味 | 水溶液のpHが7より大きい状態 | 体内のpHをアルカリ性に保つのを助ける食品 |
| 使われる場面 | 化学的性質の説明・体液のバランス | 健康・食生活の文脈 |
| 具体例 | 石けん水、重曹水など | 野菜、果物、海藻など |
| 目的 | 物質の性質を表す | 健康な体内環境を保つことを目指す |
「アルカリ性食品」と聞くと、単に『アルカリ性の食べ物』と思いがちですが実は少し違います。
アルカリ性食品とは、食べた後に体内で代謝され、尿や血液などの体液の酸性度を下げ、アルカリ性に近づける食品のことです。だから、直接食べ物がアルカリ性というわけではなく、体の中でどう働くかがポイントなんです。
例えばレモンは酸っぱいですが、体内ではアルカリ性食品に分類されることもあります。これは成分が代謝されるとアルカリ性の物質になるからなんですね。こうした話は食事や健康の話題でよく誤解されやすいですが、知っておくと食事の選び方が変わるかもしれません。
前の記事: « 定期検査と計量証明検査の違いとは?わかりやすく解説!
次の記事: 定期検査と登録点検の違いとは?わかりやすく徹底解説! »





















