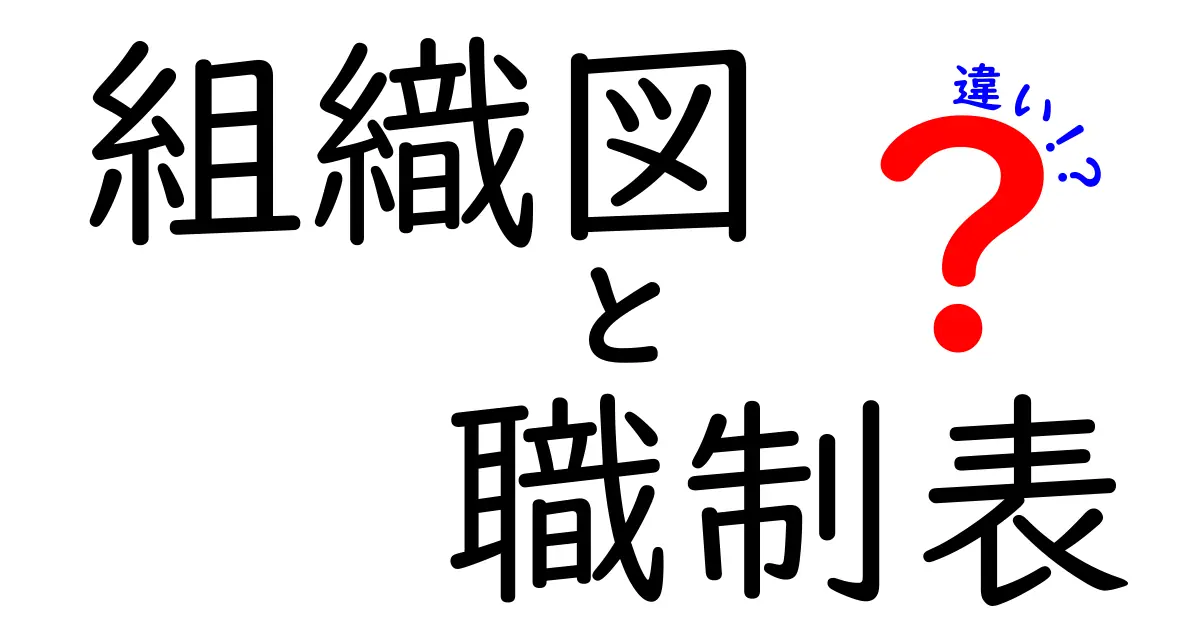

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
組織図と職制表の違いを徹底解説:現場で使い分けるためのポイント
ここでは「組織図」と「職制表」の基本的な違いを、中学生にも分かる言葉で丁寧に解説します。
組織図は、会社や団体の中で誰が誰に指示を出すのか、誰が誰に報告するのかといった権限と関係性を視覚的に示す図です。箱と線で階層を作り、上司と部下の関係をひと目で把握できるよう設計されます。部門名や役職名、人数などが表示され、会議の説明資料や外部向けの説明資料などで活用されます。
ただし組織図だけでは日々の業務分担を詳しく知ることは難しく、どの人が具体的に何を任されているかは別の資料で補足するのが一般的です。そこで職制表が役立ちます。
職制表は各ポジションの業務内容、責任、権限、所属部門などを整理した表です。職制表は人と業務の対応関係を明確にし、人事配置や評価設計、教育計画などに強く関与します。
組織図と職制表は相互補完の関係にあり、現場ではこの二つを組み合わせて使うことが効果的です。組織改編時には両方を同時に更新すると混乱を防げます。
結局のところ、組織図は組織の“関係性の地図”として、職制表は業務の“辞書”として、組織を動かす基盤になります。
この理解を基に、学校の部活動や部門などでも活用の工夫をしていくと、役割の取り違えを減らし、協力の輪を広げられます。
組織図とは何か?
組織図は、組織のトップから下位の役職まで、権限と責任の流れを棒と箱の連なりで示す図です。箱には部門名や役職名が入り、線は指揮・報告・承認のルートを描きます。大きく分けて「階層型」と「マトリクス型」があり、階層型は典型的な縦のつながりを強調します。一方、マトリクス型は機能とプロジェクトの両方の関係性を同時に表し、複数の上長を持つこともあります。組織図の良さは、誰が意思決定の最終責任者なのかを直感的に把握できる点と、組織の規模感や部門間の距離感を理解しやすい点にあります。ただし、組織図だけでは日常の業務分担や個々の責任の細かな差異は見えづらい、補足資料とセットで使うのが効果的です。
職制表とは何か?
職制表は、各ポジションの役割や担当業務、権限、直属部門などを一覧にした表形式の資料です。横軸に部門名、縦軸に役職名が並ぶ場合もあれば、1つの表に“職位・仕事内容・責任範囲・権限限界・補足情報”を列として並べるケースもあります。職制表の強みは、誰が何を担当するのかを明確に示せる点です。採用時の人事配置、新人教育の設計、業務改善の際の責任の割り振り、評価基準の設定など、実務のあらゆる場面で土台となります。
ただし、職制表はあくまで業務と権限の一覧であり、組織の“人間関係”や“報告ライン”を示すものではないため、組み合わせて使うのがベストです。
使い分けの実務ポイント
日常業務の中で組織図と職制表を使い分けるコツは、目的を先に決めることです。報告ラインや意思決定の流れを伝えたいときは組織図を用い、具体的な業務の分担や責任範囲を決めたいときは職制表を用います。更新の頻度も目的で変えます。組織改編があれば両方を見直し、変化点を全員に周知します。新人教育では、まず組織図を一緒に眺めて“ここに誰がいるのか”を理解させたうえで、職制表を使って自分の担当業務を具体的に確認させると良いでしょう。実務ではこの二つを組み合わせて、横断的なプロジェクト運営にも対応できるようにします。
ねえ、組織図ってただの箱と線の集まりだと思ってたけど、実は“視点の道具箱”なんだ。上司が誰か、誰が誰の上司かが矢印で分かると、困る人が誰か急に浮かび上がる。僕が入社して最初に見た時、部屋の人の動きが全部頭に浮かんだ気がした。組織図は変化する生き物だから、改編の度に書き換えることが大事。新人教育では、まず組織図を一緒に眺めて“ここに誰がいるのか”を想像させ、それから各人の業務や責任を職制表で詰める。





















