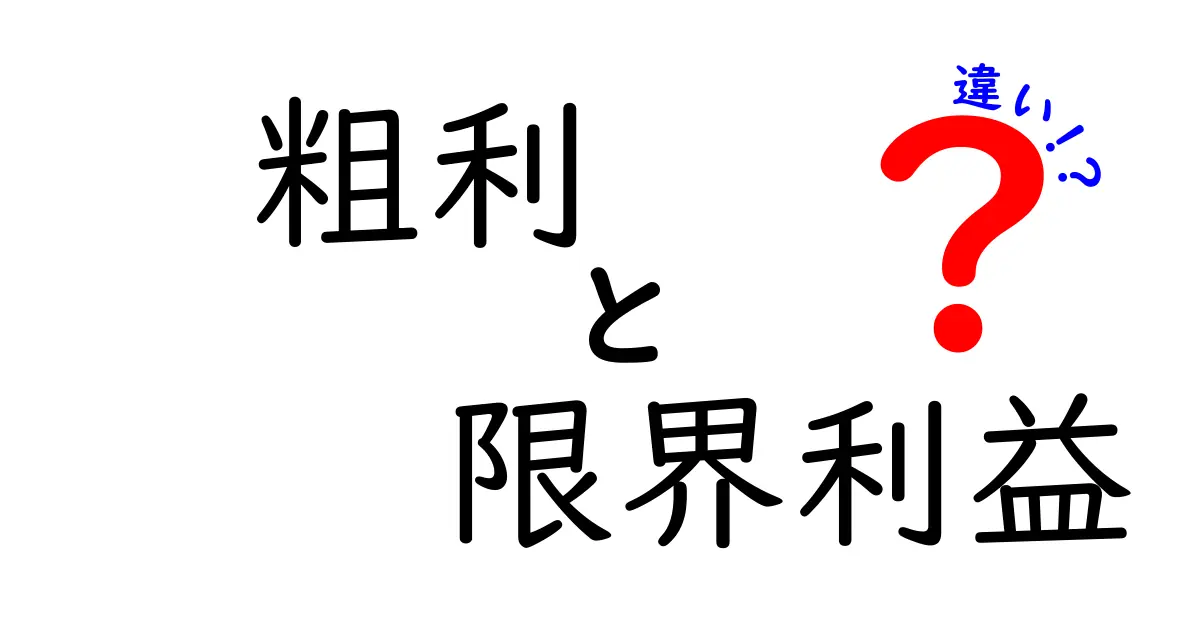

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
粗利と限界利益の違いを理解するための基礎
まずは用語の意味をしっかり押さえましょう。粗利とは、売上高から売上原価を差し引いた金額のことです。売上原価には仕入れ原価や製造原価のような、直接的に商品を作るためにかかった費用が含まれますが、販管費や広告費、店舗の家賃といった固定的な費用は含まれません。この点が重要で、粗利は商品やサービスの「作る力」を起点として、どれだけの金額が現場で自由に使えるかを示す指標になります。ここからがビジネスの肝です。もし原材料の値段が上がれば、粗利は下がりますし、逆に売上を伸ばせば粗利自体は増えます。しかし、粗利が高いだけでは会社全体の健全性は保証されません。なぜなら、消費者に対する販売費用や一般管理費、家賃や人件費などの固定費が別に控えているからです。したがって、粗利を評価するときは「総合的な収益力」を見る軸として、他の費用との関係性をセットで考えることが大切です。
一方、限界利益は売上高から変動費を差し引いた額です。変動費には材料費、直接労務費、販売手数料、梱包費など、売上の量に応じて増減する費用が含まれます。固定費は含まれません。したがって、限界利益は「売上を増やしたときにどれくらい追加の利益が生まれるか」を表す貢献度の考え方です。ここが粗利と大きく異なる点で、実務ではこの差を使って価格戦略や製品ラインの見直しを考えます。たとえば、ある製品の変動費が100円、販売価格が500円、月間の売上が1000個であれば、限界利益は500円×1000個=50万円となります。この値が高いほど、固定費をカバーした後の利益余地が大きく、経営判断の材料として有効です。
日常の活用と実務の考え方
この二つの指標を実務でどう使い分けるかを、実例とともに見ていきます。まず、製品Aの売上が1,000円、変動費が300円、固定費が200円の場合を想定します。粗利は売上高からCOGSを差し引くので、もしCOGSが600円なら粗利は400円になります。限界利益は売上高から変動費を差し引くので、限界利益は700円です。つまり、この商品を追加で1,000個売ったとき、固定費200円を除けば追加で700,000円が貢献利益として残ります。ここが「価格をどう設定するか」「量をどう調整するか」という意思決定の肝です。実務で大切なのは、売上の増減が変動費と固定費のどちらに影響を与えるかを把握することです。さらに、複数の製品を同時に見る「製品別の限界利益と寄与利益率」を比較することが有効です。
また、戦略的な判断としては、特別価格で受注を取る際の評価にも両指標を使います。例えば、顧客から特別価格の依頼が来た場合、追加の売上がどれだけ固定費をカバーし、企業の利益を押し上げられるかを考えるのが基本です。変動費が主なコストになる場合は、限界利益の視点が特に重要です。COGSに固定費が大きく含まれている場合、この点に注意が必要です。こうした判断を日常の会計処理とセットで行うことで、過大な在庫リスクを避けられ、健全なキャッシュフローを保つことができます。
友達とカフェで話していたとき、粗利って耳にするけど正直よく分からないよね、という話題になりました。私はこう答えました。粗利は“売上から原価を引いた額”と覚えるといいんだよ、と。だけどここで勘違いしがちなのは、粗利と純利益が混同されやすい点です。粗利は商品を作る力の大きさを示す指標で、固定費は含みません。一方、純粋な最終利益を知りたいときは、ここから販管費や税金、減価償却などを引く必要があります。つまり、粗利は「現場で使えるお金のイメージ」を作る材料であり、限界利益は「売上を伸ばすとどれだけ利益が増えるか」いう貢献度を示します。日常生活の中で、どの価格設定が最も効率的かを考えるとき、この二つの視点を同時に持つと、無駄なコスト削減と売上の両方をちゃんと両立させられるんですよ。
前の記事: « 返却・返品・違いを徹底解説!日常で使い分けるコツと実例
次の記事: 組織図と職制表の違いを徹底解説!現場で使い分けるためのポイント »





















