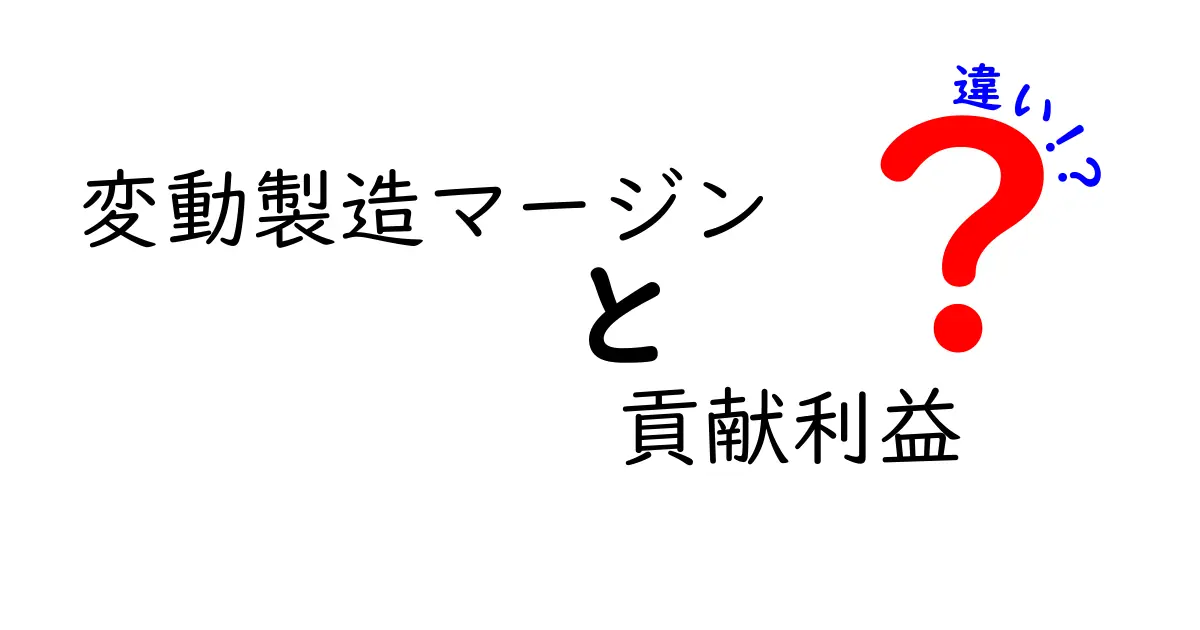

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
変動製造マージンと貢献利益の基本を押さえる
このセクションでは、まず用語の定義と役割を丁寧に整理します。変動製造マージンは、製造活動における変動費の影響を強く受ける利益の指標です。生産量が増えると材料費や労務費が増えることがありますが、同時に売上も増えます。ここで覚えるべき点は「マージンを生み出すのはどの費用か」という観点です。変動費を正しく分解しておくと、価格設定、製造規模の最適化、在庫の回転速度の改善といった意思決定がしやすくなります。変動製造マージンは、単純な利益の大きさだけでなく、量に対する感度(生産量が1単位変わるとマージンがどう動くか)を示します。これを使えば、季節変動や需要の回復期における適正な生産方針を立てやすくなります。対して貢献利益は、個々の製品が全体の利益にどれだけ寄与しているかを示す指標です。複数の製品を扱う企業では、売上が多いだけではなく、どの製品が固定費を分担する力を持っているかを理解することが重要です。これらを混同せず、役割を分けて理解することが、現場の意思決定力を高める第一歩なのです。
変動製造マージンと貢献利益の違いを見極める具体的なポイント
このセクションでは、違いを「使う場面」と「求められる情報」という観点で分解して説明します。まず変動製造マージンは、製造の現場で変動費がどの程度生産量に連動するかを評価します。価格を下げて販売を増やす戦略を取るとき、変動費がどう動くかを知ることは不可欠です。工場のラインを変える前に、1日あたりの可変費の増減が利益に与える影響を測定するのに最適です。次に貢献利益は、製品別の寄与度を測る尺度です。複数の製品を比べるとき、どの製品が固定費を効率よく分担しているか、どの製品群を中心に強化すべきかが見えてきます。実務では、売上構成の変化に対する感度分析を合わせて行うと効果が高まります。例えば、新製品ラインを追加する場合、貢献利益の高い製品と低い製品の組み合わせを検討することで、固定費の最適化にもつながります。最後に、意思決定の前提をそろえるために、両者の計算基礎を同じ仮定で揃えることが極めて大切です。
結論として、変動製造マージンは「生産プロセスの変動リスクを測る指標」、貢献利益は「製品ポートフォリオの収益貢献度を測る指標」であり、これらを対比することで、ユーザーはより正確な経営判断を下せます。
具体的な計算例で理解を深める
では、実際の数値を使ってイメージを固めます。仮に、製品Bの販売価格が1200円、材料費が600円、直接労務費が150円、その他の変動費が50円、これらを合計すると変動費は800円になります。1単位あたりの変動製造マージンは1200-800=400円です。生産量が1500単位の場合、総変動マージンは400×1500=600,000円。貢献利益は販売価格から変動費を引いた1200-800=400円の同じ計算ですが、ここでの貢献利益は変動費以外の要素が固定費の分担を考慮した場合の金額になります。固定費が月額200,000円と仮定すると、月間の貢献利益は400円×1500=600,000円で、固定費を賄う力を示します。
このように貢献利益は、製品ラインの構成を見直す際の重要な指標となり、固定費を効率的に分担して黒字化を目指すための判断材料になります。
部活の文化祭準備の話をひとつ。売り物を2つ出すとき、Aは材料費が100円、Bは材料費が300円とします。売上がそれぞれ500円と700円なら、貢献利益はA=400円、B=400円。結局、同じ数字でも寄与の仕方や販促費の分担で結果が変わるのが分かります。つまり、貢献利益は“どの品が固定費を効率よく分担して黒字化に貢献するか”を教えてくれる指標なのです。





















