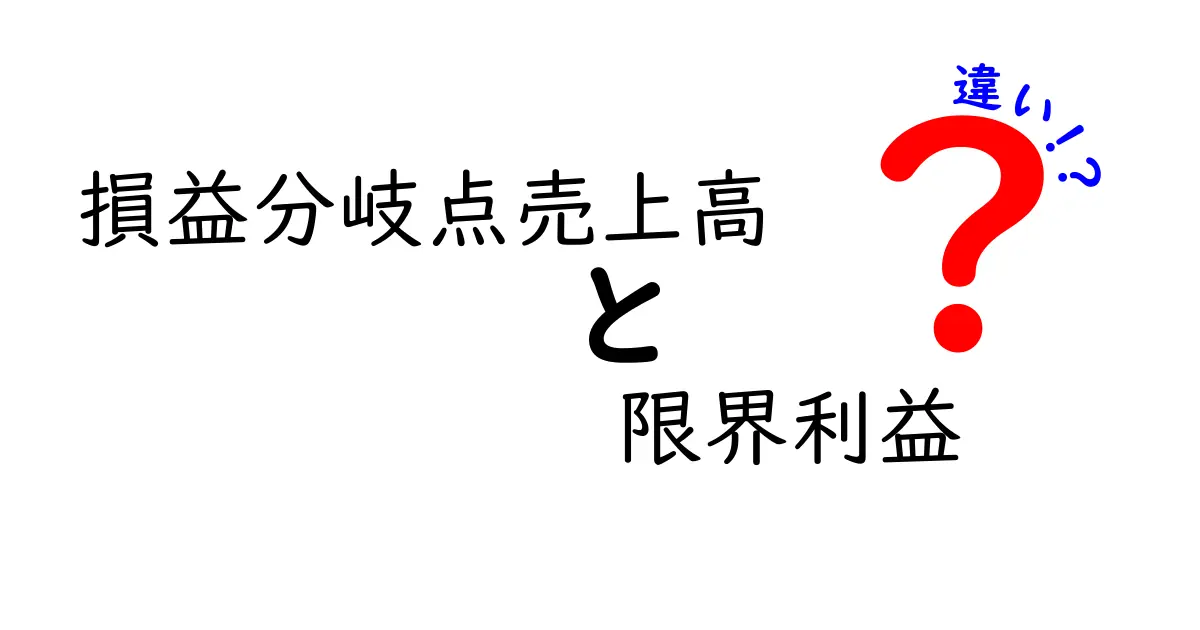

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
損益分岐点売上高と限界利益の違いを理解するための基礎と実務への橋渡し
このブログでは多くの人が混同しがちな用語 損益分岐点売上高 と 限界利益 の意味を、難しくならないように丁寧に解説します。まず大事なのは、これらはどちらも売上を軸にした考え方だという点です。企業が黒字になるラインを探したり、どのくらいの売上があれば安定して利益が出るのかを判断したりする際に役立つ道具です。
損益分岐点売上高 は「利益がちょうど0になる売上の金額」を指します。つまり赤字にも黒字にもならない境界線の売上です。一方、限界利益 は売上高から変動費を引いた額で、製品を追加で1つ販売したときにどれだけ貢献できるかを示す“貢献度”のような値です。これらの言葉の違いを理解すると、価格設定やコスト管理、事業の選択をより賢く進められるようになります。
ここからは、用語の意味を分かりやすく具体例とともに詳しく見ていきます。読み進めるほど、実務での使い方が見えてくるはずです。
損益分岐点売上高とは何か
損益分岐点売上高 とは、利益が正にも負にもならない「ちょうど黒字と赤字の境界線」となる売上高のことです。つまりこの売上高を超えれば企業は利益を生み出し、下回れば赤字になります。計算の基本は固定費と限界利益の関係です。固定費は生産量に関係なく発生する費用で、限界利益は1単位あたりの貢献度です。日常の例えで言えば、カフェを開くと想像すると分かりやすいです。家賃や人件費のような固定費があり、コーヒー(関連記事:アマゾンの【コーヒー】のセール情報まとめ!【毎日更新中】)1杯の販売によって得られる貢献分(単価から変動費を引いた額)が存在します。この貢献分で固定費をカバーできる数量を求め、それに売上高をかけると 損益分岐点売上高 が得られます。具体的な計算の結果は、事業のスケジュールや販促戦略を決める際の「目標値」になります。現場では季節変動や在庫の影響もありますが、基礎となる考え方を知っているだけで判断が格段にしやすくなります。以上を踏まえると、直感だけでなく、数字を通じた意思決定が身につくようになります。
限界利益とは何か
限界利益 とは、売上高から変動費を引いた額のことです。変動費は生産量や販売量に比例して増減する費用で、例えば材料費や直接労務費などがこれにあたります。
「限界利益」は、製品を追加で1単位販売したときに手元にどれだけお金が残るかを示す指標であり、総額では総売上から総変動費を引いた金額になります。さらに、単位あたりの限界利益は「販売価格 − 変動費」として計算され、製品ごとの収益性を比較する際に有効です。現場では、限界利益を高めるための価格設定やコスト削減の工夫を行います。限界利益が高いほど、固定費をカバーして黒字化に近づく力が強くなります。こうした考え方を知っておくと、複数の製品を持つ企業で「どの製品を優先して増産するべきか」を判断する材料になります。
実務での違いの活かし方と日常の例
実務では、損益分岐点売上高 と 限界利益 を組み合わせて意思決定を行います。まず固定費を正確に把握し、次に価格戦略やコスト構造をどう変えれば黒字化のラインを早く越えられるかを考えます。具体的なステップは次のとおりです。
1) 固定費を洗い出す。家賃・人件費・保険料など、売上の増減に関わらず発生する費用を全て挙げます。
2) 変動費と販売価格を確認する。製品ごとに変動費を集計し、単位あたりの限界利益を計算します。
3) 損益分岐点売上高を計算する。固定費 ÷ 単位あたりの限界利益 などの式を用います。
4) 価格戦略と販促の計画を立てる。売上目標を設定し、目標達成に向けての施策を組みます。これらを実務で活用する際は、季節性や在庫、競合の動向も加味して調整します。
例えば、固定費が100万円、単価が1,000円、変動費が600円のとき、限界利益は400円、損益分岐点売上高は固定費 ÷ 限界利益/単価の関係から約2500単位、売上高は約2,500,000円となります。こうした計算をベースに、何を削るか、何を増やすかを検討します。
ある日の放課後、友だちと部活の話をしていたときのこと。彼は新しいお店の企画を考えていて、何を売れば黒字にできるかを悩んでいました。私は「損益分岐点売上高」と「限界利益」という二つの考え方をざっくり教えることにしました。まず損益分岐点売上高は、利益がちょうど0になる売上のライン。つまりここを超えると初めて利益が出るという“境界線”です。次に限界利益は、売上から変動費を引いた額。単位あたりの利益を見れば、どの商品を増やすと会社が早く黒字化するかが分かります。彼は「この二つを合わせれば、キャンペーンの効果を測れるね」と笑顔に。会話の途中、私は彼に簡単な計算表とグラフの作り方を伝えました。実際の場面でも、固定費の総額と製品ごとの変動費を整理しておくと、価格決定や仕入れの判断がぐんと楽になります。小さな疑問からでも、数字を使って考える力を身につけると、将来のビジネスにも必ず役立ちます。





















