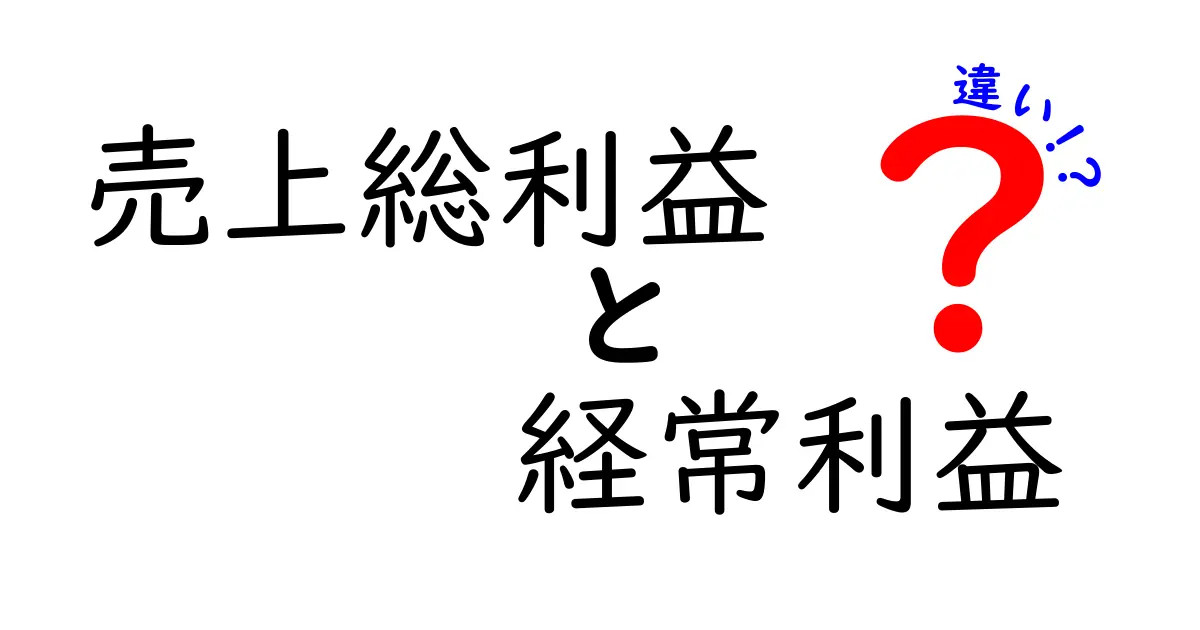

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
売上総利益と経常利益の違いを徹底解説:中学生にもわかる実務ガイド
売上総利益と経常利益は、企業の財務を理解するうえで核となる指標ですが、表面的な数字だけを見ていると本当に大切な情報を見逃してしまいます。売上総利益は商品やサービスを売って得た総収入から、その売上を生み出す直にかかった費用、主に原価を引いたものです。ここが「原価管理」の土台になります。一方で経常利益は、日常的な事業活動の成果を示す指標で、営業利益に営業外の収益と費用を加減して算出します。つまり、営業の動きとそれ以外の“普通の”収支を合わせて、企業がどれくらい安定して稼いでいるかを示す数字です。こうした違いを理解することは、投資や就職活動、ニュース解説など、さまざまな場面で役立ちます。この記事では、売上総利益と経常利益の基本を押さえ、実務での使い方とよくある誤解について、図解と具体例を交えながら中学生にもわかるように丁寧に解説します。
この解説で覚えておくべき点は、売上総利益が原価構造の強さを、経常利益が日常的な稼ぐ力を示す点です。原価は製造や仕入れの効率を、経常利益は財務の安定性を左右します。
売上総利益とは何か?その定義と計算の基本
売上総利益は企業が商品やサービスを販売して得た総売上高から、それらの売上を生み出す直にかかった費用、つまり売上原価を差し引いた値です。式としては売上総利益 = 売上高 - 売上原価となります。ここで大事なのは売上原価に含まれるのが直接材料費、直接人件費、製造間接費など、商品を作る過程で直接反映される費用である点です。例えば、文房具のメーカーA社が一冊1000円で売っており、原価が600円かかった場合、売上総利益は400円になります。この400円は「商品を作るのに直接かかった費用を引いた後の、売上の基本的な利益の部分」を示します。売上総利益は企業の「製品やサービスそのものの原価構造がどれくらい安いか」を判断する基準になり、原価管理の改善が利益を押し上げる鍵になることが多いです。
この指標の理解で最も大切な点は、売上高が同じでも原価の内訳が異なると売上総利益が大きく変わるという点です。原価を抑える努力が直接的に売上総利益の改善につながり、結果として企業の競争力や安定性へ影響します。
経常利益とは何か?営業外項目を含む考え方
経常利益は日常的な事業活動の結果として生じる利益を表す指標で、営業利益に営業外収益を加え、営業外費用を差し引いたものです。式としては経常利益 = 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 です。営業利益は本業の販売活動の利益であり、営業外収益には取引外の収益、例えば受取利息、受取配当金、為替差益などが入り、営業外費用には支払利息、為替差損、手数料などが含まれます。これらを組み合わせて経常利益が決まります。実務では、経常利益は「日常の取引から安定して生まれる利益」の指標として重視され、企業の財務健全性や利回りの評価、複数年度の比較にも使われます。例えば、営業利益が200、営業外収益が50、営業外費用が20の場合、経常利益は230になります。
この指標は、急な特別損益や一時的な事象を除いた“通常の稼ぐ力”を示す役割を持ちます。よって、ニュースで「経常利益が増えた/減った」というときには、まずこの基本構造を押さえることが大切です。
売上総利益と経常利益の違いを理解するには?実務での活用と注意点
ここでは両者の違いを具体的な場面で捉え、使い分けのコツを紹介します。
まず最初の違いは対象とする費用と収益の範囲です。売上総利益は「売上高から売上原価を引いた値」であり、製品の原価構造のみを反映します。一方、経常利益は「本業の利益に、日常的な収益と費用を加味した値」で、金融収支や為替差損益などの影響を受けます。
次に、企業の意思決定への影響が異なります。売上総利益は価格戦略や原価削減の効果を直接示し、製造部門の改善点を探る手掛かりになります。経常利益は事業全体の安定性や資本コストとの比較、財務戦略の評価に使われます。
さらに、投資家の見方も異なります。投資家は売上総利益を原価管理の健全性の指標として見ることが多く、経常利益は企業の通常の稼ぐ力を示す指標として重要視します。最後に実務での注意点として、特別損益(臨時の利益や損失)や税効果など、一時的な要因により両指標が動くことがある点を理解しておくことが大切です。
以下の表は両者の違いを要約したものです。
表をご覧ください。項目 売上総利益 経常利益 対象 売上高と売上原価 営業利益に営業外収益を含む 用途 原価管理の評価 通常の稼ぐ力の評価・財務の健全性 影響要因 原価構造 営業外要因・日常の収支
今日は友達とカフェで会計の話をしていて、売上総利益と経常利益の区別がどうして大切かを深く掘り下げてみた。売上総利益は商品を作るコストの効率を映す鏡のようなもので、原価が安ければ同じ売上でも利益は大きくなる。一方、経常利益は日常的な取引から生まれる安定した稼ぐ力を示す指標で、特別なイベントの影響を受けにくい“普通の利益”を表す。これを知るとニュースを読んだときに「本当に影響しているのはどの部分か」が見えるようになる。例えばスマホの部品を輸入している会社が為替の変動で経常利益に影響を受ける場面を想像してみよう。為替差益が増えれば経常利益は上がるし、逆に差損が出れば下がる。そんなイメージで考えると、原価の管理と為替リスクの管理が別々の力として働いていることが分かる。僕らが教科書だけでなく身の回りの例で考えると、難しい会計用語も身近な事柄として理解できる。さらに、キャッシュフローや投資判断をする場面でも、経常利益の安定性は大事な判断材料になる。要は、数字はただの記号ではなく、企業の日々の工夫や努力の結果を映す鏡だと感じるようになった。
次の記事: 売上と粗利の違いを徹底解説 初心者でも納得の基本ガイド »





















