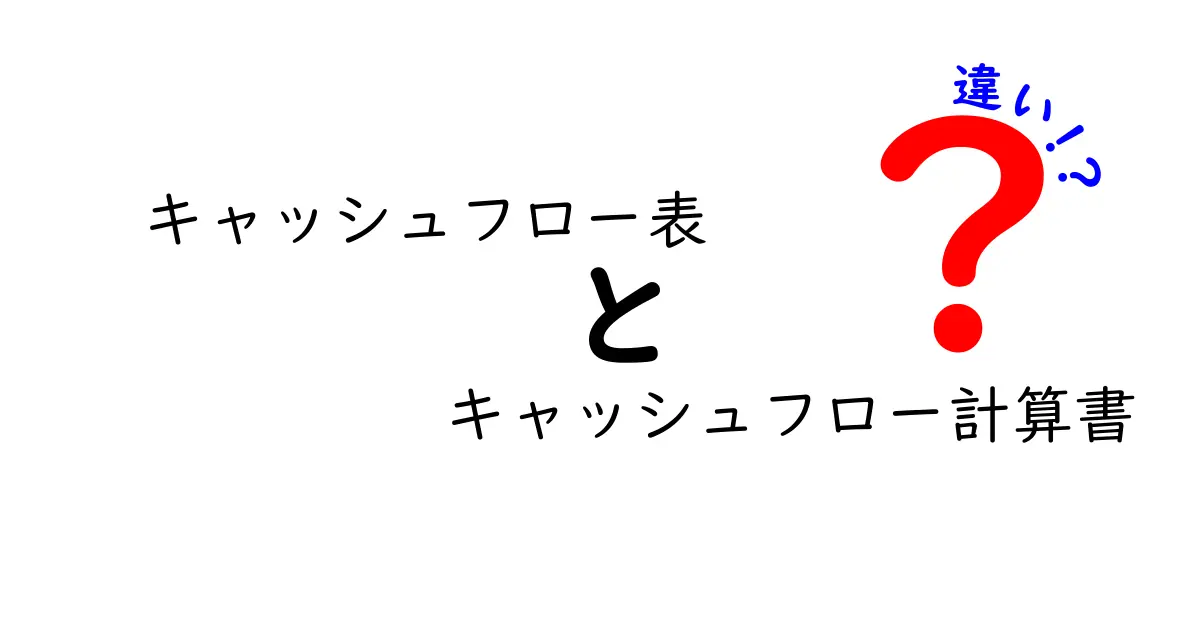

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
キャッシュフロー表とキャッシュフロー計算書の違いを知ろう
財務を学ぶときに出てくる「キャッシュフロー計算書」と「キャッシュフロー表」。似た名前ですが、それぞれの目的・使われ方・見せ方には大きな違いがあります。最初に結論を伝えると、キャッシュフロー計算書は正式な財務諸表の一つで現金の流れを三つの活動に分けて示す文書です。一方、キャッシュフロー表は学習用・社内用として現金の動きを表形式で整理する私用ツール的なものです。どちらも現金の動きを追う点は同じですが、読み方・用途・閲覧する相手が異なります。
現金は企業の生命線です。利益が出ていても手元資金が不足していれば、日々の支払いが滞ってしまい、事業の継続が難しくなります。だから「現金の流れを正しく理解する」ことが非常に大切です。キャッシュフロー計算書は外部の投資家や金融機関に対して「現金の動き」と「資金の健全さ」を示す正式な手段。対してキャッシュフロー表は社内教育や資金繰りの計画を立てるための道具として使われることが多いのです。
この違いを押さえておくと、財務資料の読み方がぐっと分かりやすくなります。
キャッシュフロー計算書とは何か
まずキャッシュフロー計算書の本質から見ていきましょう。これは法的・会計的に認められた公式の財務諸表の一部で、期間中の現金収入と現金支出を「営業活動」「投資活動」「財務活動」の三つの区分で整理します。営業活動には本業の現金の動き、投資活動には設備投資や長期資産の取得・売却、財務活動には借入金の返済や株主への配当・新株発行などが含まれます。
この三区分は、会社がどのくらい現金を生み出しているのか、どの分野が資金を使っているのかを示し、経営判断の材料になります。現金の流れを直截に示す指標として、利益と現金のずれを理解するのにも役立ちます。
キャッシュフロー表とは何か(用途と特徴)
次にキャッシュフロー表の性質と使い方です。こちらは公式な財務諸表ではなく、現金の流れを「いつ・いくら動いたのか」を把握しやすくする、教育・実務の補助ツールとして作られることが多いです。月次や週次で分類して表示するので、現金の不足や過剰が起きるタイミングをつかみやすく、資金繰りの練習にも適しています。
企業の短期的な資金計画を立てるときには特に有効で、現金の見える化が組織の判断を速くします。
違いを実務でどう使うか
違いを理解したうえで、実務の場でどう使い分けるかを見ていきましょう。キャッシュフロー計算書は法定の財務情報として外部に公開されることが多く、株主・金融機関への説明資料として必須になる場面が多いです。現金がどの区分で増減したかを把握することで、企業の資金力・安定性を伝えられます。これに対してキャッシュフロー表は内部の意思決定ツールとして力を発揮します。現金の動きを細かく整理することで、いつ資金が不足するかを事前に予測し、緊急対応策を考えるのに役立ちます。
要するに、公式な報告と内部の計画、この2つが互いに補完し合う関係です。
読み解くコツと実践のポイント
最初のコツは、現金の「総入り」と「総出」を比較して純キャッシュフローを出すことです。次に、営業活動の現金が黒字か赤字かをチェックすると、日常のビジネスの元気度が分かります。投資活動は将来の成長投資か、資産売却による一時的な現金の動きかを見分ける目を養います。最後に、財務活動の項目で資金調達の方向を読み取り、資金繰りを安定させるための計画を作るのが実践のゴールです。現金ベースでの判断力を高めることが、企業を長く支える力になります。
友だちと放課後にお金の話をしている場面を想像してください。机の上にはノートとスマホ、そしてささやかな財布。ここで話題になるのが『キャッシュフロー計算書』と『キャッシュフロー表』です。計算書は公式ルールに沿って現金の動きを三つの活動に分け、外部の人にも見える形で現金の流れを丁寧に説明します。表はもっとカジュアルで、学習用・社内の練習用として現金の動きを“見える化”します。利益が黒字でも現金が足りなければ動けない、という現実をどう伝えるかを二つの道具でどう表現するか、雑談の中で深掘りしていきます。
前の記事: « 企業年金と私的年金の違いを徹底解説 老後資金を自分で守る方法
次の記事: 公的年金と障害年金の違いを徹底解説!中学生にも分かるポイント »





















