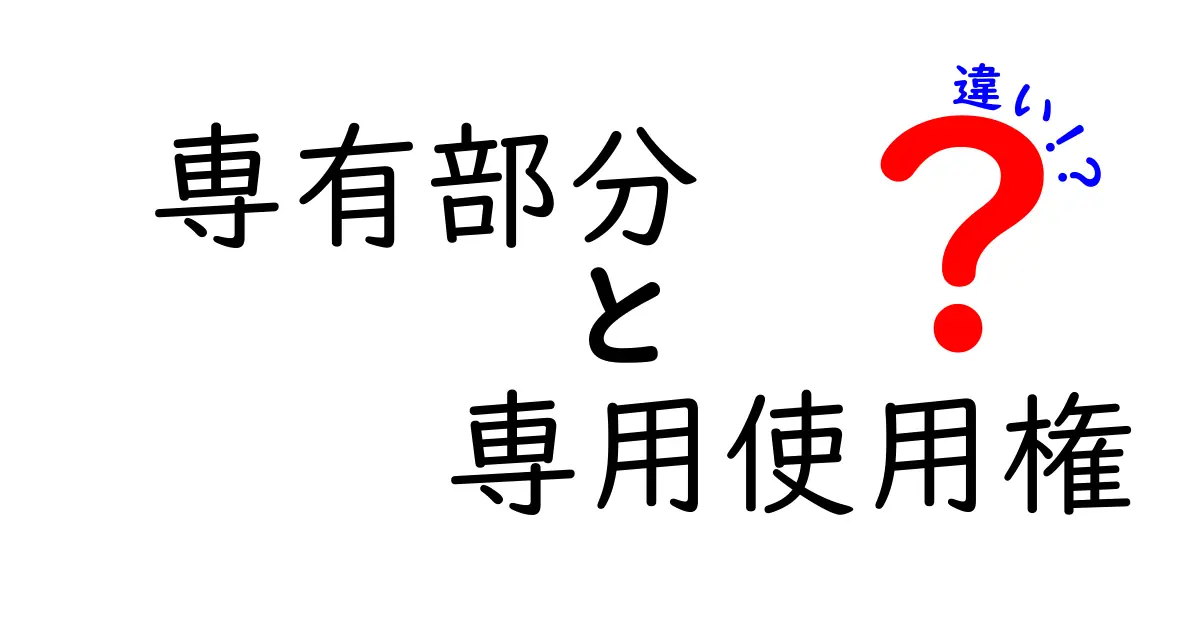

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
専有部分と専用使用権の違いをわかりやすく解説
このテーマは、マンションやアパートなどの建物の「自分の権利」が何を指すのかを理解するうえでとても役立ちます。専有部分と専用使用権は名前が似ていますが、法的な意味は大きく異なります。この記事では、まず両者の基本を丁寧に解説し、次に日常の場面でどう使い分けるべきかを、具体的な例とともに紹介します。さらに、資産価値や将来の売買・リフォームの際に知っておくべきポイントにも触れます。読み進めるほど、自分の住まいの資産価値を守るヒントが見つかるはずです。
特に初学者にも理解しやすいよう、難しい用語はできるだけ避け、身近な言葉を使って説明します。なお、正式な判断や契約は専門家に相談することをおすすめします。ここで扱う内容は、一般的な考え方のガイドラインとして捉えてください。
では、まず「専有部分とは何か」から順に見ていきましょう。
専有部分とは何か
専有部分は、建物の中で「自分だけが所有して使える範囲」として法的に定められた部分のことを指します。具体的には、各区画の壁によって区切られた床や天井・壁などの空間で、所有者が独自に権利を持ち、外部からの干渉を受けずに占有・使用できます。この権利は日本の区分所有法に基づく「区分所有権」として認められ、他の共用部分と区別されます。
例えばマンションの一室や一戸建ての区画の室内部分がこれに該当します。購入時にはその区分の面積や境界が公的な登記により明確化され、固定資産税の課税対象にもなります。また、 interior の改修や造作を行う場合には、管理規約や管理組合の決議が必要となることが多く、勝手な変更は周囲の共用部分に影響を与えるため注意が必要です。
基本的には売買や担保設定も可能であり、資産価値の観点から見ても重要な要素です。所有者は専有部分の権利を他人へ譲渡したり、ローンを組んだりすることで資金を調達できる場合があります。これは「自分の財産」として扱われることが大きな特徴です。
専用使用権とは何か
専用使用権は、「その場所を使う権利だけを他人の財産に対して与える仕組み」のことです。例えば共用部分の中で特定の場所を特定の人だけが使えるようにする場合に設定されます。これらの権利は必ずしも所有権ではなく、契約や管理規約によって定められ、誰が、どの部分を、どの期間使えるのかが明記されます。
典型的な例として、駐車場の位置やベランダの一部、共用廊下の一部などが「専用使用権付き」で提供されることがあります。これらは厳密には物件そのものの所有権を移動させるものではなく、使用権だけを付与する性質を持ちます。権利の移転は、契約の変更や契約の譲渡によって行われることが多く、登記簿上の「物件の所有者の地位」の移転とは別扱いになるケースがほとんどです。
また、専用使用権は期間付きの場合が多く、期間が満了したり、契約が解除されたりすると権利は終了します。建物全体の管理費・修繕積立金の負担は、専用使用権の有無に関わらず対象となることがありますが、権利の対象部分の費用負担は契約により異なります。
この2つの権利は、現実の生活で「誰が何をいつ使えるか」を決める際に大きな影響を与えます。自分がどの権利を持っているのかを日頃から把握しておくと、未来の売却やリフォームの際にもトラブルを避けやすくなります。公式の文書には専門的な表現が多く登場しますが、基本は「使える範囲と管理の仕組みをどう取り決めるか」という点に集約されます。
専用使用権について友人と話していたとき、私は最初、『それって自分のモノ?』と勘違いしていました。しかし現場の話では、専用使用権は“使える権利”であって所有権ではない点が大事です。例えば駐車場を特定の人だけに使わせる契約は、車を所有していてもその場所を使う権利を買っているだけ。権利の性質上、期間が決まっていることが多く、契約満了時には権利が消えるケースが多いです。すぐ“売る”ことは難しく、契約の更新が必要になることが多い。こうした事情を知ると、後から意図せぬトラブルを減らせます。さらに、専用使用権は他人の所有物への影響を避けるために契約で細かく条件づけられます。管理規約をよく読み、どの部分が誰の使用権を持つのかを確認することが大切です。





















