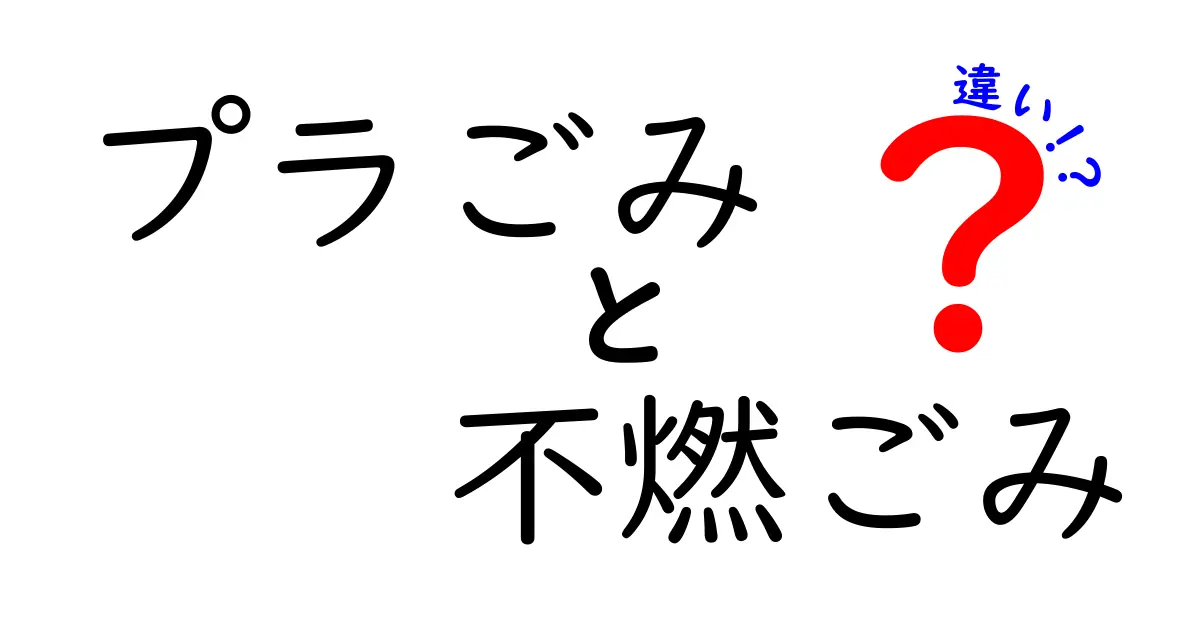

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
プラごみと不燃ごみの違いを理解してクリック率アップを狙う理由
プラごみと不燃ごみは、家庭ゴミの中でも混乱しやすいカテゴリーです。
新しく引っ越したばかりの家庭では、自治体の細かなルールに戸惑う人も多いでしょう。
ここでは、まず基本的な違いを整理します。プラごみは主にリサイクルの対象になりえる素材で、再資源化を目的として出します。一方で不燃ごみは燃やすことができないゴミで、焼却炉の負荷を減らす目的があります。
ただし、素材名だけで判断すると間違いが起きやすい点に注意が必要です。例えば、プラスチック製でも金属が混ざっていたり、ラベルのついた容器が汚れていたりすると不燃ごみ扱いになることがあります。
このようなケースは自治体の指示や回収車両の流れに影響します。
重要ポイントとしては、素材の名前だけで区分せず、自治体の公式情報やラベル表示を確認すること、そして汚れをしっかり落とし、形を崩さず分別することです。
分別が適切であると、リサイクルは効率的になり、焼却処分の負荷は減ります。
家族が協力して日々の分別を習慣化することが、地球環境の未来を守る第一歩になります。
分別の実務と誤解を解くポイント
現場での分別は、家庭の冷蔵庫横のゴミ箱を使い分けることから始まります。まず最初に確認すべきなのは、あなたの自治体がプラごみを何として回収するかです。地域ごとに制度が違うので、町内掲示や自治体のホームページの分別一覧を必ず見るようにしましょう。通常は、プラごみにはPETボトル、ペットボトルのキャップ、食品トレイ、ポリプロピレン容器などが該当します。
一方、不燃ごみには耐熱性のプラスチック部品や傷んだプラスチック製品、金属含有の混合素材などが混じることがあるため、素材の判断だけでなく、形状や汚れの程度も考慮します。
特に液体や油分がついたプラ製品は、汚れを落としてから出すことが基本です。
また、口は完全に閉じないと中身が漏れる可能性があるため、袋の封をしっかり行い、他のごみと混ざらないようにします。
私たちが守るべきルールは、「自治体の指示を最優先にすること」と、「分別したうえで清潔に保つこと」です。以上の習慣を家族全員で共有すれば、分別の正確さは格段に上がります。
友人と話していて、分別の話題になるとよく出るのが“分別の境界線”です。僕はこんな風に説明します。プラごみと不燃ごみの違いは、材料名だけで決まるのではなく、リサイクルの可能性と回収コストの関係で決まることだと。たとえば透明なペットボトルはプラごみとして回収されやすいが、キャップがゴム製だったりラベルが粘着していたりすると、別扱いになる場合がある。つまり、素材の純度と汚れの程度、そして自治体の指示を組み合わせて判断するのが現実的だ。もっとも、完璧を求めすぎず、日常の小さな工夫—洗って潰して軽くまとめる、分別容器を家中に設置して迷わないようにする—が、習慣化のコツだと思います。





















