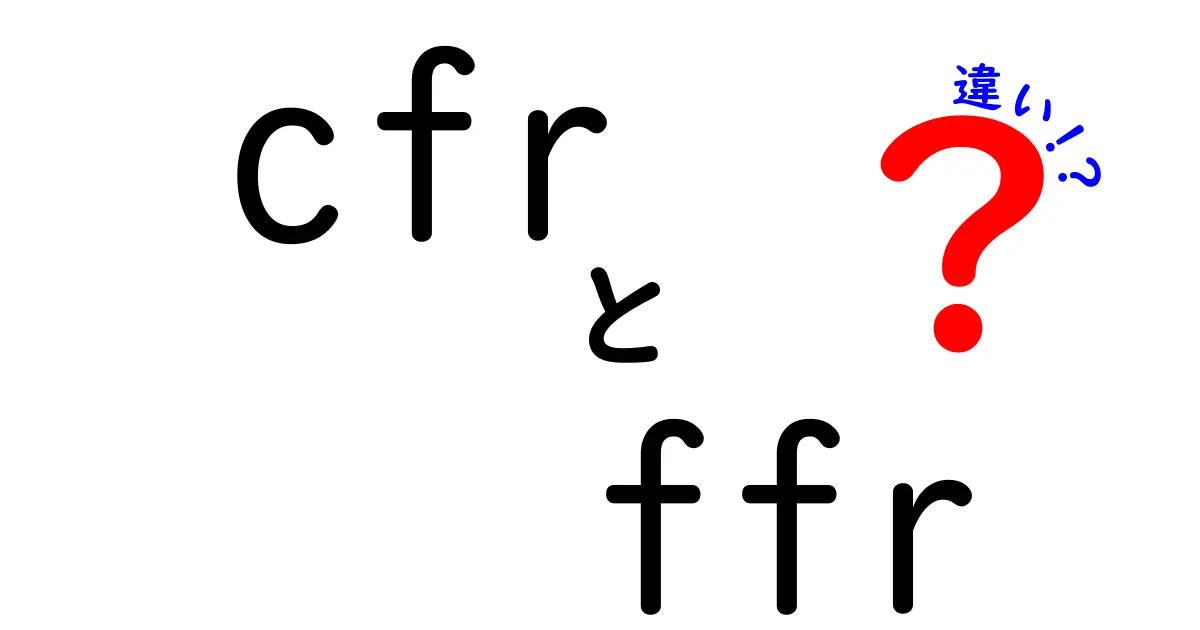

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
CFRとFFRの違いを徹底解説:心臓の血流を測る2つの指標をやさしく理解する
CFRとFFRは、どちらも心臓の冠動脈の血流を評価するための重要な指標ですが、意味・測定の方法・使いどころが異なります。この二つの指標を正しく理解することは、病院での検査を受けるときや治療方針を考えるときに役立ちます。CFRは冠血流の総合的な能力を示し、FFRは狭窄部が血流に与える影響を直接測る指標です。臨床現場ではこの性質の違いを踏まえ、患者さんの病状に合わせて使い分けが行われます。
まずは全体像を押さえ、次に具体的な測定方法・解釈・適用場面へと進んでいきましょう。
CFRとFFRの両者を理解することで、なぜ同じ患者さんでも異なる数値が出るのか、どう判断すべきかが見えてきます。特に微小血管疾患や複数本の病変があるケースでは、二つの指標が互いに補完的な情報を提供することが多いのです。
この節では、まず CFR が何を意味するのか、次に FFR がどういう意味を持つのかを、日常の診療シーンに結びつけて解説します。読みやすい言葉に置き換えつつ、専門用語の定義と現場での実務を結びつけて説明します。
最終的には、患者さんとの対話を想定した説明のポイントや、検査の流れ・注意点も整理します。これから医学的な用語に慣れていく人でも、二つの指標の違いと使い方が自然と理解できる構成にしています。
CFRとは? Coronary Flow Reserve の意味と測定方法
CFRは Coronary Flow Reserve の略で、冠動脈全体の血流の「増える力」を示す指標です。具体的には、安静時の冠動脈血流と最大血流時の比をとった値で表されます。実際の臨床では、血管の狭さだけでなく微小血管の機能も影響するため、CFRは血流の全体的な能力を評価する役割を持ちます。測定方法としては、画像診断と血流量の組み合わせが用いられます。代表的な方法には以下のものがあります。
- PET(ポジトロン断層法)やMRIを用いた血流量測定
- 超音波ドプラ法を用いた流れの推定
- 侵襲的には、カテーテルを使い動脈の流れの変化を評価する手法もあります。
通常、正常なCFRはおおむね 2.0 以上とされ、これを下回ると“冠動脈の血流増加能力が低い”状態と判断されます。CFRが低いと、安静時には血流が足りていても、運動時・興奮時・ストレス時など血流需要が高まる場面で血流不足が生じやすく、痛みや狭心症様の症状が出やすくなります。
注意点として、CFRは大きな血管だけでなく微小循環の状態にも影響を受けるため、微小血管疾患があると正確な判断が難しくなることがあります。さらに、CFRの値は測定法や個人差にも左右されるため、単独での判断よりも他の指標と組み合わせて評価するのが一般的です。
FFRとは? Fractional Flow Reserve の意味と測定方法
FFRは Fractional Flow Reserve の略で、狭くなった冠動脈の“血流の圧力影響”を測る指標です。具体的には、最大血流を作り出した状態(薬剤による発作的な血流増加)で、狭窄部の distal 側と大動脈との圧力比を求めます。一般に、圧力比が 1.0 に近いほど正常で、0.80 未満だと狭窄が機能的に重要(虚血を引き起こす可能性がある)と判断され、血行再建(PCI など)の適応を検討します。
FFRの測定にはカテーテル検査が必要で、カテーテル内の圧力センサーを使って最大血流時の distal 圧を測定します。動脈の狭窄の影響を直接的に評価でき、狭窄そのものが血流に及ぼす影響を“圧力の変化”として捉える点が特徴です。FFRの閾値としては、一般的に 0.80 以下が治療を検討する目安とされ、0.75 など下限値の議論もあります。
FFRは狭窄部の機能的影響を評価することに長けており、特定の病変が再血流改善のための介入が必要かどうかの判断に強力です。とはいえ、FFRは局所的な評価に偏るため、微小血管の機能や他の血流制約を見落とす可能性もあります。そのため、他の検査と併用するケースも多いのが実情です。
臨床での使い分けと注意点:いつどちらを使うべきか
臨床の現場では、CFRとFFRはそれぞれ異なる目的を持って使い分けられます。FFRは“狭窄の有効性”を判断するための指標として非常に信頼性が高く、局所的な病変が患者の血流にどれだけ影響しているかを直接評価します。したがって、特定の血管病変が原因の虚血を疑う場合には、FFRが第一選択となることが多いです。
一方、CFRは“全体の血流増加能力”を評価する指標として有用です。複数の病変がある場合や微小血管疾患が疑われる場合、FFRだけでは不足する情報をCFRが補います。つまり、FFRがその病変の影響を示すのに対し、CFRは全体の血流適応力を示す性質があります。
使い分けの実務的ポイントとしては、以下が挙げられます。
- 単一病変で症状がある場合はFFRが有効なケースが多い。
- 複数病変や微小血管疾患の可能性がある場合は CFR もしくは総合的な評価が重要。
- 介入の必要性を検討する際には、FFRで局所の機能的影響を、CFRで全体の血流応答を確認すると判断が安定します。
検査時の注意点として、薬剤(アデノシンなど)を用いた最大血流状態を作出する際の副作用や、測定の技術的難しさも覚えておくべきです。どちらの検査も専門的な知識と経験を持つ医師・技師が実施する必要があり、患者さんの安全を最優先にします。
総じて、CFRは血流の“潜在的な能力”を評価し、FFRは狭窄そのものの“機能的影響”を評価します。二つを組み合わせて解釈することで、最適な治療方針を立てやすくなります。
CFRとFFRの使い分けのポイント
使い分けのコツは、病変の数と組織の機能を同時に考えることです。単純に狭窄の有無だけで判断せず、患者さんの症状・心機能・他の血管病変の有無を総合的に見ることで、過剰な治療を避けつつ適切な介入を選べます。臨床現場では、ケースごとに二つの指標を補完的に活用することが推奨されています。
また、検査の準備段階で患者さんに説明するポイントとして、どの指標を測るのか、なぜ両方が必要になるのかを分かりやすく伝えることが重要です。例えば「この病変がどれくらい血流を妨げているかを、圧力と流れの両方の視点から見ています」と説明すれば、納得感が高まります。
よくあるケースと誤解を解く
よくある誤解として、「FFRが正常なら治療はいらない」「CFRが高いほど安全だ」という思い込みがあります。しかし、FFRが正常でも他の病変が血流を制限することは珍しくなく、CFRが低くてもFFRが正常な場合には別の治療が検討されることがあります。逆に、FFRで“重要な狭窄”と判断されても、微小血管の問題で症状が改善しないケースもあります。こうしたケースは、二つの指標を組み合わせて総合的に判断することが大切です。
また、検査の適用時期や実施方法には地域や施設ごとの差があります。最終的な治療方針は、担当医と患者さんが納得する形で決定されるべきで、必要に応じて他科の意見を求めることも有効です。
以上のように、CFRとFFRはそれぞれ長所と限界を持っています。患者さんの症状、病変の数、microvascular の状態を総合的に判断することで、最適な治療方針を決めやすくなります。
もし、あなたや身近な人が冠動脈の検査を受ける場合には、医師からの説明をよく聞き、自分の質問をメモしておくと良いでしょう。十分な情報をもとに意思決定をすることが、最終的な健康の改善につながります。
ある日の病院ラウンジで、看護師さんが私にこう言いました。
「CFRとFFR、同じ血の話だけど、どっちが自分にとって大事なのかを覚えておくと、検査の意味がわかりやすくなるわよ」。私はすぐに思ったのです。
実はこの二つ、情報の取り方が違うだけで、医師が治療方針を決める手がかりをくれる“友達”のような存在です。CFRは“血がどれだけ増える力を持っているか”を、FFRは“狭くなった道がどれだけ血の流れを妨げるか”を、それぞれ教えてくれます。
コップ一杯の水を例にすると、CFRは体全体の水の流れの元気さ、FFRは狭い通りを抜ける水の圧力を測るようなイメージ。二つを組み合わせると、患者さんの症状がどの血流の問題に起因しているのかが、ぐっと見えてくるのです。
だからこそ、検査の結果を一つだけで判断せず、医師の説明を丁寧に聞くことが大切だと私は感じました。
前の記事: « maa nda 違いを徹底解説!意味・使い方・例文で理解を深める





















