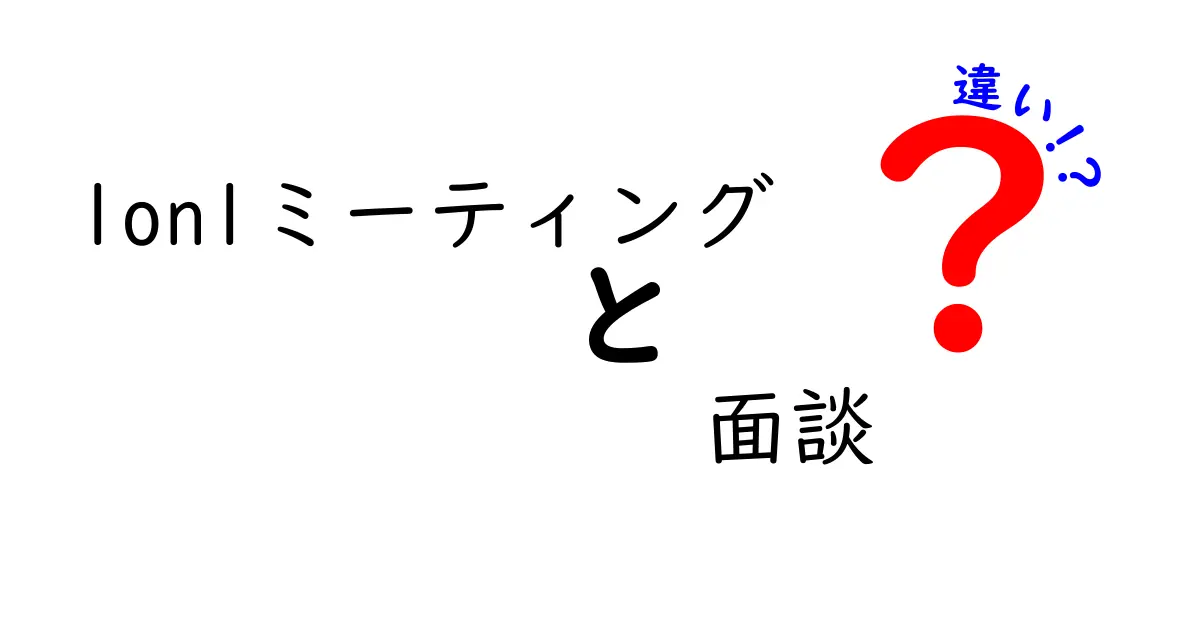

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:クリックされる理由と全体像
このキーワードを検索する人の多くは、1on1ミーティングと面談の意味が混同していることに気づき、正しい使い分けを知りたいと思っています。まず結論を先に言うと、1on1ミーティングは普段の部下育成・業務支援のための継続的対話であり、面談は組織の意思決定や評価・採用などの特定の目的に使われる対話です。場の設定も異なり、1on1は定期的に設定される小さな枠組み、面談は必要な時に設定される大きな枠組みです。結果として、1on1は長期的な関係性の構築を重視しますが、面談は短期的・成果指向の情報収集と判断材料の整理に重きを置きます。現場ではこの違いを理解して使い分けると、部下の成長を促す対話と組織の透明性を同時に高めることができます。つまり日常のフィードバックと公式な評価を混同しないことが大切です。
1on1ミーティングとは何か
1on1ミーティングは、2人だけで行う定期的な対話の場です。基本の目的は成長支援と課題解決です。頻度は週1回や隔週など組織や部門によって異なり、長期的な視点でのキャリア設計も含まれます。典型的な進行は、事前に部下が議題を提案し、開始時の軽いチェックイン、前回のアクションの確認、今週の予定と課題の話し合い、最後に今後のアクションを設定する、という流れです。重要点は 信頼関係と安全性 をつくること、開かれた質問 を用いて部下の本音を引き出すこと、実行可能なアクション に落とすこと、そして記録とフォローアップを徹底することです。リモートと対面での運用の差は、画面越しでも声のトーンと反応を丁寧に読み取ること、画面共有やドキュメントを活用して透明性を高めることです。失敗例としては、ただの報告会に終わってしまう、準備不足で話が雑になる、という点が挙げられます。
面談とは何か
面談は状況に応じて幅広く使われる対話の総称です。採用前の面談、配属や異動の人事面談、評価の面談など、場面によって目的が変わります。採用前の面談は候補者の適性を見極める場で、候補者の志望動機や業務適性を深掘りします。人事面談は組織の人材配置を決定する情報を集め、従業員のキャリア設計を支援します。評価面談は過去の成果を振り返り、次の目標設定と改善点を話し合います。いずれも公式記録が残ることが多く、透明性と公正さが求められます。面談は公式な場として扱われやすく、話題や質問は事前に準備されることが多いですが、部下が安心して話せる雰囲気作りも大切です。
実務での使い分けと運用のコツ
ここからは実務での具体的な使い分けのコツを解説します。日常のフォローには1on1を使い、年次の大きな意思決定には面談を使う、という基本方針が有効です。まず準備の段階ですが、1on1では部下が自分の課題と相談事項を事前に整理する時間を設け、上司は聴く姿勢とメモの取り方を工夫します。面談では目的を事前に明確化し、議題と評価基準、合意事項を共有します。実作業では以下の手順を繰り返すと良いです。1)目的を再確認 2)議題を自由に話す 3)要点をメモに残し、次回のアクションを設定 4)会議後に公式記録を共有 5)次回のフォローを明確に約束します。
まとめと実務のヒント
要点を振り返ると 1on1ミーティングは成長と信頼構築のための継続的対話、面談は組織の意思決定に関する公式な対話という役割分担が明確です。日常的には1on1を軸に、必要に応じて面談を活用するのがバランスの良い運用です。注意点としては、どちらの場面でも準備と記録、フォローアップを欠かさず、相手の話を肯定的に聴く姿勢を保つことです。これを実践すれば、部下の成長を促し、組織の透明性と信頼性を高めることが可能になります。
追加の実務ヒント
導入前には経営層と人事部の合意を取り、方針を公開しましょう。定義を揃え、守秘義務と記録の取扱いを明確にします。組織文化として批判を恐れず話せる雰囲気づくりを重視し、記録の保管場所・アクセス権限・保存期間を周知します。落とし穴としては、1on1が過度に長くなり時間管理が崩れる場合や、面談が過度に形式的になると信頼を損ねる点です。ここで紹介したポイントを守れば対話文化を高めつつ業績にも結びつきます。
- 定義を会社全体で統一する
- 守秘義務とプライバシーを確保する
- フォローアップの責任者を明確にする
今日の小ネタは1on1の語源話。1on1は英語のone on oneがそのまま日本語化された表現で、二人が向き合って話す空間という意味です。会議室に入るとき、二人だけの世界が始まる感じが新鮮で、相手の言葉を遮らず聴く姿勢が信頼の土台になります。最近はリモートでもこの距離感を保つ工夫が増え、画面越しの表情や声のトーンを注意深く読み取る訓練が役立ちます。小さな工夫として、議題を二つに分けると整理しやすく、部下が話しやすい雰囲気が生まれます。結局は会話の質を高めるコツを覚えることが、1on1を成功させる最短ルートです。





















