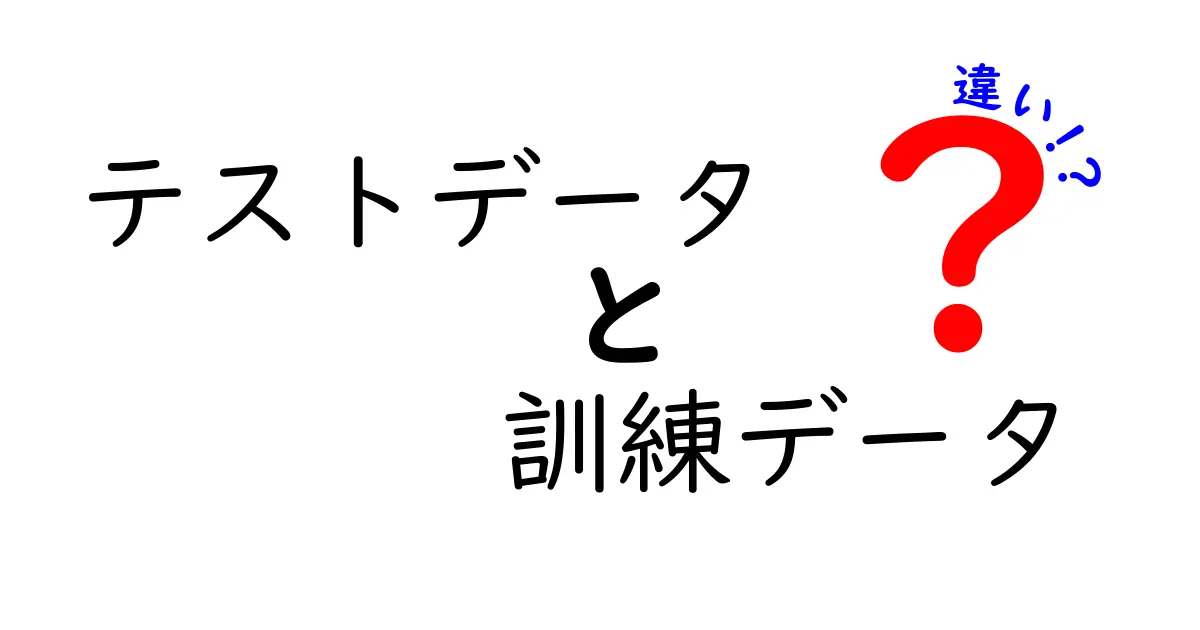

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
テストデータと訓練データの違いを徹底解説!中学生にも分かる具体例つき
テストデータと訓練データの違いを理解するには、機械学習という仕組みをイメージすると分かりやすいです。機械学習では、まずデータの山からロボットの“知識”を作るための材料を集めます。その材料を2つのコップに分ける作業が必要で、ひとつはモデルを育てるための訓練データ、もうひとつは完成したモデルの力を確かめるためのテストデータです。ここで大切なのは、両方のコップの中身が似すぎてはいけないということです。訓練データで覚え過ぎると、形の似た事例だけを得意にしてしまう“過学習”が起きてしまいます。そうなると、実際の世界に現れやすい新しいデータに対してはうまく予測できなくなります。そこで、訓練データとテストデータを適切に分けて使うことで、モデルが新しい状況にも対応できる力を持つように育てられるのです。
この基本を理解すれば、データをどう扱うべきか、何を評価すべきかの土台が固まります。
基本の理解:データを分ける理由とは
ここで言う、機械学習には訓練データとテストデータは別々のデータで、同じソースや似たルールのデータを混ぜないことが重要です。訓練データはモデルがパターンを見つけるための“教師用の材料”です。ここでは特徴量と呼ばれる入力の情報と、それに対応する正解ラベルがセットになっています。モデルはこのデータに対して何をどう予測すべきかを何度も繰り返して学習します。ところが、正しい答えに近づくようにだけ学習してしまうと、別のデータを出してみたときに正解率が落ちてしまいます。だから、訓練データの中にもバリエーションが必要です。テストデータは学習の最後のチェック用であり、モデルが本当にどれだけ汎用的に使えるかを測る鏡の役割を果たします。訓練データとテストデータは別々のデータで、同じソースや似たルールのデータを混ぜないことが重要です。これにより、モデルの実力を正しく評価できます。
実務での流れ:機械学習の作業での使い分け
実務では、データを集めた後でまずデータを分割する設計が最初の仕事です。データをどう分けるかは、モデルの目的やデータの性質によって少しずつ違いますが、基本は70/15/15程度の訓練/検証/テストの比率を目安にすることが多いです。検証データはモデルのハイパーパラメータを調整するための中間チェックで、テストデータは最終評価に使います。開発中は訓練データを使ってモデルの性能を高め、時にはクロスバリデーションと呼ばれる方法でデータを複数の分割で回して学習します。こうした手法を実践することで、過学習を避け、現実世界の新しいデータにも強いモデルが出来上がります。現場ではデータの前処理、欠損データの扱い、カテゴリ変換、スケーリングなどの作業も同時並行で行われ、訓練データとテストデータの境界を崩さないように注意します。
表でざっくり比較
この節では、訓練データとテストデータの違いを表でざっくり比べます。表に入れる項目は下記のような点です。用途、役割、リスク、評価指標、分割の基準など。表を読むと、なぜデータを分けるのかが頭の中で映像としてつながりやすくなります。以下の表はあくまで概略ですが、実務でよく使われる考え方をまとめたものです。
訓練データという言葉を聞くと、私は友人とアニメの制作現場の話を思い出します。私たちはまず、登場人物の言動や背景をたくさんの例として用意します。これをモデルの練習素材として机の上に並べ、正解を見せながら解き方を覚えさせます。しかし現実には、同じパターンばかりが現れるわけではありません。だから訓練データにはバリエーションを増やす工夫が必要です。新しい場面を少しずつ加えることで、モデルは「こんな場合でもこう動くべきだ」という考え方を身につけ、実際のデータにも対応できるようになります。
前の記事: « 教師データと訓練データの違いを理解する基本ガイド





















