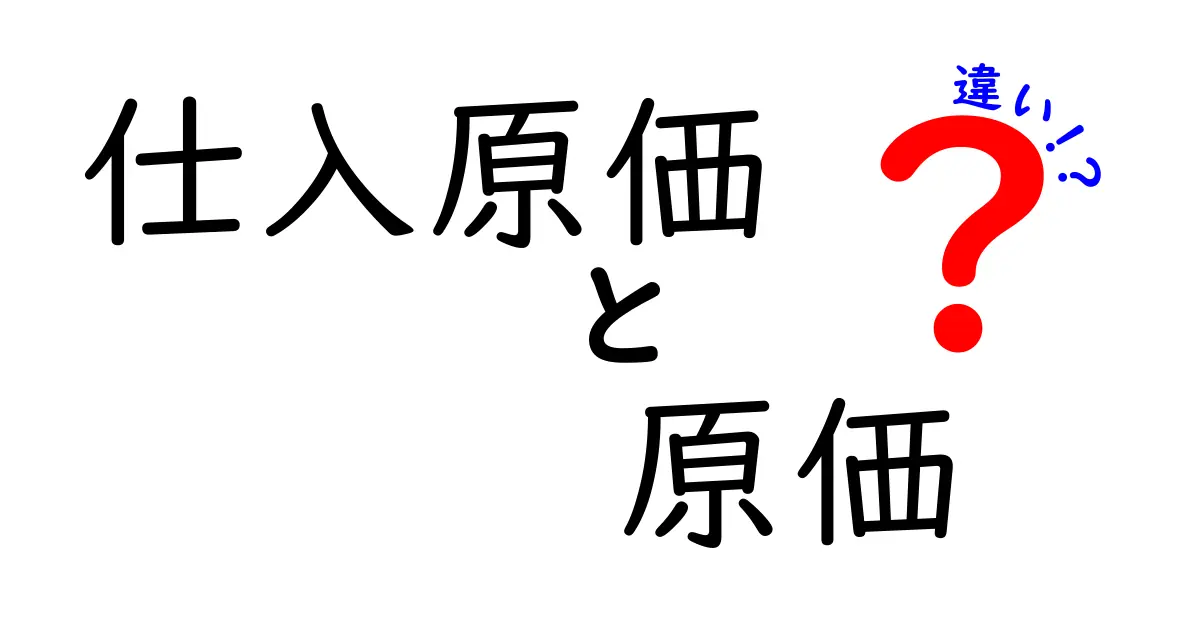

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
仕入原価と原価の違いを正しく理解するための徹底ガイド
この章では、まず仕入原価と原価の基本的な意味を整理します。仕入原価とは何か、そして日常の事例でどう使われるのかを、実際の数字を使って丁寧に説明します。
中学生にも伝わるように、専門用語をひとつずつ噛み砕き、身近な例とともに考え方を示します。
また、会計の世界では費用の計上方法が場面によって変わることがあります。仕入原価と原価の違いを知ることで、商品がどうやって利益につながるのかが見えるようになります。
このガイドの目的は、数字が苦手な人でも費用の区分を理解できるようになることです。仕入原価は“仕入れた商品の入手コスト”を表し、原価は“製品を作るためのコスト全般”を示します。つまり、同じ“コスト”という言葉を使っていても意味が異なる場面があるという点を押さえましょう。実務では、在庫を保有する企業と、生産して自社ブランドの商品を扱う企業とで、費用を分けて管理します。こうした区分をきちんと行うことが、正確な利益計算と適切な意思決定につながるのです。
仕入原価とはどんな費用か
まず前提となるのが仕入原価です。仕入原価は「商品の仕入れに直接かかった費用の総額」を指します。具体的には「購入価格」に加えて「運賃・保険料・関税・検品費用・荷役費用」など、商品を自社の在庫として手元に置くために必要な費用を含みます。
たとえば食品を仕入れるとき、A社から野菜を1kg100円で買い、運送費が20円、検品費用が5円、保険が3円、関税が0円なら、仕入原価は全体で128円になります。ここには在庫としての価値が含まれており、売上を計上する際にこの仕入原価が原価として扱われます。
このように仕入原価は「仕入れのために直接かかった費用の総額」と覚えておくと混乱にくくなります。
原価とは何か、どんな場面で使われるか
次に出てくる言葉が原価です。原価は「何かを作るのにかかった費用全般」を指すことが多く、製品を作る企業では「製造原価」という言い方をします。製造原価には材料費、労務費、製造間接費が含まれ、これらを合計して一つの製品のコストとします。つまり、原価は「作るときにかかった総費用」で、仕入原価とは範囲が少し違います。
この区別は、在庫を持つビジネスや自社ブランドの商品開発、工場での生産など、さまざまな場面で使われます。一般に原価は売上総利益を計算するうえで重要な値であり、利益を分析するための基本データとして機能します。
違いを整理する表と実務のポイント
実務では、仕入原価と原価の使い分けを正しく行うことが大切です。以下の表は基本的な違いを整理したものです。
実務のポイントとして、在庫評価や原価計算をする際には、どの費用が含まれるかを明確にすることが重要です。
たとえば卸売業と製造業では、仕入原価と原価の扱い方が異なります。
この理解があると、決算時の在庫評価や利益の見積もりが正確になります。
この表を見れば、仕入原価と原価がどの場面で使われるかがわかります。実務では、在庫を持つ企業と自社でモノを生産する企業で使い分けることが多く、財務諸表の読み方にも影響します。
最終的な「利益」は、売上高からこの原価を引いた額で決まり、適切な費用の区分と正確な計上が、企業の経営判断や将来の計画を左右します。
今日は友だちと雑談するような雰囲気で、仕入原価と原価の違いについて深掘りしていこう。仮に君が文房具を仕入れる会社の経営者だとするね。まず仕入原価は“その商品を仕入れるのに直接かかった費用の総額”を表すんだ。購入価格に加え、運賃や保険、関税、検品費などが含まれる。では原価はどうか。原価は“モノを作るためにかかった費用の総額”のこと。つまり原価は材料費と人件費、製造設備の維持費などをまとめたものになる。ではどう違うのか。仕入原価は在庫として手元にある商品にかかる費用、原価はその商品を作るための費用と捉えると整理しやすい。現場では、仕入原価と原価を適切に分けて管理することが、利益を正しく計算する第一歩になるんだ。もし在庫の評価を間違えれば、実際の利益が見えなくなることもある。こうした違いを意識して、費用の区分を正確に行えば、経営判断もより現実的になるはずだ。





















