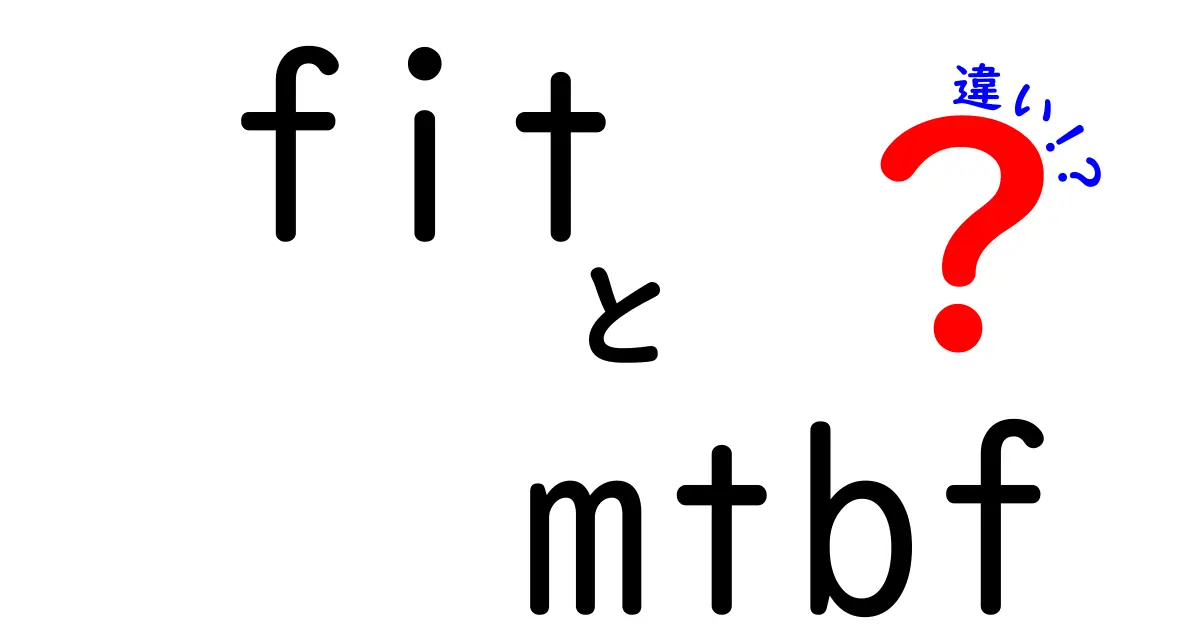

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
FITとMTBFの違いを理解するための基礎講座
FIT(Failures In Time)とMTBF(Mean Time Between Failures)は、機器の信頼性を評価するときによく使われる指標です。これらは似ているようで、実は測っているものと使われ方が違います。FITは故障が発生しやすさの頻度を1e9時間あたりで表す指標で、部品が多くの時間を使って動いた場合にいくつ故障するかを見積もるときに便利です。対してMTBFは、故障と故障の間の平均時間を表す時間の間隔の指標であり、保守計画や長期的な信頼性の判断に向いています。
この二つの指標を混同すると、計画がずれてしまうことがあります。例えば、部品数が多い製品でMTBFが長いと「壊れにくい」と思われがちですが、実はFITが高いと短時間で多くの故障が起きる可能性があり、短期間の信頼性には注意が必要です。
どちらを使うかは、あなたが何を評価したいか、どのくらいの期間で意思決定を行うかで決まります。
実務では、仕様書や品質データシートに正式な値の定義と単位が明記されていることを確認するのが基本です。
MTBFとFITの実務での使い分けポイント
実務では現場の要件に合わせて指標を使い分けます。短期の保守計画にはFITの視点が有効なことが多い一方で、長期の信頼性評価や設計の比較にはMTBFが役立ちます。
ここでは実務でのポイントを整理します。
まず第一に、データの出典と定義を確認することです。測定の対象部品、試験条件、時間の単位などがデータシートと一致していなければ、数字だけ見ても誤解を生みます。次に、製品のライフサイクルと保守頻度を考慮して指標を選択します。工場のラインで1日単位の改善を狙うならFITが現実解になる場合が多く、家電製品の長期信頼性を評価するならMTBFが適しています。最後に、両方の指標を併用して総合判断するのが最も安全です。数値だけでなく、現場の経験や原因分析も合わせて検討しましょう。
koneta: 最近、ある機械の保守計画を立てる機会があり、FITとMTBFの違いについて同僚と雑談した。話をすると、FITは“1e9時間あたりの故障回数”の指標で、部品の信頼性を比較するのに向く。一方MTBFは“故障が起きるまでの平均時間”を示すので、保守の頻度を決める判断材料になる。結局は、長期視点と短期視点の両方をバランスよく見ることが大切だと気づいた。
前の記事: « 不良率と歩留まりの違いを完全解説!中学生にもわかる基礎と計算方法





















