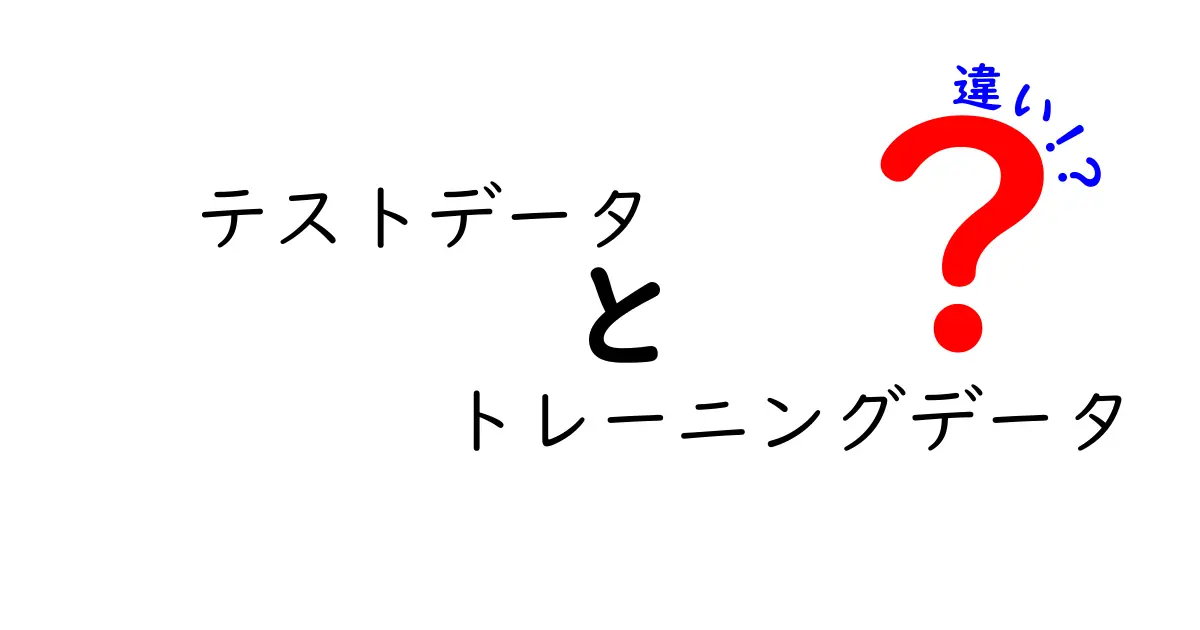

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
テストデータとトレーニングデータの違いを理解する基本
機械学習という言葉を聞くと難しく感じる人もいますが、実はデータをどう使うかというだけの話です。ここではトレーニングデータとテストデータの役割を丁寧に分けて説明します。まず大切な考え方は学習と評価を別々にするということです。学習は情報を蓄える作業、評価はどれくらい正しく推測できるかを確かめる作業です。トレーニングデータは学習用、テストデータは評価用です。これを間違えると作られたモデルは新しいデータに弱くなり、いわゆる過学習の原因になります。過学習とは覚えたことを本番には適用できず、まるでテストだけの練習に強い人のような現象です。
この違いを理解することはデータを使うときの基本中の基本です。
- トレーニングデータの役割はモデルに学習させること
- テストデータの役割は学習した後の実力を測ること
- 検証データはハイパーパラメータの調整に使うことが多い
分割の目安としてはよく使われる比率があり、70対15対15などが挙げられます。これらは標準的な目安でありデータ量や目的で変わります。データを分ける理由は未知のデータにも正しく推測できるかを試すためです。もし全てを一つのデータにまとめてしまうと、モデルはそのデータの偏りを覚えてしまい、実際の新しいデータに弱くなります。データを分けて使うときは偏りを避けるためにシャッフルを行い、カテゴリが偏っていないか確認します。これらの注意を守るだけでモデルの信頼性はぐんと上がります。
日常の例で考えるとつながる理解
学校のテストの例を使ってデータの使い方を身近に感じましょう。練習問題を解くときは解法を覚える作業が中心です。これがトレーニングデータにあたります。新しい問題に挑む本番のテストのときには、覚えただけの解法をそのまま使えるかどうかを試します。これがテストデータの役割です。良いモデルは練習で身につけた考え方を新しい形の問題にも応用できるよう、学習と評価を分けて考えます。
さらにデータを選ぶ順番や分け方にもコツがあります。データの順序をランダムに並べ替えるシャッフルを使い、あるカテゴリのデータが偏らないようにすることが大切です。偏りがあると学習の結論が偏ることになり、現実の場面で正しく判断できなくなるからです。
今日はテストデータとトレーニングデータの話を友達と雑談風に深掘りします。練習問題を解くときの感覚を日常の出来事に例えると、何が学習で何が評価かが見えるようになります。例えばスポーツの練習と公式戦の違いを思い浮かべてください。練習中はコツを覚えることが中心ですが、それを公式戦で実際に使えるかを見るのが評価です。練習データを増やすときは、ただ同じ問題を何度も解くのではなく似た形の問題に挑戦して考え方を広げます。これが学習の力です。一方、公式戦で問われる新しい問題は練習の成果を試す場であり、データを分けておく理由は未知の問題にも強くなるためです。もし練習だけで終わってしまうと、覚えた解法が特定の問題にしか通用せず、現実の難問には対応できません。だからデータを分け、適切な評価を受けることがとても大切です。





















