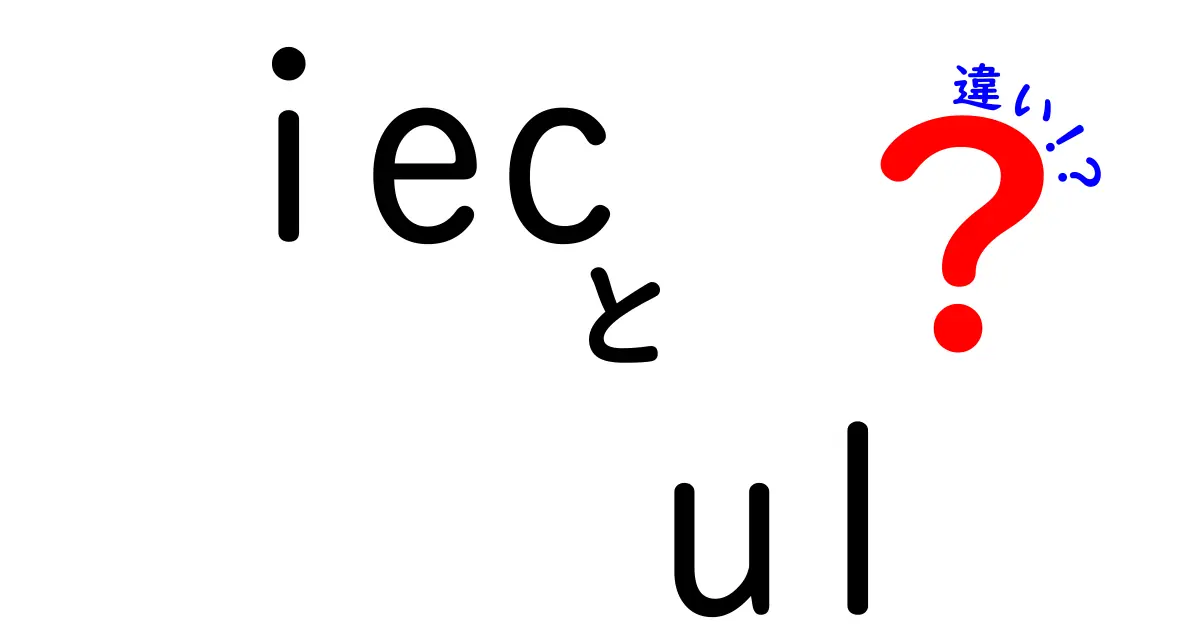

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
IECとULの違いを深掘りする理由
世界にはたくさんの安全規格があり、製品を市場へ出す前にどんな検査を受けるべきかを教えてくれるのが規格です。IECは国際的な組織で、世界中の国々がこの基準を参照して自国の法制度や規制を作ります。
このため、同じ製品が複数の国で販売される場合、IECを出発点として各地域の補足規制に対応することが多いです。しかし地域ごとに細かな差があり、同じ製品でも市場ごとに求められる適合試験が異なることがあります。
この点を理解しておくと、海外展開の計画が立てやすくなり、どの市場でどの認証が必要になるかを事前に予測できます。
一方、ULは主に北米市場に特化した認証機関です。ULは現地の安全性と耐久性を実証する試験を重視し、ULマークを取得することが北米の信頼性の証になります。北米以外の地域でもULと同様の検証過程をとる企業はありますが、最も一般的なマークはULです。家庭用機器や工業製品の安全性を示す際にUL認証が求められる場面が多く、現地市場進出の際には欠かせない要素となります。
このようにIECとULは市場ごとに「認証の文化」が異なることを教えてくれる大切な指針です。
IECとULの仕組みと実務的な違いを知ろう
ここからは実務の話です。認証の目的は共通して「消費者を守ること」ですが、進め方が異なります。IECは世界的な標準を作る機関であり、各国はその規格を国内法や規制の中で解釈して適用します。つまり、ある国で通る規格が別の国で必ずしも同じ形で認められるわけではなく、地域ごとに追加の試験や文書提出が必要になることがあります。
ULは検査機関として現地の審査を中心に進み、機器の部品、絶縁、耐熱性、電気的安全性などを実際の試験で確認します。試験にOKが出れば認証が得られ、製品ラベルやマークを付けることができます。こうしたプロセスは透明性が高く、企業や消費者にとっては判断材料が増える利点があります。
こんな感じで、IECとULは「世界基準と北米の現実」を結ぶ両輪です。製品を世界市場に出すときは両方を視野に入れると安全性と流通の両方を確保できます。もしあなたがメーカー側であれば、最初にどの地域を狙うのかを決め、適切な認証ルートを計画すると良いでしょう。
この考え方は個人の家電だけでなく、学校で使う実験機材や学習用ロボットにも当てはまります。市場の違いを理解することで、無駄な時間と費用を減らすことが可能です。
ねえ、IECとULの話、ちょっと難しく感じるかもしれないけど、要は世界の安全基準と北米の安全基準をどう使い分けるかってこと。ULのマークは北米での信頼の証になるし、IECは世界中の国が共通して使える基準を作る。現場では製品を出す地域に合わせて、どの認証を先に取るべきか計画を立てるのが大事。マークひとつで市場の扉を開くこともあれば、別の地域では別の証明が必要になることもある。つまり、世界で売るには“戦略的な認証の順序とタイミング”を考える必要があるんだね。
次の記事: Wi-Fi規格の違いを徹底解説!自宅と学校で正しい規格を選ぶコツ »





















