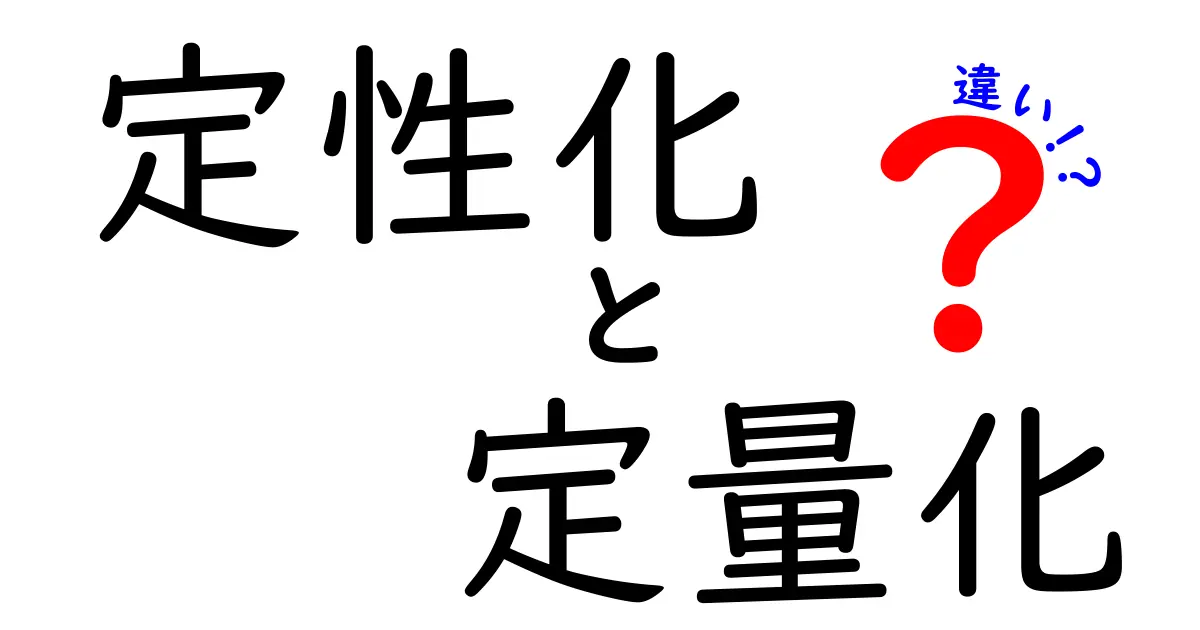

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
定性化と定量化の違いをざっくり知る
データには大きく分けて2つの世界があります。ひとつは言葉や感覚で語る定性的な情報、もうひとつは数字で語る定量的な情報です。定性化とは、物事を“どう感じたか”“どんな質があるか”といった言葉のかたちで整理する作業です。具体的には人にインタビューして意見を録音・文字に起こし、そこから共通のテーマを見つけ出す作業を指します。定性的なデータは、経験や背景、場の雰囲気など、数値には表れにくい細かなニュアンスを拾えるのが長所です。たとえば学校の授業を受けたときの“楽しかった”“難しかった”といった感覚、友だちの話し方のリズム、クラス全体の雰囲気などを言葉で整理します。
ただし、数値と違って「どのくらい多いか」を正確には示せません。人によって感じ方が変わりやすく、同じテーマでも解釈が分かれやすい点が難点です。
一方で定量化とは、物事を数値で表す作業です。測定可能な指標を設定し、データを集め、平均値・割合・頻度などの統計的な指標へ変換します。例えば「1週間の授業出席率は何%だったか」「テストで何点以上を取った人の割合はどれくらいか」といった形です。数値は直感に頼らず、客観的な比較を可能にします。
ただし、数字だけでは現場の複雑さが見えづらく、原因を特定するには追加の分析が必要です。定性化と定量化は“両輪”のように使うと、物事をより深く、正しく理解できます。
この違いを知っておくだけで、ニュースのデータ解説や学校のレポート作成、プロジェクトの進め方が変わってきます。
定性化の特徴と使い方
定性化の基本は“質”を深掘りすることです。まず質問を決め、開かれた問いで人の意見や感情を引き出します。次に得られた言葉を整理して、意味の似ている内容をグループ化します。この作業を「コーディング」と呼び、そこから共通のテーマを見つけ出し、物語として説明します。
特長として、現場の空気感・背景・文脈がそのまま生きてくる点があります。人の気持ちや経験の深さを伝えられるので、何が大切かを理解するのに向いています。
使い方のコツは、信頼できる人に話を聞くこと、偏りを避けるために複数の視点を集めること、そしてデータを記録したら必ず要約と引用を残すことです。これにより、後で「この表現はどんな場面で生まれたのか」を再現しやすくなります。
定性化を学ぶと、相手の声をそのまま拾う力がつき、説明不足だった点を補うヒントが増えます。
実際の現場では、インタビューの録音を文字起こししてから、キーワードの出現頻度を見たり、似た言い回しを集めてグループ分けをする練習をします。こうした作業は、教育現場や地域の調査、マーケティングの初期段階で特に役立ちます。
定量化の特徴と使い方
定量化は、データを数値で扱う作業です。測るべき指標を決め、標準的な方法でデータを集め、統計的な処理をします。代表的な方法はアンケートの点数化、実験による測定、計測器の読み取りなどです。数値を集めたら、平均値・中央値・分布・比率などを計算して、グラフに表します。こうすることで、全体の特徴を「見える化」し、他のデータと比較することができます。
定量化の長所は、客観性と再現性です。同じ条件なら誰が分析しても同じ結論に近づく可能性が高く、意思決定を助ける力が強いです。
注意点は、数値だけに引っ張られて現場の実態が見えにくくなることです。たとえば「得点が高い人は必ずしも満足しているわけではない」というようなケースもあります。定性化と組み合わせると、数字の裏にある意味を読み解くことができます。
ビジネスの現場では、顧客の購買データを分析して需要を予測する際に定量化が活躍しますが、顧客の声を聞く定性化と合わせることで、なぜその傾向が生まれているのかを理解する力がさらに強くなります。
このように、定量化は数字という共通言語を作ってくれるため、全体像を素早く把握する力を高めてくれます。
定性化と定量化の比較実例
ここでは、学校のイベント評価を例に、定性化と定量化がどう協力して意味を作るかを示します。まず定性化では、参加者の感想を文字起こしして「楽しかった」「退屈だった」「運営がスムーズだった」「待ち時間が長かった」といったテーマを抽出します。次に定量化では、同じイベントをアンケートで5点満点の満足度に数値化し、出席率やリピート意向の割合を算出します。
この組み合わせにより、数値だけでは分からなかった満足の理由が、発言のテーマとして見えるようになります。以下の表は、その違いを整理したものです。
このように、定性化と定量化は対立ではなく、状況に応じて使い分けることが重要です。適切に組み合わせることで、データの洞察が深まり、より良い判断につながります。
友だちとの雑談を思い出してほしい。会話の中には数字で測れない“雰囲気”や“感じ方のちがい”が必ずある。そんなとき定性化の腕を少しだけ磨いておくと、相手が本当に伝えたい意味を拾い上げられる。ある日、学校のイベントを振り返るとき、定性的な感想と定量的な満足度を併用するだけで、なぜ人気だったのか、どこを直せばいいのかが見えてくる。結局、数字は道案内、言葉は地図。これが定性化と定量化を仲良く使うコツだと思う。
次の記事: 【図解付き】p値と効果量の違いが一目で分かる完全ガイド »





















