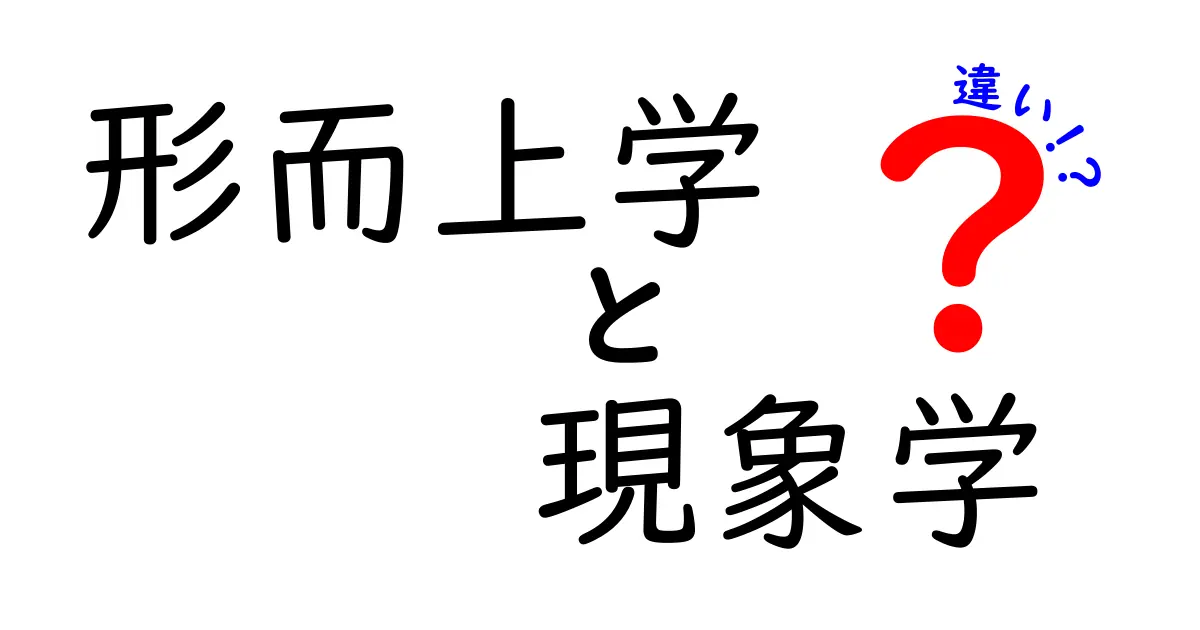

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
形而上学と現象学の違いを徹底解説!中学生にもわかるやさしい入門ガイド
形而上学の基本と問い
形而上学とは、現実の“表れてくるもの”の背後にある本当の性質を問う学問です。私たちが目にする星、木、音、考え方などの“現れ方”は大切ですが、それらがなぜ存在するのか、存在するとはどういうことなのかを考えるのが形而上学の役目です。つまり、存在とは何か、現実の背後にある本質とは何かといった大きな問いに取り組みます。日常の理科や生物の授業で物を測る方法を学ぶのとはちょっと違い、物事の“根っこ”をさぐることが多いのが特徴です。
形而上学は論理と概念の整理を好みます。実在するかどうかを実験で確かめるのではなく、概念の間違いや言葉の使い方を正す作業を多く含みます。例えば、存在を説明する言葉が複数あると混乱が生まれやすいので、それぞれの語が何を指しているのか、どの条件で成立するのかを明確にします。これが難しく感じられる理由の一つです。
日常と形而上学のつながりを考えると、私たちが物事をどのように“意味づけ”するかが見えてきます。哲学の用語をやさしく解くとき、私たちの体験や価値観、文化の影響をどう扱うかを考えることが大切です。身近な例を通して思考を整える練習を重ねると、難しい言葉にも少しずつ慣れていきます。
現象学の基本と体験の読み方
現象学は“私たちが世界をどう体験するか”を研究する考え方です。物事が実際にどう存在するかという前提を外して、まず私たちの意識に現れる“現象”を観察します。思考、感覚、感情、欲求など、意識の中で現れる全ての経験を手がかりにします。ここで大事なのは、先入観を一旦置く、epocheと呼ばれる方法です。つまり、科学的な前提や常識をいったん横に置いて、体験そのものをそのまま観察するのです。
例えばリンゴを見ているとき、私たちは色、形、匂い、味、経験する手触りなどを同時に感じます。現象学はそれらの要素を分解し、どの順番で現れるか、何が“リンゴそのもの”としての意味を作るのかを探します。この作業は形而上学が扱う“存在の本質”と対照的に、経験の側から世界を理解します。
現象学と日常のつながりを考えると、私たちの感覚が世界の理解をどう形作るかが見えてきます。私が感じる距離感、色の変化、匂いの記憶、声の響き方など、すべてが現象学の材料です。最後に、意識の観察を練習していくと、抽象的な言葉だけでなく、体験を言語化する力も自然と身についていきます。
友達とカフェで哲学の話をしていたとき、形而上学と現象学の違いについて話が盛り上がりました。私が話したのは、形而上学が“ものが何であるか”という根源の問いを立てる学問だという点。対して現象学は“私たちが世界をどう体験するか”を詳しく観察する方法だ、という点です。友人はすぐに「リンゴを見ただけでそのリンゴは何かを語るのか?」と尋ねました。私は「リンゴを見ている私の心の動き」こそ現象学の材料だと答えました。例えば、リンゴの色が変われば気分も変わる、匂いが強いと記憶が呼び起こされる——こうした体験の連鎖が、結局“リンゴそのもの”が何かを理解する手がかりになるのです。
前の記事: « 実験法と観察法の違いを徹底解説!誰でも分かる科学の基本ガイド





















