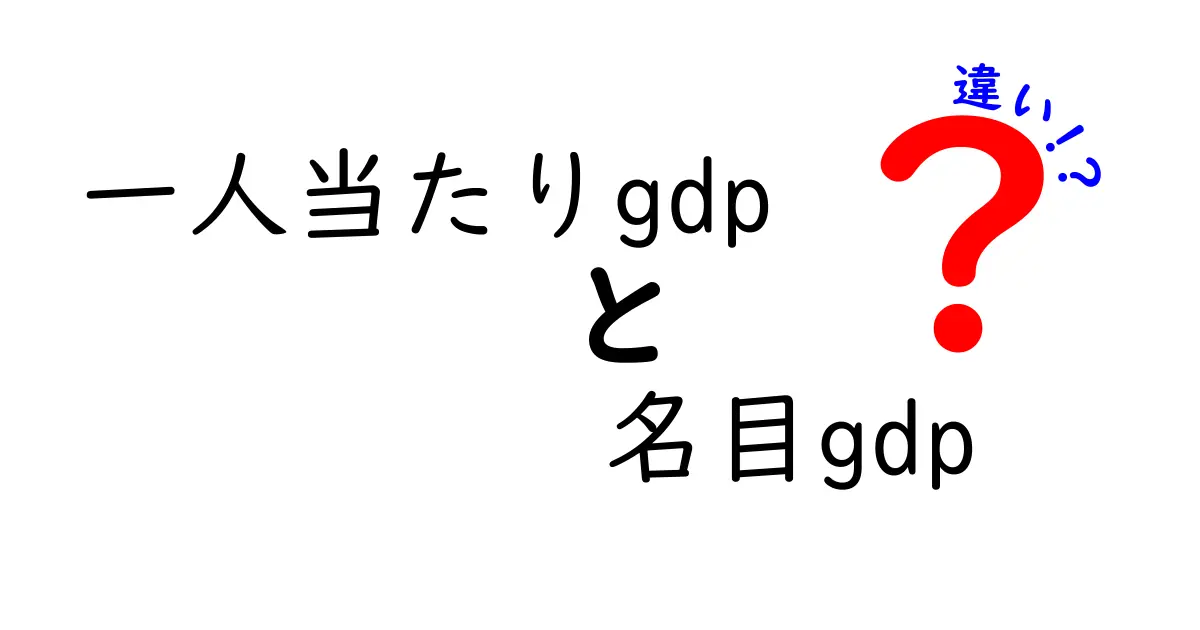

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:数字の読み違いを防ぐ
ニュースでよく出てくる経済の話には、いろいろな指標が登場します。その中でも「一人当たりGDP」と「名目GDP」は、似ているようで意味がぜんぜん違います。私たちは日常の会話でこの二つを混ぜて使いがちですが、本当は使い方が別物です。まず覚えておきたいのは、GDPは国の“価値の総量”を示すものだということです。そこにも物の値段が関係してきます。名目GDPはそのときの価格で計算した「総額」。一人当たりGDPはその総額を人口で割った「1人分の平均的な生産の量」です。要するに、名目GDPは価格の影響をそのまま受け、人口が多いと総額が大きく見えることがあります。逆に一人当たりGDPは人口の分母を使うため、人口が多いほど“生活水準が高い”かどうかが分かりにくくなります。これを理解しておくと、ニュースの数字が意味することを正しく読み解けるようになります。読んだ数字を鵜呑みにせず、「なぜこの国はこういう数字になるのか」を一歩踏み込んで考えましょう。
次に、名目GDPと一人当たりGDPの計算の違いを整理します。名目GDPはその年の現時点の価格で計算され、作られたものの市場価値を足し合わせた「総額」です。反対に実質GDPは、価格の変動を取り除くための工夫です。実質GDPを使うと、同じ量の生産でも物価が上がれば名目GDPは上がるのに対し、実質GDPは変化を抑えて比較できます。ここで大切なのは、一人当たりGDPは名目GDPを人口で割るだけの計算に見えますが、人口の変動だけでなく、価格の違いを考えるときにはPPPや実質値を使うのがよい、という点です。これを知っておくと、国と国を比較するときに“どの指標を使うべきか”が分かりやすくなります。これを見逃すとニュースを読むとき誤解につながることがあります。
違いの本質と計算のしくみ
まずは本質的な違いを整理します。名目GDPは、現在の市場価格で計算され、総生産の“価値”をそのまま数字にします。具体的には「その年に作られた全ての商品とサービスの市場価格を足し合わせた合計」が名目GDPです。反対に実質GDPは価格の変動を取り除くための方法で、物価の変動を一定にした新しい基準価格を使って同じ景気の期間を比較します。ここで、一人当たりGDPは名目GDPを人口で割るだけの計算に見えますが、人口の変動だけでなく、価格の差や生活水準の違いを正確にとらえるには、PPPでの調整も必要になることがあります。これにより、単純にGDPが大きい国と人が多い国の関係だけで暮らしの豊かさを判断するのは難しくなります。名目GDPと一人当たりGDPの違いを理解すると、ニュースを読み解く力がぐっと高まります。
身近な例と表での比較
ここでは身近なイメージとして、二つの国を比べる例を考えます。国Aの名目GDPを20兆ドル、人口を1億人、国Bの名目GDPを18兆ドル、人口を0.8億人とします。これを使って一人当たり GDP(名目)を計算すると、国Aは約200,000ドル、国Bは約225,000ドルとなり、名目 GDP が大きいからといって必ずしも一人当たりが高いとは限らないことが分かります。表で見ると、名目GDPと人口が組み合わさると、一人当たりGDPの結果が変わることが一目でわかります。なお、本格的な比較をするときには実質GDPや購買力平価(PPP)を使って物価の違いを調整するのが一般的です。これにより、国ごとの“暮らしの水準”の差が、より正確に見えてくるのです。
表を見ると、総量が多くても人口の違いで1人あたりの数字は変わります。物価が高い国では名目 GDP の数字だけを見ても豊かさを比べられません。次の項目では、こうした違いを踏まえた読み方のコツをまとめます。
名目GDPはその年の価格で計算された総額だから、物価が上がれば数字も大きくなる。つまり“総生産の価値”を表す指標で、人口が多いと見かけ上の数字が大きく出やすい。一方、生活水準の大小を知るには一人当たりGDPや実質GDP、PPPでの調整が必要。私は友だちとこの話をしていて、数字を鵜呑みにせず“仕組み”を知ることの大切さを実感した。雑談の中で、数字の裏側を理解すると経済ニュースがずいぶん身近に感じられるようになった。





















