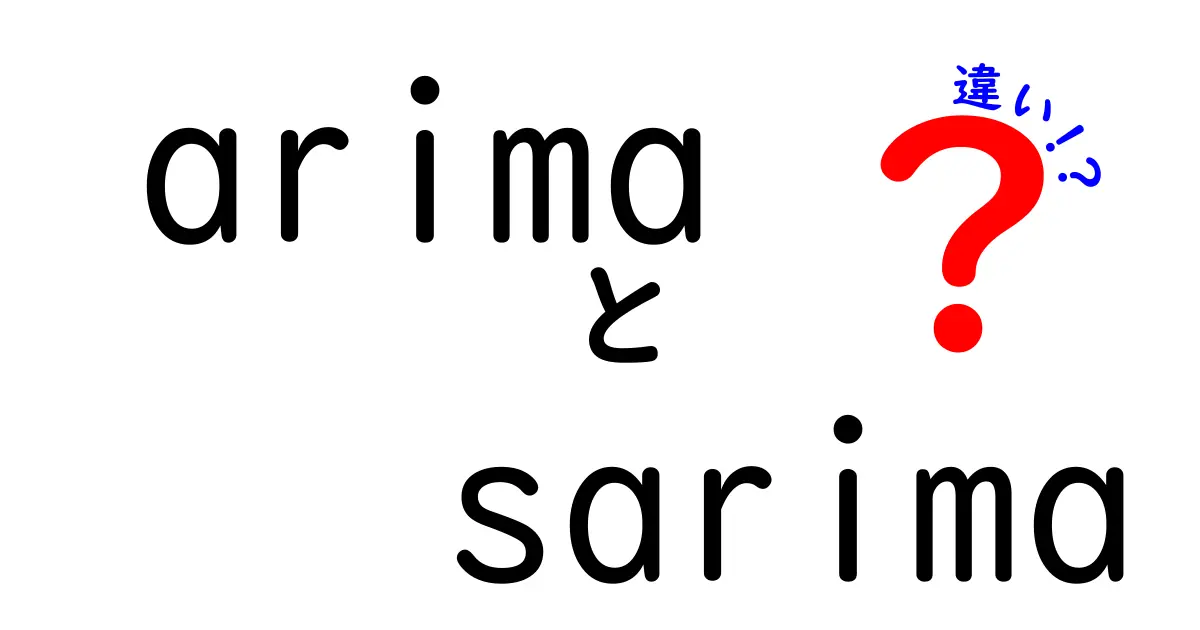

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ARIMAとSARIMAの基本を押さえよう
時系列データとは、時間の経過とともに連続して並ぶデータのことです。気温の変化、株価の動き、売上の推移など、過去の値を使って未来を予測したい場面で活躍するのが ARIMA というモデルです。ARIMA は3つの要素を組み合わせてモデルを作ります。まず 自己回帰 を表す AR、次にデータを安定化させるための差分を表す I、そして過去の予測誤差を現在の値に取り込む MA の3つの成分です。これらをパラメータとして p、d、q と表します。データが非定常(平均や分散が時間とともに変わる状態)な場合、差分を使って安定化させます。ただし d の回数が多すぎると本来の情報を失い、予測力が低下することもあります。モデルを選ぶときには AIC や BIC などの指標を使って、異なる組み合わせを比較します。
ARIMA は「季節性がない」データを前提として設計されており、季節的なパターンを別に扱う必要がある場合には他の手法を検討します。
ARIMAとSARIMAの違いを理解する
一方、SARIMA は季節性を扱える拡張モデルです。季節成分を表すパラメータ P、D、Q のほか、季節周期を示す m を追加します。これにより非季節性の ARIMA 部分と季節性の SARIMA 部分を組み合わせて、より複雑な時系列データを予測できます。季節周期が長いデータ(月次・年次・四半期など)に適しており、季節差分 D を使って季節性の非定常性を取り除いた後、非季節性の差分 d、自己回帰 P と移動平均 Q の組み合わせを探索します。季節性が強いデータほど SARIMA の恩恵が大きく、季節性がほとんどない場合は ARIMA で十分な場合が多いです。
実務ではデータの可視化、自己相関関数と部分自己相関関数(ACF/ PACF)を使った特徴の把握、そして AIC/BIC の比較を繰り返して最適解を探します。
データを観察する際には、まず時系列を可視化して季節性の有無を確認します。次に ACF・PACF を見て自己相関の傾向を把握します。季節性が認められる場合は SARIMA の導入を検討します。実務ではデータの分割、検証、パラメータ探索を自動化するツールを活用して、予測の再現性を高めることが重要です。最後にモデルの解釈性も大切です。単に予測値を出すだけでなく、どの要因が予測に影響しているのかを説明できると、ビジネスの意思決定にも役立ちます。
実務でのコツと注意点
ここでは実務でのコツを具体的に記します。まずデータを観察して季節性の有無を判断します。季節性がある場合は SARIMA の導入を検討します。季節の長さを決めるには月次データなら m = 12、週次データなら m = 52 など、データの周期を把握します。次にパラメータ探索を行います。p,d,q の組み合わせは小さく始め、AIC の推移を見て過学習を避けます。季節性と非季節性の両方を同時に最適化する場合は、SARIMA の P,D,Q と非季節性の p,d,q を同時に調整します。検証データでの予測精度を重視し、過去のデータに過剰適合しないように注意します。実務ではデータの欠損値処理、外れ値の扱い、差分の適用タイミングにも気をつけます。これらを踏まえると、ARIMAと SARIMA の違いは、季節性の扱い方の有無であり、データに合わせた最適なモデルを選ぶことが重要だと理解できるでしょう。
友人同士の会話風に小ネタをひとつ。SARIMA は季節性を別枠で扱える“季節のアイテム箱”のようなものだと考えると分かりやすいよ。例えば月次データで毎年同じ時期に売上が上がるとする。ARIMA だけだとこの“季節の波”を見逃してしまうかもしれない。そこで P、D、Q、そして季節周期を表す m を組み合わせて季節性の動きを捕まえる SARIMA を使うと、実際の動きに近い予測が可能になる。つまり、季節性を別のパーツとして切り分けて考える発想が、データの特性を活かすコツなんだ。実務ではこの切り分けがうまくいくと、予測の信頼性がぐんと上がるんだよ。
前の記事: « 回帰と重回帰の違いをわかりやすく解説!中学生にもできる簡単ガイド





















