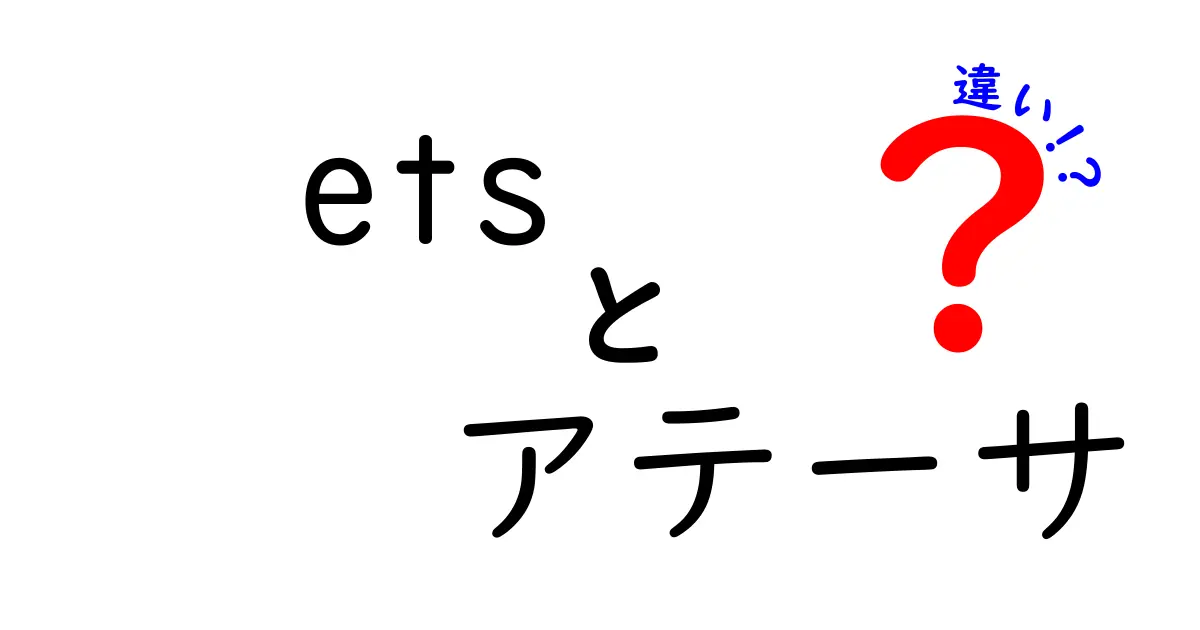

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ETSとアテーサの違いを知ろう:初心者向け解説
このテーマは車好きの人だけが興味を持つものではありません。
AWDのしくみを知ると、日常の運転や中古車選びが楽になります。
まずは結論から。ETSは電子制御のトルク分配機構の総称のひとつ、ATESSAは日産の正式な全輪駆動システムの名前です。
ET-Sという名称はETSの中のあるバージョンの代表的な呼び名です。
つまりETSとATESSAは同じ系統の技術を示す場合もありますが、名前と機能の細かさが違うのです。以下で順を追って詳しく見ていきます。
まずはETSの基本を押さえましょう。ETSはElectronic Torque Splitの略称であり、車が路面状況に応じて前後の車輪へどの程度のトルクをかけるかを電子的に決定する仕組みです。基本は前後のトルク配分を可変にすることが目的で、滑りやすい路面や急なコーナーでの安定性を高めます。
古い車ではASRやESCなどの電子制御と協調して動作します。
ただしET-Sが必ずしも全車輌で使われるわけではなく、車種や世代ごとに呼び名が異なります。
ETSは単体で動くのではなく、他の運転支援システムと組み合わせて使われることが多いのが特徴です。
ここでのポイントは、「トルクを配分するのは機械的なだけでなく電子の判断も入る」という点です。
次にATESSAの位置づけを整理します。ATESSAはAdvanced Torque Split Electronic Systemの略で、日産が採用する全輪駆動技術の正式名称です。基本思想はETSと同じく前後の駆動力を状況に合わせて分配することですが、ATESSAはより高度な制御と複数モードを持ち、車両の挙動をより積極的に安定させる機能を備えています。
車種によってATESSA-ETSやATESSA-E-TSといった派生名が使われ、路面状況に応じて前後のトルクだけでなく時には左右の車輪間の分配も調整します。
つまりATESSAは「ETSを含む一連の技術を統括する名札」であり、運転時の安心感とスポーティさの両方を両立させる仕組みだと考えると分かりやすいです。
表現を砕いて要点を整理すると、ETSは電子制御によるトルク分配の総称、ATESSAはNissanが用いる具体的な全輪駆動技術の名前です。そしてET-SはETSの具体的なバージョン名のひとつとして使われることが多い、ということになります。
この違いを知っていると、中古車や新車を選ぶ際に「どのような挙動を求めるか」を明確に伝えやすくなります。
ETSとは何かをはっきりさせるポイント
ETSは車両の路面状態に応じて前後のトルク配分を変える機能です。滑りやすい路面では後輪のトルクを増やして安定を取り、乾燥路では前後で適切な比率を保つことが基本の考え方です。この「適切な比率」は機械だけで決まるのではなく、電子制御ユニットが現在の状態を判断して微調整します。
さらに、他の運転支援システムと連携して動作することが多く、車全体の挙動を制御するうえで大切な役割を果たします。
この section ではETSの概要を押さえ、次のセクションでATESSAの具体的な特徴へと移ります。
アテーサ(ATESSA)とは?どんな車種に使われるのか
アテーサはNissanの全輪駆動技術の総称で、Advanced Torque Split Electronic Systemの頭文字を取った名前です。基本的な考えは前後のトルクを状況に合わせて自動的に分配すること、これにより直線だけでなくコーナリング時にも安定します。NissanのGT-Rをはじめ、多くの車種に搭載されており、〈ATESSA-ETS〉や〈ATESSA-E-TS〉といった派生名で語られることが多いです。
ATESSAは単なる前後の分配だけでなく、必要に応じて前後の駆動力を積極的に変える「躍動感」を与える点が大きな特徴です。
現在の自動車では電動化と組み合わさり、路面状況に応じた多様なモードを実現します。これにより、雪道や雨天での安定性が高まり、スポーツ走行時には車の挙動がより素早く、正確に出せるようになります。
ATESSAはET-Sのような基本的なトルク分配機能を核に、車両の挙動をコントロールする高度な制御を追加している点が大きな特徴です。同じET系の技術でも、ATESSAはより広い車種で高いレベルの安定性と運転感覚を提供します。この点はドライバーが感じる安心感にも直結します。
ETSとATESSAの違いを分かりやすく比較
まず名前の違いを押さえましょう。ETSは機能の総称、ATESSAは特定のメーカーが使う正式名称です。構造的にはETSもATESSAも“前後の駆動力を分配する仕組み”ですが、ATESSAはより高度な制御、複数のモード、そして車両の挙動をコントロールするための電子制御ユニットの役割が大きくなっています。
具体的には、ET-Sは古い世代で前後のトルク配分を比率で表現するのに対して、ATESSAは状況に応じた瞬間的な調整、時には左右の車輪間のトルク分配を変えることも可能です。
この差は実際の運転感覚にも影響します。雨の日にフロントが滑りやすい場合、ETSは配分を調整するだけ、ATESSAは場合によっては前後のバランスを積極的に変え、車の挙動を落ち着かせます。
続いて、実車での体感の違いを簡単に言えば、ETSは安定性を高める基本機能、ATESSAはスポーティさと安定性を両立させる高度な制御を提供する、というイメージです。車種や世代によってはATESSAの方が複数のモードを持っており、ドライバーが好みに合わせて挙動を変えられる点が大きな魅力です。
具体的な車種と体感の違い
実車の例としては、NissanのGT-Rのような高性能車にはATESSAの高度な制御が組み込まれており、急なコーナーやスポーツ走行時にも安定性とトラクションの両立を実感できます。
一方でET-Sの存在する車は、過去のモデルや入門的なAWD車で見られ、路面状況に応じたトルク配分を行いますが、ATESSAほどのモード切替や挙動制御の幅はないことが多いです。
運転者の感覚としては、ATESSA搭載車の方が「舵角に対する車の反応」がより直接的で、雪道や悪路での安心感が高いと感じやすい場面が多いでしょう。
このあたりは実際の試乗や中古車の説明書を読むとわかりやすくなります。車種ごとにATESSAのモードがどう設定されているか、ET-Sの名称がどのように使われているかを確認すると、同じAWD車でも運転感覚が違う理由が見えてきます。
まとめと運転時のポイント
ETSとATESSAの違いを理解すると、車の選び方や運転のコツが見えてきます。購入前には車両の仕様を確認し、ATESSAが搭載されているかどうかを確かめるのが大切です。実際の運転では、路面状況に応じたトラクションの変化を感じられる場面が多く、ブレーキの踏み方、アクセルの開き具合、コーナリングのライン取りが影響します。
経験としては、凍結路では前後の分配で安定を取る、スポーツ走行ではトルクの素早い移動で車の挙動を確認する、という順序で練習すると良いでしょう。
この知識は中古車を選ぶときにも役立ち、車選びの幅が広がります。
最後に押さえておきたい点は、ETSとATESSAは同じ系統の技術である一方、ATESSAはより高度な制御を意味する名称として使われることが多いということです。路面状況に応じたトルク配分と車両挙動のコントロールの違いを意識すると、車選びや運転の楽しみ方が広がります。
友人と自動車の話をしていて、ETSとATESSAの違いについて深掘りした雑談です。彼は“ETSはトルクの配分を電子的に調整する機能の総称”だと説明し、私に『じゃあATESSAはそれに加えて“前後の駆動を積極的に動かす”機能があるのか?』と尋ねました。答えは『はい、ATESSAは複数モードを持ち、路面状況に応じて挙動をコントロールする高度な連携を行う』というものでした。私たちはフェイルセーフの話や雪道の話をしながら、実際の運転感覚としての安定性の違いを想像して盛り上がりました。日常の運転にも、こうした細かな技術の違いが、突然の滑りやカーブでの安心感に直結するのだと再認識しました。
前の記事: « 線形回帰と重回帰の違いを徹底解説|中学生にもわかる基礎と見分け方





















