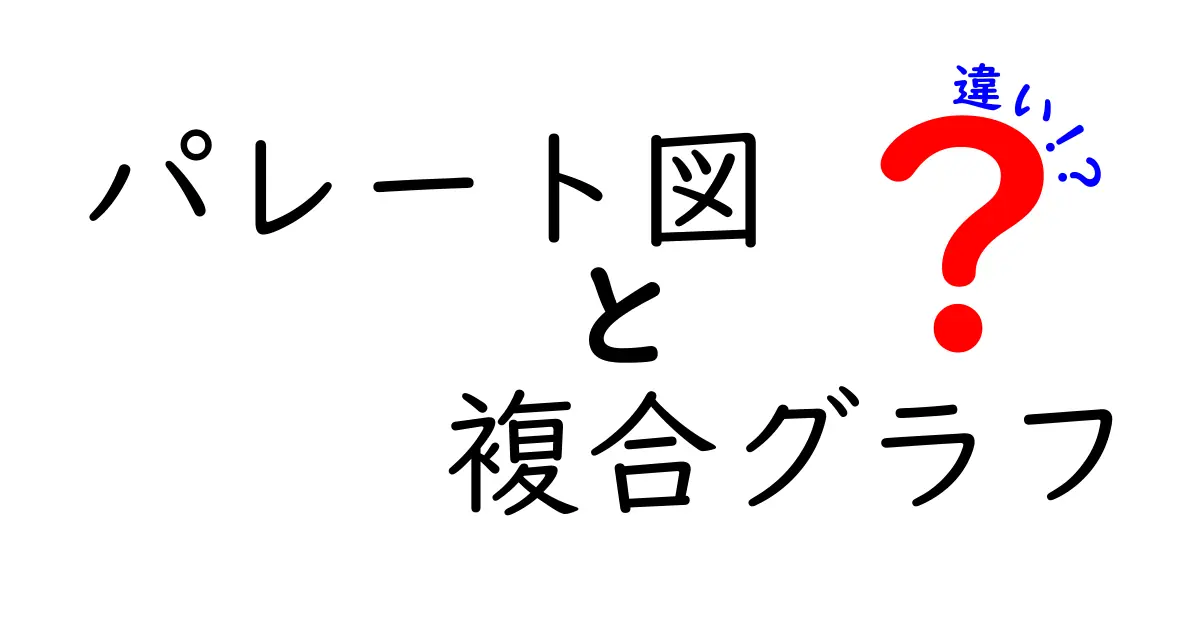

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
パレート図と複合グラフの違いを理解する
まず前提として、パレート図と複合グラフは「データを伝える道具」であり、同じデータでも見せ方が違います。パレート図は「重要な要素を上から順に並べる」特徴があり、問題の原因や影響の大きさを優先度で可視化します。複合グラフは、複数のデータ系列を一つのグラフに重ねて表示することで、相関関係や時系列の変化を一度に確認できます。読み手にとっての目的を考え、どちらを使えば伝えたい情報が伝わるかを選ぶことが大切です。
ここでは、両者の基本、作成時のポイント、使い分けのコツを丁寧に解説します。
この文章だけでは伝わりにくい部分もあると思いますが、例や注意点を織り交ぜながら、わかりやすく説明します。
特に中学生のみなさんには、専門用語をできるだけ避け、図の見方と意味を結びつけて理解できるように工夫しています。
パレート図とは何か
パレート図は、横軸に「要素のカテゴリ」縦軸に「頻度・影響の大きさ」をとり、要素を「大きい順」に並べた棒グラフと、上に積み上げる折れ線グラフを組み合わせた図です。この組み合わせは、80/20の法則、つまり「全体の80%は全体の20%の要素によって生み出される」という考え方を視覚化するのに役立ちます。棒の高さが各要素の大きさを示し、折れ線は累積の割合を表します。これにより、最初の数要素だけを対策すれば全体の問題の多くを解決できる、という結論を直感的に示せます。パレート図を作るときには、データを「カテゴリごと」に分け、値を適切に集計することが大切です。
さらに、データの単位や期間を統一することも重要です。こうしておくと、比較がしやすくなり、会議での意思決定がスムーズになります。
実務では、クレームの原因分析、品質管理、顧客の苦情の多いポイントの特定などに活用されます。
- 整理されたカテゴリ分けが鍵となり、複数のカテゴリが混在するデータを整理できる点が強みです。
- 80/20の考え方を具体的な根拠として示せるため、優先度の高い対策に資源を集中できます。
- データの透明性を高め、関係者全員が同じ認識で議論を進められる点が評価されます。
複合グラフとは何か
複合グラフは、同じグラフ上に異なるデータ系列を同時に表示するタイプの図です。例として、棒グラフと折れ線グラフを同じ軸上に描く「棒+折れ線」や、棒グラフと点線を組み合わせるケースがあります。目的は「複数の情報を同時に比較・関連づけて見る」ことです。例えば、月ごとの売上(棒)と成長率(折れ線)を同時に見ると、売上の変動と成長の動きがどのように関係しているかが分かります。複合グラフを作る際は、軸のスケールを適切に揃えること、色や凡例を分かりやすくすること、そして視覚的な混乱を避けるために不要な要素を削ることがポイントです。
データの性質によっては、二つ以上の縦軸を使う「Duplex(デュプレックス)」型の複合グラフも有効ですが、読み手が混乱しないよう、説明文を添えることが大事です。
ビジネスの現場では、売上と在庫、アクセス数と転換率、費用と利益など、さまざまな組み合わせが活用されます。
- 同じグラフ内に複数のデータを表示することで、相関関係がひと目で分かります。
- 軸の単位やスケールが崩れると読み間違いが起きやすいので、事前の設計が大切です。
- 色分けと凡例の工夫で、初心者にも優しい視覚表現となります。
違いと使い分けのコツ
パレート図と複合グラフは、目的が異なる場面で使い分けるべき道具です。パレート図は「原因の優先順位をつけたいとき」に強力で、問題の中で何を最初に手をつけるべきかを直感的に示します。一方、複合グラフは「複数の要素の関係性を同時に見たいとき」に適しています。ここで大切なのは、伝えたいことを明確にしたうえで、グラフの種類を選ぶことです。例えば、在庫の多い原因を特定して改善策を打つ場面ではパレート図が有効です。一方、月別の売上と広告費の関係を同時に見たいときには複合グラフが適しています。
また、データ量が多い場合には、要素をカテゴリごとにまとめて、「上位5〜10要素」に絞ってパレート図を作ると読みやすくなります。複合グラフでは、色の使い方を統一し、凡例を分かりやすく、軸の単位を揃えることがコツです。
結論として、使い分けは「伝えたいメッセージ」が何かを最初に決めることです。
- 伝えたい結論が明確であれば、図の選択が自然と決まります。
- 視覚的に重ねる情報が多すぎないよう、情報量を抑えることが効果的です。
- データの出典と前提条件を明記することが信用性を高めます。
実務の具体例と注意点
現場での実際の活用例を挙げておきます。例えば、顧客からのクレームの多い原因を特定する場合、まずパレート図を作って上位の原因を見つけます。次に、それらの原因のコストや影響を数値化して、優先度の高い要因に対する改善計画を立てます。これにより、少ない労力で大きな効果を狙えます。複合グラフは、年間の売上と広告費、または月間の訪問者数と転換率を同じグラフで示すことで、予算の最適化に役立ちます。ただし、複合グラフは多くの情報を一度に示すため、読み手が混乱しないように、凡例を明確にし、配色にも注意します。
加えて、データの出典や集計方法を明記しておくと、後で見直すときに役立ちます。データの整合性、期間の揃え方、単位の統一を最初に決めておくことが、分析を正確にするコツです。
- 実務ツールとしてExcelやGoogle Sheets、BIツールでの作成方法を学ぶと現場で役立ちます。
- 関係者にとって分かりやすい説明文と共に提示することが説得力を高めます。
- データの更新時には、同じ基準で再計算する手順を事前に決めておくと混乱を防げます。
友達とカフェで話しているとき、パレート図の話題になったんだ。彼は“20%の要素が全体の80%を生み出す”って聞くと、つい“そんな単純な話なの?”と眉をひそめた。でも僕は、実際の現場でその法則が働く瞬間を想像してみると納得できると伝えた。パレート図は、うまくいけば“最初の一歩”をとても強力に教えてくれる地図になる。複合グラフは、たとえば売上と広告費の関係を同じグラフで見せることで、見落としていた結びつきを見つける手がかりになる。結局、データをどう伝えたいかが道具の選択を決めるんだ、という話を彼とした。
次の記事: モールと自社ECの違いを徹底解説!初心者にもわかる選び方ガイド »





















