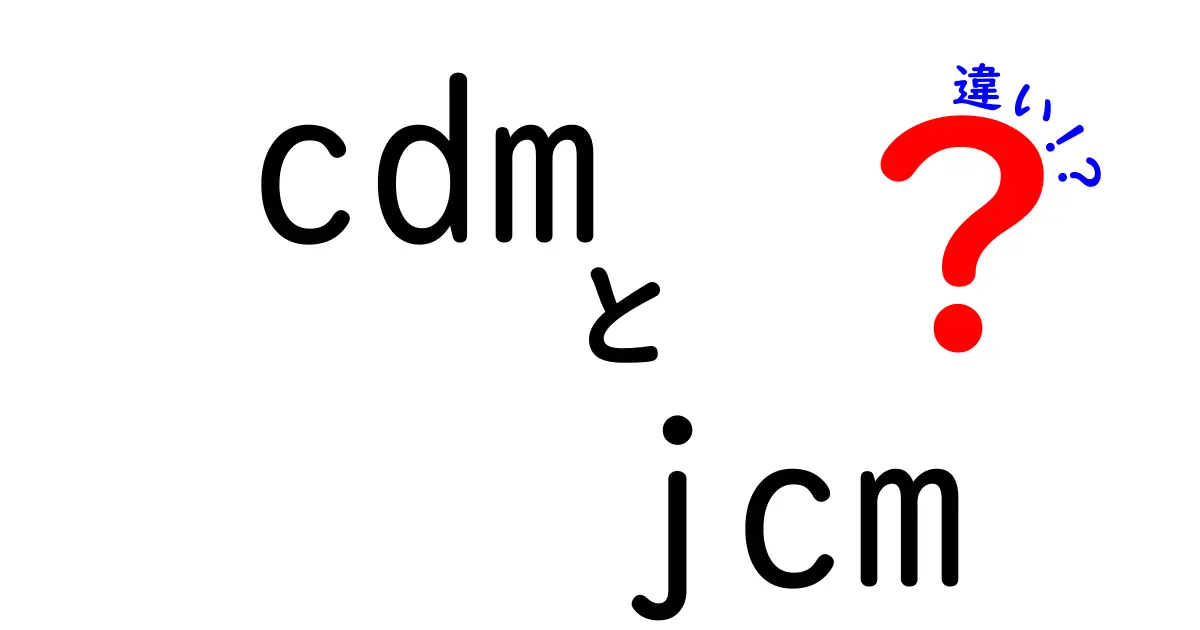

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
CDMとJCMの違いを徹底解説
CDMとは何か?
CDMとは、クリーン開発メカニズムの略称で、京都議定書の下で設けられた制度です。この制度の目的は、世界各国が温室効果ガスの排出削減を行う際に、途上国での削減プロジェクトを通じて排出削減量をクレジットとして創出・取引する仕組みを提供することです。具体的には、企業や自治体が発電所の効率化や再エネ導入などのプロジェクトを実施し、その削減分をCER(クレジット)として認証されます。
この流れによって、先進国は自国の排出削減義務を果たす手段を得る一方、発展途上国はクリーンな技術導入による経済的メリットを享受できます。
ただしCDMには厳格な条件と検証プロセスがあり、追加性の証明、持続可能性への影響評価、第三者認証などが不可欠です。これらの要件を満たさないプロジェクトはクレジット化されず、制度の信頼性を保つための厳密な審査が行われます。
CDMは過去の温室効果ガス削減の枠組みの中で重要な役割を果たしてきましたが、現在は新しい制度設計や他の機構との関係性の中で位置づけが変わっています。
この項目の要点をまとめると、CDMは京都議定書の枠組み内でのプロジェクトベースの削減クレジットを生み出す仕組みであり、追加性の証明・第三者検証・持続可能性評価などの厳格な条件をクリアする必要がある、ということです。
仕組みの全体像をつかむには、実際のプロジェクトの例をいくつか見ると理解が深まります。例えば、発電所の効率改善や廃棄物処理の最適化といった活動が対象になります。
今後も国際的な気候枠組みの変化とともにCDMの役割は再評価されていくでしょうが、歴史的には温室効果ガス削減の実務的な入り口として重要な意味を持っていました。
ポイント:京都議定書の下で設けられた枠組み、削減量をクレジット化、追加性と検証が必須、途上国での取組みを促進する役割がある。
JCMとは何か?
JCMとは、Joint Crediting Mechanismの略称で、日本と他国が協力して温室効果ガスの削減を実現するための枠組みです。国と国との二国間協力に基づき、先進国が技術・資金を提供する形で、相手国の排出削減を促進します。
CDMと比較すると、UNFCCCの公式な国際機関の認証だけでなく、二国間の合意と監視が中心になる点が特徴です。JCMの成果は「削減量」として蓄積され、関係国間でのクレジットとして活用されますが、国際的なCERとしての扱いは必ずしも同一ではありません。この点がCDMとの大きな違いです。
JCMの目的は、技術移転や資金協力を通じて、長期的に持続可能な発展と排出削減を両立させることです。
bilateral な協力関係の中で、現地検証・モニタリングが継続的に行われ、成果は政府間の合意に基づいて報告・評価されます。
JCMの利点は、迅速な導入と現地適用性の高さ、技術移転の促進、そして二国間の信頼関係構築に役立つ点です。一方で、CDMに比べて国際的なクレジット市場としての統一性が低いことや、適用対象の絞り込み・監視方法の差異など、実務上の違いも多くあります。
このような背景から、JCMは「二国間協力の成果を計測・活用する枠組み」として位置づけられ、各国のエネルギーセクター改革や技術革新の推進に寄与しています。
CDMとJCMの違いのポイント
ここでは主な相違点を分かりやすく整理します。
対象と認証機関:CDMはUNFCCCを中心とした国際認証、JCMは二国間の契約・監視。
適用範囲:CDMは主に発展途上国での削減プロジェクト、JCMは日本と相手国の協力を前提にしたプロジェクト。
信用の扱い:CDMの削減量は国際的なCERとして取引されることが多いが、JCMは二国間での合意に基づくクレジットとして活用される。
追加性と検証:CDMは厳格な追加性と第三者検証が必須、JCMも検証は重要だが制度設計は二国間の合意に依存します。
このような違いが、実務での適用先や意思決定のプロセスに大きな影響を与えます。
実務での使い方と注意点
企業や自治体がCDMやJCMを活用する際には、まず制度の適用条件と対象地域を確認することが重要です。CDMではプロジェクトの追加性証明、ベースライン設定、監査・検証の手続きが厳格です。JCMでは二国間の契約内容、監視体制、成果の評価方法が成功の鍵となります。
また、長期的なライフサイクルコストと技術移転の可否、現地の法制度や市場環境との整合性、現地雇用や地域社会への影響も検討する必要があります。
実務上の注意点としては、過度な期待を避け、実際に削減できる量の現実的な見積りとリスク評価を行うこと、第三者機関による検証をしっかり依頼すること、そして透明性の高い報告書作成を徹底することが挙げられます。
最後に、制度の最新動向を追い続けることも大切です。制度は時代とともに変わるため、最新のガイドラインや政府の発表を定期的にチェックしましょう。
まとめ
CDMとJCMは、いずれも温室効果ガス削減を促進する重要な枠組みですが、適用対象・認証機関・信用の扱いなど backside に違いがあります。CDMは国際認証を軸にした歴史ある制度で、JCMは日本と他国の二国間協力を軸にした現代的なアプローチです。どちらを選ぶかは、組織の目的、地域、技術力、法的要件、そして長期的な戦略に左右されます。
この違いを理解して適切な制度を選べば、環境面だけでなく技術移転や経済的効果も同時に得られる可能性が高まります。
今日は友達とカフェでcdm jcm 違いについて長めの雑談をしました。僕は、CDMが京都議定書の枠組みで生まれた“国際的に認証される削減クレジット”を生む仕組みだと説明しました。対してJCMは日本と相手国の二国間協力で技術移転を通じて削減を実現する枠組みで、UNの公式認証とは別の道をたどる点が興味深いと話しました。二つの制度には、認証機関の違い、信用の扱い方、適用範囲の違いがあり、実務ではこの差が導入の判断材料になると言われました。結局、どちらを使うかは目的次第ですが、両方を正しく理解することが、今後の環境ビジネスの成功には欠かせないと感じました。
次の記事: 排出基準と総量規制の違いを徹底解説|中学生にも分かる仕組みと実例 »





















