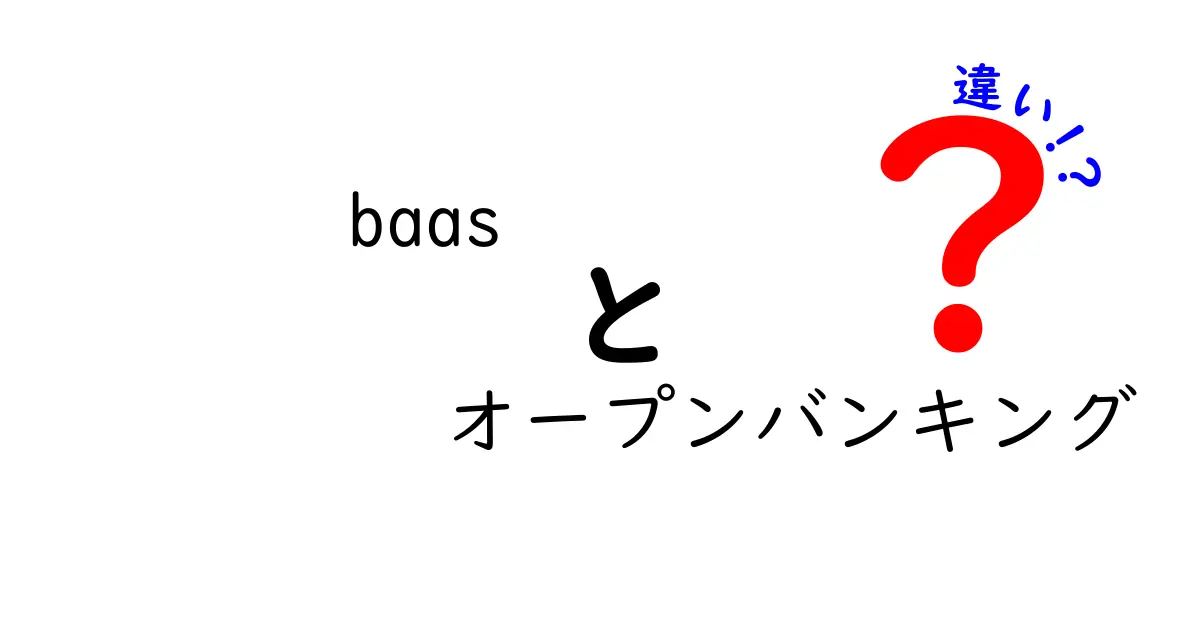

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:baasとオープンバンキングの基本を正しく理解しよう
ここでは「baas(Banking as a Service)」と「オープンバンキング」という言葉の意味を、専門用語が苦手な人でも分かりやすいように丁寧に解説します。baasは銀行機能をサービスとして提供する枠組みで、開発者や企業が自社のアプリに銀行の機能を組み込みやすくするための“部品セット”のようなものです。たとえば口座開設、残高照会、カード発行、決済、KYC(本人確認)といった機能を、APIという扉を通じて外部の相手が使えるようにします。これに対してオープンバンキングはデータの共有と決済の主体を開く仕組みであり、顧客の同意のもと第三者の業者が口座情報を取得したり、支払いを代行したりできるようにするものです。要はbaasは「銀行の機能そのものを外部に提供する技術・サービス」、オープンバンキングは「その機能を使ってデータや支払いの自由度を高める制度・仕組み」です。
両者は目指すゴールが違います。baasは金融機関が自社の銀行機能をコアとして外部に提供することで、顧客の新しい体験を実現することを重視します。一方、オープンバンキングは競争を促し、消費者が自分のデータをコントロールしながら新しいサービスを見つけられるようにすることを狙います。ここが混同されやすいポイントですが、それぞれの「誰が、何を、どのように使えるか」という視点で分けて考えると理解が進みます。
違いその1:提供するものの範囲と目的
baasは「銀行機能そのものを組み込むための土台」を提供します。口座関連の機能、カード、支払い、KYCの自動化など、銀行業務の中核を外部パートナーが呼び出せるようにします。これにより、従来は金融機関自体が自社で作るか、専門のシステムを導入するしかなかった機能を、短期間・低コストで自社のサービスに組み込めるようになります。開発チームは自前で銀行機能をゼロから作る必要がなく、UXに集中できます。オープンバンキングはどうかというと、主にデータアクセスと決済の連携に焦点を当てます。顧客の許可を得て、口座情報、取引履歴、残高などを他社と共有したり、代金決済を第三者が起動できるようにする仕組みです。ここでの目的は“新しいサービスの創出と競争の促進”であり、機能そのものを自分のアプリに組み込むかどうかは別の話です。
つまりbaasは技術的な基盤、オープンバンキングは制度的な枠組みです。扱う対象も役割も異なるため、両者を同じ土俠で語ることは適切ではありません。baasを使えば自分のアプリに即座に銀行機能を追加でき、オープンバンキングを利用すれば他社のデータや支払いを使った斬新なサービスを作ることができる、というのが現代の金融ソリューションの要点です。
違いその2:使われ方とビジネスモデル
現場の利用場面を想像してみましょう。baasはスタートアップや企業が自社ブランドの金融機能を短期間で市場に出すときに選ぶ“エンジン”です。自社のアプリに口座機能やカード機能をつけたい場合、開発工数を抑えたい場合に有効です。提供側は銀行としての規制やコンプライアンスを担保しながらAPIを通じて機能を提供します。対して、オープンバンキングは消費者が自分のデータを使って新しい金融サービスを探したり、複数のサービス間で支払いを一本化したりする場面で活躍します。データの透明性と同意管理が重要な要素であり、規制はデータの扱い方と安全性を厳しく見守っています。ビジネスモデルの違いも大きく、baasは機能提供の対価としてのライセンスやAPI使用料が収益の柱になることが多く、オープンバンキングはデータアクセスの枠組みを提供することで新しいサービスの生態系を育てること自体が目的となります。
ただし、現実にはこれらの境界は少しずつ曖昧になりつつあります。いくつかの企業はbaasの枠組みを使いつつ、同時にオープンバンキングのデータを活用してハイブリッドなサービスを提供するケースも増えています。規制の変化や市場のニーズに応じて、どちらを選ぶべきかは企業の戦略次第です。ここで大切なのは、“自社の顧客体験をどう変えたいのか”を明確にし、それに最適な道具を組み合わせることです。
表で見る比較と選び方
下の表は、baasとオープンバンキングの主な違いを要点だけでも把握できるように作りました。表は読みやすさのために簡略化していますが、実際には提供元ごとに機能の範囲や規制要件が異なることがあります。導入を検討する際には、必ず自社の要件をリスト化し、複数のベンダーから実際にAPIのサンプルや契約条件を取り寄せて比較してください。
特に法規制の遵守状況とデータセキュリティの水準は、後から大きなリスクとなることがあるため、第一優先で確認しましょう。
以下の表は、最も基本的な観点を2つの枠組みで比較したものです。実務では「機能範囲」「データアクセス」「コンプライアンス」「開発期間」「コスト」といった観点を追加して評価します。
この表を見ながら、次のような質問を自分に投げかけてください:「自分たちの顧客はどんな体験を欲しているのか?どの機能を早く出すべきか?」。それに答える形で、実現したいユーザー体験から逆算してベンダー選定を進めるのがベストです。
ねえ、さっきの話をもう少しだけ深掘りしてみよう。オープンバンキングって、ただデータを開く制度だと思われがちだけど、実は日常のアプリ開発にもぐっと近づく話なんだ。僕たちがスマホで銀行アプリを使うとき、違うサービス同士が連携して決済がスムーズになるのは、Open Bankingの力のおかげ。データの同意管理やセキュリティの工夫が、私たちの生活の安全と利便性を両立させてくれる。そして、baasはその裏側で働く“エンジン”で、サービスの速度と品質を左右することになる。





















