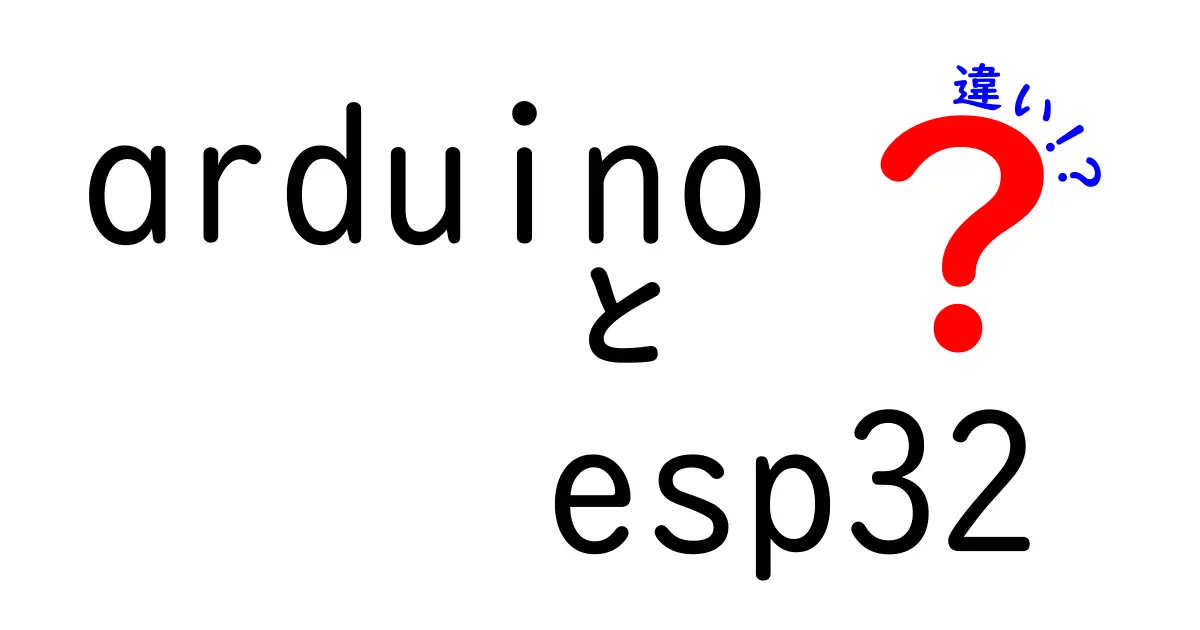

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ArduinoとESP32の根本的な違いをざっくり把握する
結論から言うと、Arduinoは「シンプルさと安さ」が魅力で、ESP32は「機能の多さと速度」が魅力です。Arduinoの主力ボードはATmega328Pを搭載しており、周波数は16MHz、RAMは約2KB、フラッシュメモリは約32KB程度です。これに対してESP32はデュアルコアのXtensa LX6系CPUを搭載し、最大周波数は約240MHz、RAMは約520KB、外部フラッシュは4MB以上など、大容量のメモリとストレージを持っています。
さらにWi-FiとBluetoothが内蔵されている点はESP32の大きな強みです。
開発環境も少し異なり、Arduino IDEは直感的で初心者に優しく、豊富なライブラリが揃っています。
一方ESP32はPlatformIOやArduino IDEを使って開発できますが、設定やデバッグの幅が広く、初めての人には少し難しく感じることがあります。
ここで大事なのは「用途と必要な機能の組み合わせ」です。例えば、光センサーを読み取ってLEDを点灯させる程度の小さな回路ならArduinoで十分です。
ただし家庭内に接続するIoTデバイスを作る、複数の機器をネットワークにつなぐ、あるいはスマートフォンやクラウドと連携するような機能を要する場合はESP32の機能が大いに役立ちます。
この基本的な理解があれば、学習の壁を下げつつ、予算と用途に合わせた選択がしやすくなります。
以下は代表的な違いを分かりやすく整理した表です。
具体的な使い分けと開発環境の違い
実務的には、IoTデバイスの試作や教育現場ではArduino UNO系が手軽です。
一方、クラウド連携や複数デバイスの同時制御、センサーの高頻度データ処理を要する場合はESP32の方が作業が楽になります。
例えば温度や湿度を測ってクラウドへ送信するデモを作るとき、ESP32の内蔵Wi-Fiを使うと配線作業が減り、開発の全体像を早く掴めます。
Bluetoothを使ってスマホとデータ交換したい場合もESP32はそのまま対応します。
開発環境の選択肢としては、Arduino IDEは学習の入口として最適です。
初心者向けのセットアップも豊富で、公式やコミュニティが提供するチュートリアルを順番に追えば基本が身につきます。
一方で複数のボードを同じプロジェクトで管理したい、CI/CDのような開発プロセスを取り入れたいときにはPlatformIOを利用すると便利です。
購買計画を立てる際は「コスト」「機能の必要性」「今後の拡張性」をバランスさせましょう。
最後に覚えておきたいのは、どちらのプラットフォームも学習リソースが豊富で、コミュニティが活発だという点です。
最初は小さな課題から始めて、徐々に機能を追加していくのがコツです。
ねえ、ESP32のWi‑Fi内蔵って本当に楽だよね。でも振り返ると、ひと昔前のArduinoみたいなモジュールを使う構成とは違い、ESP32は電源管理やセキュリティの扱いも少し複雑になる場面があるんだ。私の中では、まずはArduinoで基礎を固め、次にESP32へステップアップするのが自然な流れ。小さな成功体験を積み重ねると、インターネットへデータを送る仕組みやBluetoothでの通信の感覚もつかめる。結局は「学習の余白をどう埋めるか」が成長の鍵だと思うな。





















