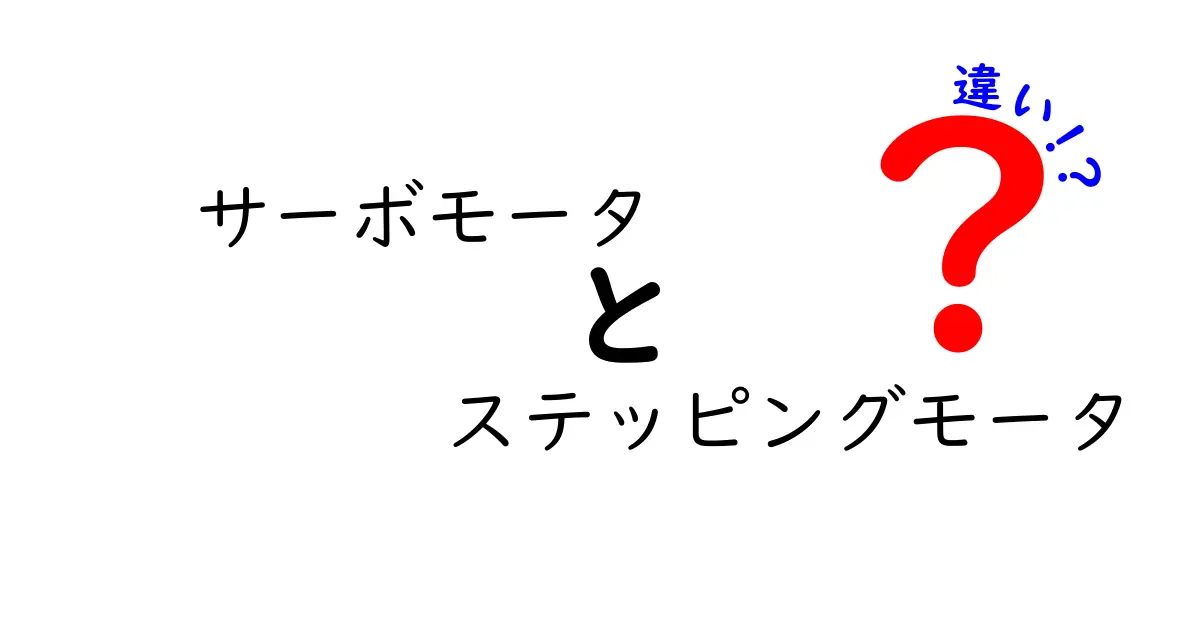

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
サーボモータとステッピングモータの違いを徹底解説!中学生にもわかるポイント比較
サーボモータとステッピングモータは回す機械の心臓のような存在です。どちらも「回す」を仕事にしますが、仕組みや使い方にはかなり違いがあります。本記事では中学生にも理解できるよう、図を描くように具体例を盛り込みながら違いを説明します。まずは基本的な仕組みの違いから見ていきましょう。
サーボモータは回転位置を常に知る仕組みが組み込まれておりエンコーダと呼ばれるセンサで現在の角度を測ります。制御回路は望む角度と現在の角度の差を受け取り信号を微調整します。この閉ループのアプローチにより負荷が変化しても正確さを保ちやすく長時間の運転でも安定性が高くなります。
またトルクの安定性や応答速度を細かく調整できる点も魅力で設計の幅が広がります。一方のステッピングモータはエンコーダを使わずとも動かせる点に魅力があります。ロータが複数の固定角度で刻まれる設計のためパルス信号を順番に送るだけで所望の角度へ進みます。複数のステップを積み重ねることで回転を作り出せるため、シンプルな制御と低コストで機械を動かせます。
しかし負荷が急に変わると回転がずれて振動が出やすくなり位置決めの誤差が増えることもあります。これらの違いは実際の機械を選ぶときの大きな分かれ道です。
1. 仕組みと基本動作
サーボモータは動かしたい角度を決める指令を受けるとエンコーダから返ってくる現在の角度情報とを照合して、必要な回転量を決定します。エンコーダは高精度なたとえば回転数を測れるセンサで、回転軸の位置を分解能の高い単位で読み取ります。制御回路はこの差をもとにモータへ送る信号を連続的に微調整します。これにより回転が遅くなっても早くなっても、狙った位置へ正確に戻ることができます。さらに servo では速度制御や位置フィードバックを組み合わせることで、荷重がかかったときの追従性を高めることができます。
いっぽうステッピングモータは基本的に開ループで動作します。 rotor は固定角度を刻むステップを順次増やしていく形で回転します。パルス信号の数がそのまま角度に対応するため、制御が比較的シンプルで回路も安定して組みやすいのが特徴です。エンコーダを付けると制御系を変えることで精度を高めることも可能ですが、それには追加の回路設計とコストが必要になります。
2. 制御方式の違い
サーボモータは基本的に閉ループ制御を前提としています。現在の位置を読み取るエンコーダと指令値を比べて差を補正するため、外部の負荷変動や摩耗による角度ずれを自動的に補正します。これにより高い正確さと追従性を保てます。反対にステッピングモータは開ループのまま運用されることが多く、外力によるズレを自分の力だけで直すことはできません。信号のパルスを増やせば角度は増えますが、負荷が大きく変わると回転が止まってしまうこともあります。そこで近年はマイクロステップと呼ばれる細かい分割を使って一歩一歩の角度を細かく刻み、振動を減らす工夫がされています。
3. 長所と短所
サーボモータの長所は高い正確性と安定性です。荷重が変わっても位置を保つ力が強く、速度も広い範囲で安定します。応答の速さを調整できる点も魅力です。その一方で部品が複雑でコストが高く、設計と保守の難易度が上がる点が短所として挙げられます。製品としては自動車や工作機械など高い精度が求められる領域で活躍します。ステッピングモータの良さは、まず第一にコストの低さと構成のシンプルさです。開ループ設計のため動作が予測しやすく、初心者の学習用としても適しています。保持トルクは低速域で強い一方、長時間の連続運転では熱がこもりやすくなる点が難点です。さらに振動が出やすい場面があり、静音性も個体差が大きいことがあります。
4. 実際の選び方と注意点
機械を選ぶ際にはまず用途をはっきりさせます。高精度と高速応答が必要ならサーボモータが向きます。コストを抑えつつ簡単に回すだけならステッピングモータが適しています。次に重要なのは荷重特性と速度域の確認です。トルクがどのくらい必要か、最高速度はどのくらいか、荷重が変わるときの追従性はどうかを実機で想定して調べます。表面的にはステップ角やマイクロステップなどの仕様を見ますが、実際には制御系の設計が最も影響します。配線の工程、冷却の仕組み、回路の信頼性についても検討しましょう。最後に予算と保守性のバランスを考え、長期的なコストを見積もることが大切です。
5. 表での比較とポイント
以下の表は両者の主要な違いを要点としてまとめたものです。なお個体差や製品の仕様によって数値は変わるため、実際の選定時にはデータシートをよく確認してください。表はあくまで目安です。表の情報を踏まえたうえで具体的な用途に合わせた設計判断を行いましょう。
4. 実際の選び方と注意点のまとめ
要点をもう一度まとめます。ポイントは三つです。第一に用途と求める性能をはっきりさせること。第二にコストと保守性のバランスを考えること。第三に実機での検証を重ね、負荷変動時の挙動を確認することです。これらを踏まえれば初心者でも自分の機械に最適なモータを選ぶ道しずみが見えてきます。モータの世界は奥が深いですが、基本を押さえれば身近な機械の仕組みをもっと楽しく理解できるようになります。
5. まとめとポイント
サーボモータとステッピングモータは似ているようで使い方が大きく異なります。閉ループで高精度を得られるサーボモータは高コストですが荷重変動に強く安定します。開ループのステッピングモータはシンプルさと低コストが魅力で学習や小型機器に最適です。選択のコツは用途の要件を明確にしデータシートの数値だけでなく実機の特性を体感して判断することです。
放課後の部室で友達とモータの話をしていた。私はサーボモータの話をするとき必ずエンコーダのことを思い出す。エンコーダがあるからこそ位置を正確に測れるし制御回路は最適な信号を出せる。反対にステッピングモータはエンコーダがなくても動くが負荷が変わるとズレや振動が生じやすい。あるロボット工作キットではステッピングで十分な場面もあるが、正確さを要求するロボットの手足にはサーボが必要になる。コストと性能のバランスをとるのが技術の取り組みだと感じた。たとえば速く動かすときにはサーボは安定した追従を保ちやすい。一方でステッピングは静かな動作は得意だが負荷が増えると熱と共振で性能が落ちることがある。結局は用途次第で最適解が変わる。
前の記事: « fpga マイコン 違いを徹底解説!初心者でも分かる選び方ガイド





















