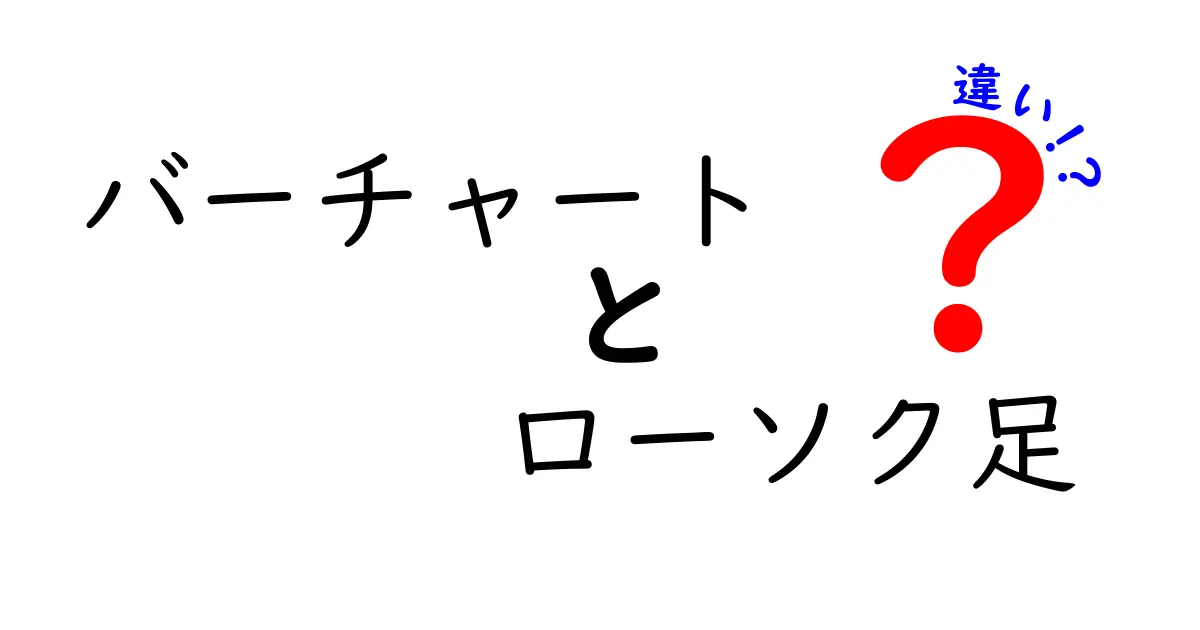

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
バーチャートとローソク足の基本を押さえる
この項目ではバーチャートとローソク足の基本的な考え方を、難しく感じる人にも伝わるように丁寧に説明します。まずは両者がどんな情報を伝えるのかを押さえましょう。バーチャートは縦棒の形で、ある時間帯の始値・高値・安値・終値を並べて表示します。横軸には時間、縦軸には価格が並び、長さや位置で値幅の大きさが分かります。これはシンプルで直感的な見方ができ、特に日々の変化をざっと掴むのに適しています。
一方のローソク足は棒の実体とヒゲで、同じOHLCという情報をもう少し視覚的に提示します。ボディの色が上昇か下降を示し、長いヒゲはその時間帯の最高値・最低値までの動きを強調します。こうした見方の違いが、使う場面を分ける理由になります。
次に、どんな場面でどちらを選ぶと良いのかを考えてみましょう。たとえば短い時間足で細かい動きを追いたい場合、ローソク足の色の変化や陰陽の連続性が直感的に理解しやすいです。反対に長期間の動向を大まかにつかみたいときは、バーチャートのシンプルさが有利です。さらに価格の動きを「四つ値 OHLC」という同じ情報セットで表す点は共通しており、理解の出発点として役立ちます。バーチャートはラインのように一本の柱で特徴を伝えるため、混雑した情報を整理するのに向いています。ローソク足は日をまたいだ変動を「実体」と「ヒゲ」で二重に強調するため、短期の反発や押し戻しを見つけやすいことがあります。
ここまでの説明を踏まえて、実際に画面を見ながら練習してみると理解が深まります。まずは過去数十日分のデータで同じ期間のバーチャートとローソク足を並べてみましょう。気になるポイントを見つけたら、次の問いを立ててみてください。この情報は短期のトレード判断に使えるか、長期の傾向の把握に適しているか、視覚的に読み取りやすいのはどちらか。こうした観点を自分の感覚に結び付けると、自然と使い分けが身についてきます。
ここまでで基本的な考え方を身につけることができます。最初は両方のチャートを並べて見比べ、どちらが自分にとって使いやすいかを探るのが良い練習です。実務での応用を考えるときには、データの時間軸を変えてみると新しい発見があるかもしれません。長所と短所を理解し、好き嫌いだけで選ばず自分の目的に合わせて使い分けてください。本文中のポイントは以下のとおりです。
・バーチャートはシンプルで長期的な動きを掴みやすい
・ローソク足は色と実体で短期動向を直感的に読み取りやすい
・OHLCの基本情報は両方のチャートで共通して重要
小ネタ:雑談で深掘りするバーチャートとローソク足の話
\nある日、放課後に友だちと学校の端末で株価チャートを眺めていたときの会話です。私たちは同じデータを見ているはずなのに、どちらを使うかで感じ方が少し違いました。友だちAは「ローソク足の色がついているから、今日は上がりそうかどうかが分かりやすい」と言います。一方で友だちBは「バーチャートの線の太さと位置関係が、長期の動きをつかむのにいい」と主張しました。私はこのとき、どちらも正解だと感じました。結局、読み方のコツは二つのチャートを同時に見る練習を重ねることです。ある程度データに慣れると、ローソク足の陰陽とバーチャートの値幅の両方を組み合わせて判断する癖がつき、判断材料が増えていきます。雑談の中にも学習のヒントが詰まっていて、友だちとの会話こそ、理解を深める良い機会になると感じました。
\n




















